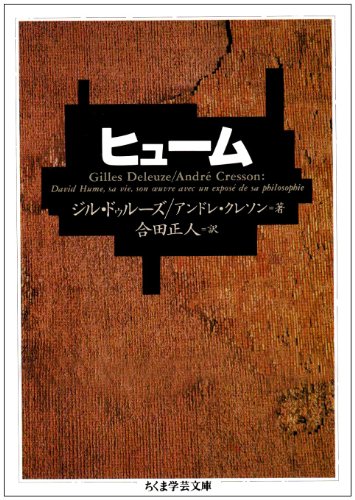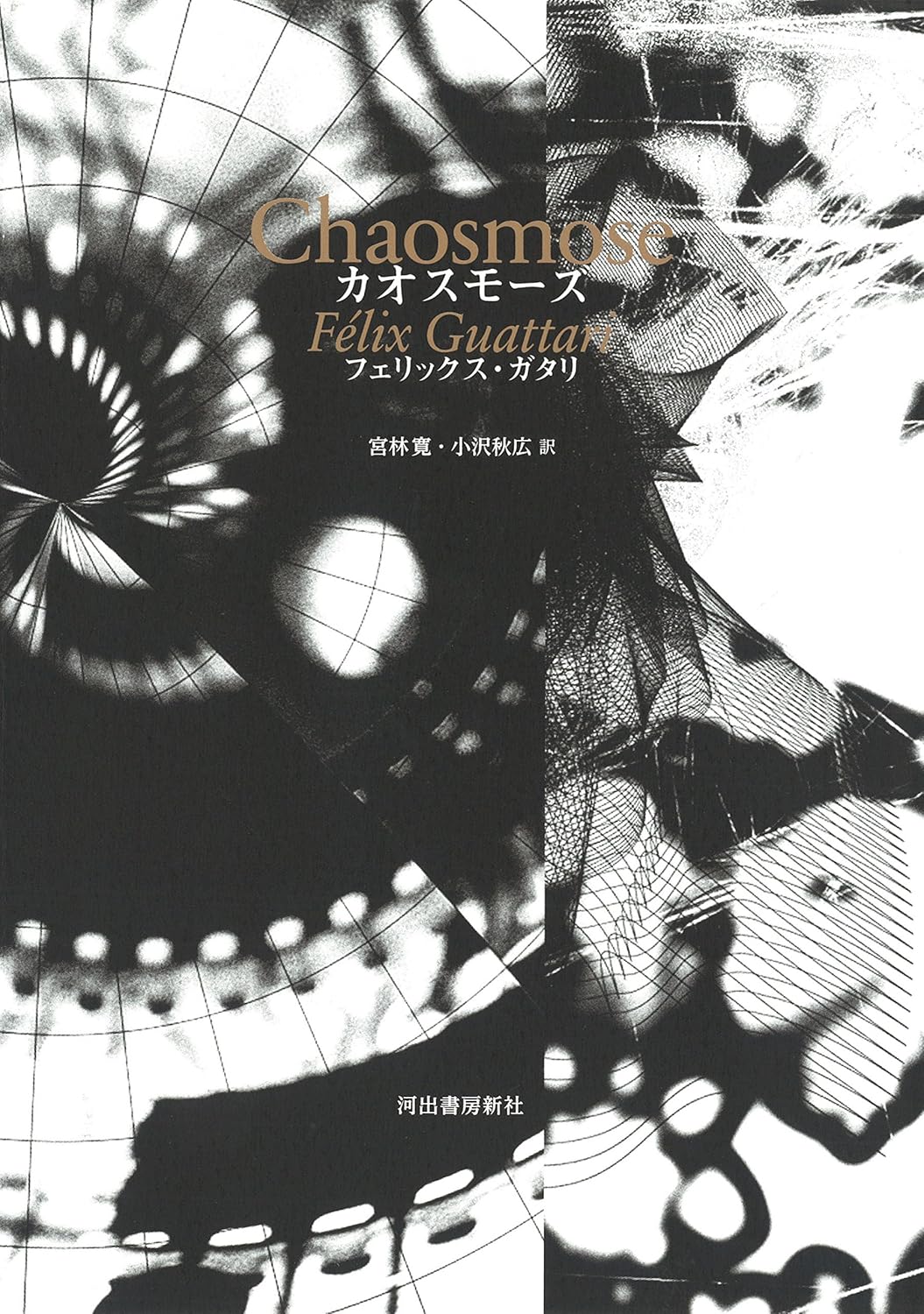即興する心とAIの因果
第5回 創造はカオスと交截することから生まれる

目次
機械は人と同じ知能を持つか
冒頭に挙げたニック・チェイターはヒュームの次のフレーズを引用する。「私が自分自身と呼ぶものの最も近くに入っていくとき、熱や冷たさ、光や影、愛や憎しみ、苦痛や快楽といった特定の知覚と決まって出くわす。何らかの知覚抜きに自分自身なるものは決して捉え得ないし、知覚以外のどんなものも決して観察し得ない」(『人間本性論』)。
その上で、思考のサイクルの観点から、意識的経験とは意味を持つように整理統合された感覚情報を経験することであり、感覚世界にない自己というものを意識することはナンセンスだと断じる。
脳が知覚できるのは、自己について語る声や、書籍や液晶画面に映る文字だけであり、その背後にある思考を意識することはできない。
脳が知覚するものは文字だけであり、その内奥にあるものを知覚することはできず、言葉の背後の心というものは、なおさら意識することができないとする。
またチェイターは、メタレベルで意識を観察する高次意識の存在も否定する。
フラットな心は、バラバラで省略されたイメージや音声、言葉といったものしか意識できない。
バラバラのピースに意味づけを行い、即興でまとめあげる柔軟な想像力こそが人の知性だとチェイターはいう。
それゆえに、彼は現在の計算機的な人工知能は、人のように前例を拡大し、混交し、再設計する人のような生物学的知性とは別のもので、実現できるとしてもずっと先のことだという。
この考えは、ジェフ・ホーキンスが「現行のAIには“I(Intelligence)”はない」とする論旨にも附合する。
ホーキンスのいう人の知能の特性は、絶えず動きによって学習し、多くのモデルを持ち、知識を座標系に保存することである。
これらの特徴を持ち、新しい課題を素早く学習し、異なる課題間の類似性を理解することで、未知の問題を柔軟に解決できるようになれば、機械知能としてのAIはAGI(Artificial General Intelligence:人工汎用知能)になりえるとする。
ベルクソンのいう“エラン・ヴィタール”のような生命の跳躍が過去のものとなった現在、そしてAGIが到来する未来のいつかの時点では、AGIは意識を持つとみなされて“ハード・プロブレム”どころか、問題ですらなくなるという。
またホーキンスは、AGIが人類の脅威となる未来は到来しないだろうという。知能と合理性を司る“新しい脳”にたいして、人々を脅かす欲望や感情を司るのは“古い脳”の役割なのがその理由である。あくまでも、人がそれを意図的に埋め込まない限りではあるが。
D.ヒューム (著)
木曾 好能 (翻訳)
法政大学出版局
ISBN:978-4588121913
高みも深みも存在しない場から生成する主体
メタ視点から観察するものの否定は、理性そのものをメタ視点から考察する超越論的観念論との齟齬を来すようにみえる。
実際に哲学者ジル・ドゥルーズは、カントの認識論が持つ感性と悟性の二元性が差異を外的存在とみなし、認識のプロセスを問うことから遠ざけてしまう点を批判するとともに、ヒュームの経験論を主体と自然との連続性を示した“超越論的経験論”として再評価している。
ドゥルーズのヒューム探求は、同じく哲学者アンドレ・クレソンとの共著として1952年に出版された『ヒューム』(合田正人訳/ちくま学芸文庫)と、最初の単著である『ヒュームあるいは人間的自然―経験論と主体性』(木田元他訳/朝日出版社)において、キャリア初期から行われている。
ヒュームにとって、精神の原初的な状態は感覚的印象と感覚的観念である。感覚的印象とは諸器官の知覚からもたらされた感覚であり、感覚的観念とはその印象が想像力によって再生産されたものである。
印象と観念とはバラバラに生成されるものだが、それらを高次から観察して整理する主観、つまりカントのいう超越的もしくは先験的な視座は存在せず、精神とは無秩序な観念そのものであるとドゥルーズは論じる。
ドゥルーズにとって主体が構成されるということは、印象と観念とが自然な原理において恒常的な運動へと生成されることである。
その生成のプロセスをもたらすものは、感覚的観念に反応する反省的印象としての感情であり、ドゥルーズはこれが主体にとって合目的な行動をもたらすとした。
また反省的印象は反省的観念をもたらすことで、印象と観念の動きが繰り返されるとする。印象と観念との自然な原理――人間の内的自然つまり本性――には2種類あり、1つは先に述べた感情、そして2つめがヒュームのいう、類似・近接・因果の動的な関係観念連合であるとされる。
人間の内的自然においては、超越論的な高みから、あるいは心理的な深みからは説明し得ない。
これもまたニック・チェイターのいう“平板な心”に近似してはいないだろうか。
ジル ドゥルーズ, アンドレ クレソン (著)
合田 正人 (翻訳)
ちくま学芸文庫
ISBN:978-4480085429
ジル ドゥルーズ (著)
木田 元, 財津 理 (翻訳)
河出書房新社
ISBN:978-4309242231
カオスと交截する脳
ドゥルーズは、1991年に刊行された精神科医フェリックス・ガタリとの最後の共著作『哲学とは何か』(財津理訳/河出文庫)においてもヒュームを援用して論じている。
同書では、人が法則や秩序を好むのは、カオスから身を守るためであるとする。忘却される、もしくは制御不可能な諸観念のなかに投げ込まれるという不安こそが人には耐え難いとしたうえで、その観念の消失と出現こそが無限の変化可能性を生じさせる場であるという。
同書では、思考の3つの形態として芸術と科学、そして哲学を挙げて、それぞれがカオスの上に平面を描くことでカオスに立ち向かうとする。
3者においてそれぞれが欲するのは、芸術においては有限なものを創造して無限なものを回復すること、科学においては準拠軸を得るために無限なものを放棄して座標平面を描くこと、哲学においては概念を無限なものを担う内在平面を描くことであると措定する。
それぞれは交差し絡み合うものの、そこには総合も同一性もない。
芸術は芸術に属する感覚をもって作品をつくり、科学は科学に属するファンクションをもってモノの状態を構築する。また哲学は哲学に属する概念をもって出来事を出現させようとするという。
しかし、3者が新しいものとなるのは、それぞれがカオスと交截する場であると彼らはいう。
芸術においては、カオスのかけらを捕まえてフレームに入れ、クリシェ(紋切型の表現)を超えることで、これまで予想されなかった合成されたカオスを構成する。
この合成されたカオスについては、のちにガタリは遺著となる単著『カオスモーズ』(宮林寛他訳/河出書房新社)において、カオス(chaos:混沌)とコスモス(cosmos:秩序)がオスモーズ(osmose:相互浸透)して自己複製が生じる場としてさまざまな観点から論じている。
また科学が活気づくのは、変化の可能性を決定論的計算や確率論において平衡の諸中心に戻すときであるとされ、例として散逸系におけるカオス(ストレンジ・アトラクタ)が挙げられる。
そして哲学はといえば、理性やコギトを前提とすることを諦めて、内在平面の上にそれらを位置づける概念を生み出すことだとする。
そして、ドゥルーズとガタリは芸術・科学・哲学の3つの平面の接合が脳であるとして、現象学に逆らって「人間ではなく脳が思考する」と主張する。
脳は生物学的器官であるとともに精神そのものであり、カオスと秩序の境界で新しい概念や可能性を産出する場であり、非概念的概念や非思考的思考といった識別不可能かつ真偽の決定が不可能なものを生成する創造的な場であるとした。
本書では人工知能についても述べられており、AIは確率論的プロセスや安定アトラクタをモデル化するロジックを有しているものの、思考に至るまでにはカオスに由来する状態やカオス的アトラクタに到達しなければならないとして、コンピュータ・サイエンスが進化するためにはカオス的もしくはカオス化的なシステムを想定する方向を目指すべきだという今日的課題も記されている。
脳を模したディープ・ニューラル・ネットワークに基づき“生成AI”と呼ばれているAIはやがてカオスの縁で格闘する真の“生成”を成すことができるのか。もしくは他のものがそれを可能にするのか。そしてそのとき、人はなにを認識することができるのか――いま私たちが考えるべきことの1つは、そこにあるのではないかと思う。
<了>
G・ドゥルーズ, F・ガタリン (著)
財津 理 (翻訳)
河出書房新社
ISBN:978-4309463759
フェリックス・ガタリ (著)
宮林寛, 小沢秋広 (翻訳)
河出書房新社
ISBN:978-4309248165