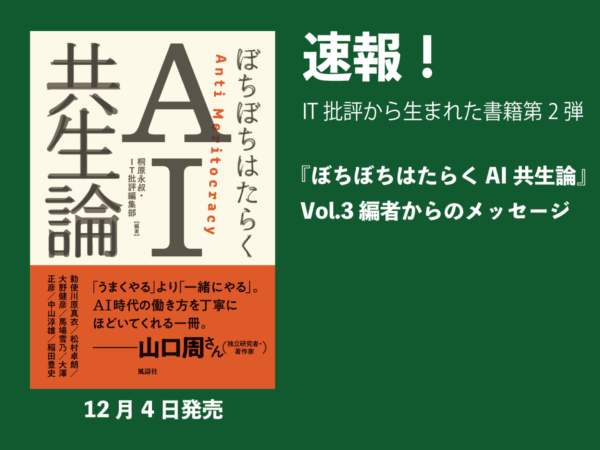サイケデリック/アシッド・サイエンス
第3回 ハルシネーションが科学を拓いた系譜

AIの“ハルシネーション=幻覚”がまだ見ぬタンパク質を設計する──最先端の研究成果について、科学ジャーナリズムは“ハルシネーション”という言葉に慎重な沈黙を守っている。科学史を遡ると、幻覚と科学とはもとより敵対的だったわけでなく、忘我や変性意識により科学的発見や医学の進歩をもたらした事例も多くあることがわかる。
目次
科学界でタブー視される“ハルシネーション=幻覚”というワード
前回まで、デイヴィッド・ベイカー教授を称揚するトーンで論を進めてきた。しかし今回注目したいのは、むしろベイカー教授の功績をめぐるサイエンス界やメディアの反応である。
ベイカー教授を中心としたグループは、ベイカーの研究室やGoogle DeepMindが開発したRosettaFoldやAlphaFoldなどの構造予測技術で、AIモデルにタンパク質の折りたたみ構造を学習させ、そこから可能な構造空間を自由に探査することで、自然界には存在しないものの安定した構造を持つ新規タンパク質を生成した。このプロセスをベイカー・チームのメンバーは「新しいタンパク質をハルシネートさせる(Hallucinating New Proteins)」と呼んでいた。
ところがベイカー博士の業績が評価されノーベル化学賞を受賞した際のノーベル賞委員会の公式プレスリリースや関連資料をみると“ハルシネーション(hallucinations)”という用語はまったく使用されておらず“計算によるタンパク質設計(computational protein design)”や“想像力に富んだタンパク質の創造(imaginative protein creation)”と表現されている。他のメディアをみても“hallucinations”という言葉を用いた例は数えるほどしかない。筆者のみたところヘッドラインに用いられたのは3例で、そのうち一般誌ではFortune誌のみだった。同誌は“Scientist says the one thing everyone hates about AI is ultimately what helped him win a Nobel Prize.(だれもがAIを嫌う1つのことこそが、最終的には自分をノーベル賞受賞へと導いてくれた――と科学者は語った)という記事中で、ベイカー教授の「AIのハルシネーションは“ゼロからのタンパク質”を作るうえで中心的な役割を果たした(Baker said AI hallucinations were central to ‘making proteins from scratch,’ adding they helped his lab to design around 10 million ‘all brand-new’ proteins)」というコメントとともに「彼らはこの手法によって“すべてがまったく新しい”タンパク質を約1,000万個設計するのに役立ったと付け加えた」という言をひいている。その他は GovInfoSecurityの“Maybe AI Hallucinations Aren’t So Bad After All(結局のところ、AIのハルシネーションはそれほど悪いものではないのかもしれない)”という記事と、Warp Newsに掲載された“Nobel laureate transforms AI hallucinations into new proteins(ノーベル賞受賞者がAIの幻覚を新たなタンパク質に変換)”という記事のみである。附言するとGovInfoSecurityはアメリカ政府関連のサイバーセキュリティに特化した報道を行うサイトで、現下の国際紛争の水面下で行われるサイバー戦について多くの情報が記されていて興味深い。一方、Warp Newsはスウェーデン発のウェブメディアで、科学技術についての悲観論に抗する“Angry Optimist(怒れる楽観主義者)”という立場から、ファクトに基づきつつ楽観的な報道を行うことを標榜している。執筆に“WALL‑Y”というAIアシスタントを用いていることも明示されており、どこまで“ネタサイト”的なスタンスなのかは判別しがたい。
上述の例からわかるのは“ハルシネーション”というタームが、科学ジャーナリズムにおいてはネガティブに、そして半ば禁忌として扱われているということだ。
科学と幻覚との蜜月時代
そもそも、科学と幻覚とは、さほど緊張をはらんだ関係にあったわけではない。宗教が“真実の影”を表すものとされ、それを知るために科学が発展してきた時代には、人々は心身を極限まで追い込んだ忘我の境地でなにかを発見しようとした。
医学分野では、麻酔が医学を飛躍的に進化させただけでなく、現代医学を構築する根本条件の1つとなっていることはいうまでもない。それまでは患者が暴れたりショック死したりする事例が多発することから短時間ですむ処置しかできず、拷問に近いとみなされていた外科手術も、1846年にマサチューセッツ総合病院で歯科医師として治療経験のあったウィリアム・モートンと外科医ジョン・コリンズ・ウォーレンにより行われた“エーテル公開手術”以降は科学として成立することとなった。麻酔を使用することで手術の正確性と所要時間は飛躍的に向上し、今日の外科手術においても解剖学や感染制御とともに外科手術の成立要件として欠くことのできないものになっている。数年前から、ジェネリック製薬メーカーが製造手順の省略や品質試験データの操作を行っていたことがGMP(Good Manufacturing Practice:適正製造規範)監査により発覚し、製造・販売の業務停止命令を下される事例が頻発している。あらゆる医療分野で供給の逼迫や市場の混乱が発生したが、業務停止が下されたなかには重要医薬品である麻酔薬を扱っていたメーカーもあり、手術が中止となる深刻な事態を招くケースを引き起こしたことで、厚生労働省・都道府県薬務課・PMDA(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency:独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による定期・無通告立入検査が厳格化された。
モートンとウォーレンによるエーテルの初期手術実演の数か月後には、スコットランドの産科医ジェームズ・ヤング・シンプソンがエーテル吸入による初の無痛分娩を成功させている。当時のキリスト教圏では産痛を神罰であると捉えられており、無痛分娩は倫理にもとるとされていたものの、1853年にはヴィクトリア女王が第8子レオポルド王子の出産時にクロロホルムによる無痛分娩を行ったことで、産科における麻酔使用の社会的正当性が担保され、無痛分娩は標準医療であり、自然分娩の強要は女性の自己決定権の否定とされるようになる。このあたりは、少子化を憂いつつも、帝王切開や吸引分娩を除く自然分娩や無痛分娩を「健康な女性が経験する自然なプロセスであり病気ではない」と位置づけ、公的健康保険適用外の私的な営みとして自己責任・自己負担の原則下におく日本とは、大きく異なるところだ。