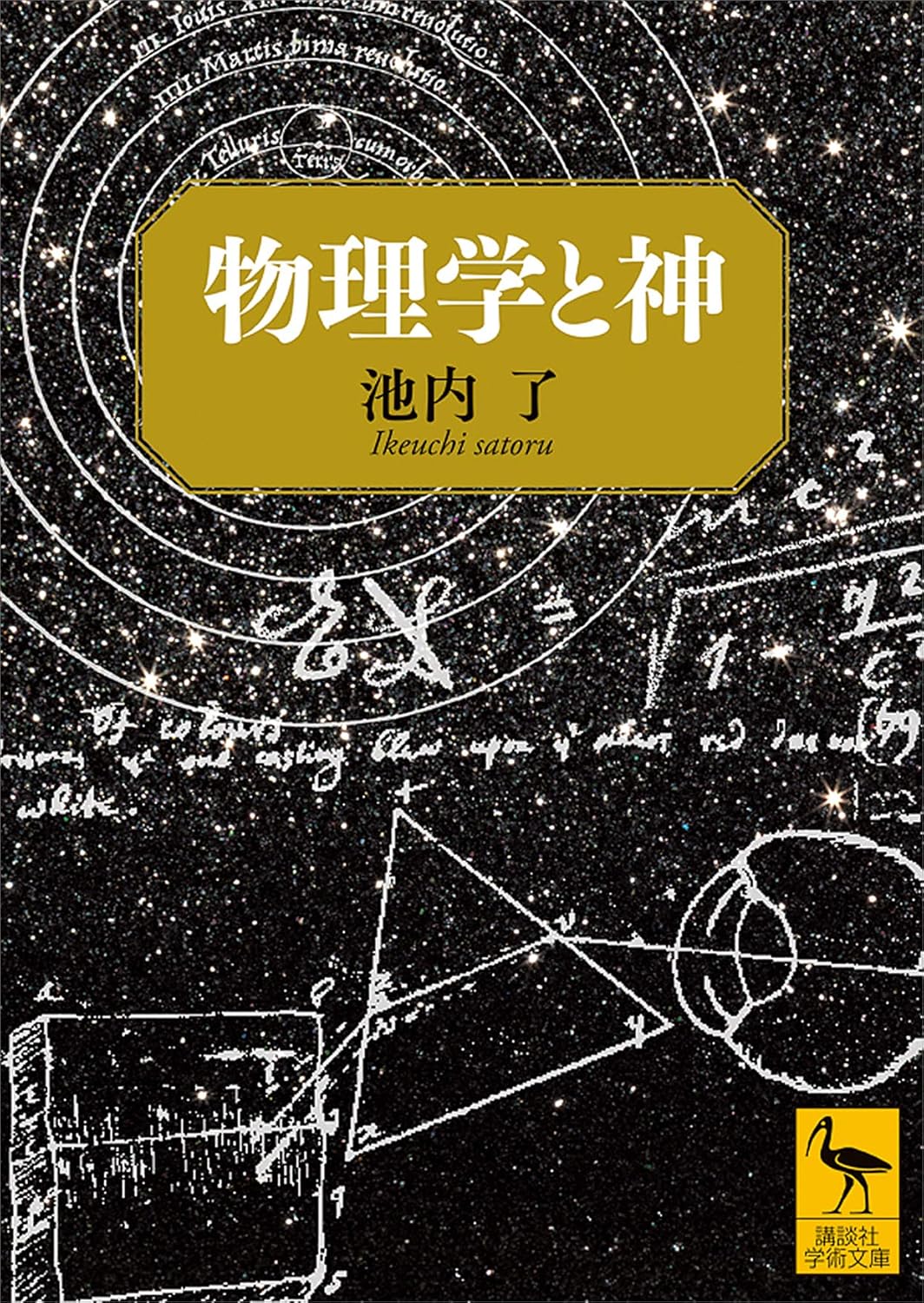神と悪魔と、人間と。
量子の世界は知的枠組みの何を変えうるのか?
ウェーバーと脱魔術化
ニーチェと同じ頃、近代の訪れを「脱魔術化」と称したのはマックス・ウェーバーだ。ウェーバー自身もニーチェに大きな影響を受けていたとされる。
「脱魔術化」という概念は、ウェーバーが大学生向けに行った講演をまとめた『職業としての学問』(尾高邦雄訳/岩波文庫)に登場する。学問は、欲しさえすればどんなことであろうと学び知ることができるとういう知性主義的合理化の方向へ進化していく。主知化と合理化を通じて、「魔法からの世界解放」つまり脱魔術化が行われるのだ。洪水が起きても大地の怒りを鎮めるために祈祷するのではなく、川の氾濫を予測し治水工事といった技術をもって解決していく。
注意したいのは、進歩が世界から神秘や魔術を奪っていく過程で、世界の意味が明らかになったのではないということだ。科学の進歩はむしろ神による説明以上に世界の意味そのものを消滅させてしまった。だからこそ、近代において人間が世界を意味づけし直していったのだ。この辺りは、フーコーにおける事物と言葉の間に人間が登場したという論点と似ている。
世界の意味づけを行うことが学問なのだ。そのうえで、登場する概念が「価値自由」である。ウェーバーは価値判断と事実判断を厳密に峻別せよという。社会科学においては事実判断が、個々人の価値に左右されてはならないという。それが価値からの自由、価値自由だ。しかし、フーコーの議論を思い出せば、この価値こそエピステーメーに支配されたものかもしれず、決して自由とは言い切れない。
ウェーバーが最も厳しく戒めたのは事実判断に個々人の価値が紛れ込んで、知らず知らずに不毛な正当化を行ったり利益誘導したりしてしまうことだ。
ウェーバーにおいては、事実は事実として客観的にあるべきだという科学的な姿勢が強調されるわけだ。
マックス・ヴェーバー (著)
尾高邦雄 (著)
岩波文庫
ラプラスの悪魔が示す神
しかし近代化以前は、ウェーバーが推奨するような科学的な姿勢は神の意志を揺るがす魔術としてあった。全能であるべき神の記述である「聖書」に逆らう科学的な事実は悪魔の所業であった。ガリレオ・ガリレイが地動説によって裁判にかけられたことを思い出すだけで十分だろう。科学者とは神を冒涜する悪魔であったわけだ。
近代の少し前、万有引力によって古典物理学を確立したのはアイザック・ニュートンである。ニュートンはリンゴの樹からリンゴの実が落ちるのと、地球が太陽のまわりを回るのに共通の法則を見つけた。世界は神の意志としての運命ではなく、ひとつの法則として運行されている。
すべては因果律でつながっているという古典物理学の考えをつきつめていけば、世界は誕生から終焉まであらゆる事物がすでに決定しているということになる。フランスの数学者、ピエール・ラプラスの決定論として有名な「ラプラスの悪魔」である。
「ラプラスの悪魔」について、天文学者で宇宙物理学者である池内了は『物理学と神』(講談社学術文庫)のなかで次のように解説する。
自然界のあらゆる力と物質の状態を完全に把握した知的存在が存在すれば「その知的存在にとっては、宇宙の中で何ひとつとして不確定なものはなく、未来を完璧な正確さで予見できる」と主張した。
科学はまさに神を世界から追放する悪魔である。しかし、ラプラスのいう「知的存在」とはどこか全知全能の神のようでもある。「自然界のあらゆる力と物質の状態を完全に把握した知的存在」こそが神たる存在ではないか。科学の全知識を総合しうる存在は、神のごとき超越的存在としてしか想像できない。科学を信奉したラプラスは、むしろ神に代わる新たな神(物理学)を設定しただけともいえる。
池内 了 (著)
講談社学術文庫
多世界解釈と人間存在
20世紀に入るとこの超越的な存在さえも許さない世界観が量子力学をもって登場する。前回も量子コンピューターをテーマにするなかで、量子力学について述べた。
量子力学の歴史においてアインシュタインとボーアの論争のように、普遍絶対の(神のごとき)法則を追い求める決定論と、すべては相対的で観測者の介在によって変化する確率論の間に対立があった。アインシュタインが「神はサイコロを振らない」といったのは、そのまま神の存在を前提としたものと考えるのはナイーブすぎるが、少なくとも神のような絶対性、決定性を前提としていることに間違いはない。アインシュタインは、量子力学の非局所性を強く拒否したことも有名だ。“いまここ”にないものが絡み合う非局所性とはテレポーテーションのような現象で、古典物理学の延長ではとうてい受け入れ難い。
ボーアとエイゼンシュタインは極小の世界で量子は重ね合わせの状態にあるという。シュレーディンガーの猫でいえば、猫の生と死は重ねあったままある。それが、観測者が登場することで、重ね合わせの状態は収縮しどちらかに定まる。シュレーディンガーの猫の生死は確率的に定まる。これが「コペンハーゲン解釈」といわれるものだ。
量子力学には別の解釈もある。それが「多世界解釈」である。ヒュー・エヴェレットⅢ世が提唱したものだ。エヴェレットの定式では世界は収縮するのではなく分岐するという。シュレーディンガーの猫ならば、観測によって猫が死んだ世界と猫が生きている世界に分岐するのだ。にわかには信じられないSF的な解釈であるが、現在ではコペンハーゲン解釈よりも多世界解釈を支持する物理学者のほうが多い。量子コンピューターの発明も、この多世界解釈に依拠している。イギリスの物理学者、デイヴィッド・ドイッチュは多世界解釈の支持者であり、それをもとに量子コンピューターを理論的に定式化したのだ。多世界解釈がなければ、量子コンピューターも生まれてはいなかっただろう。
ボーアのコペンハーゲン解釈は、天才フォン・ノイマンの証明によって不可侵なものとなっていた。北アイルランド出身のジョン・スチュワート・ベルがノイマンの証明に疑いをもったことにはじまって、コペンハーゲン解釈の牙城はさほど強固ではなくなっていく。そこから多世界解釈が生まれた。
この一連の変遷を追ったのが、アダム・ベッカーが著した『実在とは何か ——量子力学に残された究極の問い』(吉田三知世訳/筑摩書房)である。ボーアに対してかなり批判的であり、むしろアインシュタインに同情的なこの書籍はこれまで紹介してきた量子力学関連の書籍では異質なほうだが、むしろ物理学の世界ではこちらのほうが大勢になりつつあることがわかる内容だ。
そして、この多世界解釈こそついに神を世界から追放すると同時に、人間というエピステーメーに終焉をもたらすものにも思える。いや、かえって観測者、解釈者としての人間の存在をさらに強調するようにも思える。
多世界解釈をもとに量子力学をつきつめていけば、実在というものの手応えはますます失われていく。実在が無とすれば、人間もすでに無である。人間(ヒューマン)の死はこのようにやってくるのだろう。
そういえば、かつて小説家の小林恭二は『ゼウスガーデン衰亡史』(ハルキ文庫)で未来の世界を「ノーアイデンティティ」とした。アイデンティティなき世とは、そのまま「人間」なき世なのかもしれない。
アダム・ベッカー (著)
吉田 三知世 (翻訳)
筑摩書房
小林 恭二 (著)
角川春樹事務所