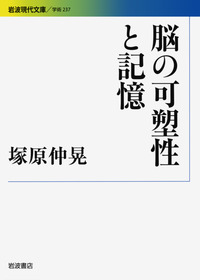脳の可塑性と自然の可塑性、または落語に救われた話

「尾籠(びろう)な話」という。もともとは、愚かで分別がないという意味の「痴(おこ)」という言葉に当て字してできた。なにが尾籠かといえば、排泄や排泄物と決まっているが、そのくせそういう話題の最初には、こんな洒落た言葉を使うというわけだ。
目次
脳の機能はつくり直せる
長い入院をしていたことがある。2018年8月から11月にかけてだから、もう4年半も前だ。どうしてそうなったかといえば、近所の銭湯で脳梗塞に襲われて昏倒したからだ。では、なぜ脳梗塞なんかになったかといえば、経営していた会社はうまくいかないし、1歳上の姉が自分の家族を残して自決しやがるしで、心労が祟って血圧が爆上がりして首筋あたりの血管の内側が剥離して詰まったのだ。脂肪や糖が原因の、いわゆる生活習慣病ではなくストレス由来だったのは、退院後の検査で詰まっていた血管がちゃんと再建していたのでわかった。
とはいえ、後遺症が残った。未だ首から下の左半身、顔の右側は温冷覚、痛覚が鈍い。もっともやっかいなのは、バランスを司る脳細胞が壊れてしまったことだ。そのせいで、いつも車酔い、船酔いのような状態だ。しかし脳というのは不思議な器官で、失われた機能を他の部位が代替したりする。これを「脳の可塑性」といったりするが、可塑性とはつまりつくり直せるという意味だ。粘土のような柔軟性があると考えてもいい。
脳の可塑性については、短命の天才医学者・塚原仲晃が書いた『脳の可塑性と記憶』 (岩波現代文庫)に当たりたい。古典といえるほどの名著だ。当時、脳神経学の研究で世界をリードしていた塚原は、学習や記憶が脳のシナプスの変化に表れることをつきとめ、脳が計り知れないほど驚異的な器官であることを一般に知らしめた。当然、現在の知能研究、AI研究の礎になっているのはいうまでもない。
急性期の病院に担ぎ込まれた最初の1週間は絶対安静を言い渡された。絶対安静だから、ベッドから起きあがることも許されない。食事は点滴だし、排泄は……とここが問題だ。いや、問題だった。看護師から差し出されたのは、お茶や水を注ぐには口が広すぎ、花を刺すには口が傾きすぎる容器だ。ボール紙でできていた。ははん、どうやら使い捨てらしい。
「桐原さん、用を足したくなったらナースコールしてください」
そう言われた。ナースコールでやってきた看護師は私にボール紙製の使い捨ての“尿瓶”を渡すと、しゃーっとカーテンを閉め、私やルームメイトのいる6人部屋から出て行く。私はふっと息を吐いて、尿瓶の口を急所に当てがい、なんとか力を抜いて排尿しようと試みる。私を困らせたのは、それからだ。いかな努力しても一向に排尿できない。尿意はあるのに既(すんで)のところでひっこんでしまう。
さてはて往生した。まったくなんともならない──。
猪牙で小便千両
「猪牙(ちょき)で小便千両」という。これは、「猪牙で小便千両も捨てたやつ」という都々逸からきている。
江戸の昔、主要な交通機関といえば渡し船だった。「東洋のヴェニス」といわれたのもさもありなんというわけだが、じつは「××のヴェニス」といわれるところは世界中にごまんとある。日本国内にさえ数ヵ所あるので、言葉なんてものはずいぶんといい加減に流布することが知れる。
江戸の渡し船といえば、猪牙船である。舳先がちょうど猪の牙のように上を向いて尖っていえる小型船を指す。これを船頭が竹棹と櫓で操る。不安定なうえに人目もある猪牙船のうえで排尿するのは難しい。普通の人間なら、まず苦労するはずだ。ちょうど、ベッドのうえでボール紙製の使い捨てをあそこへ押し当てている私と同じように。
猪牙船が別名「山谷船」といわれたのは山谷にある吉原遊廓に通うのに使われたからだ。千両の意味もここでわかる。千両つかいきるほど遊び倒し、つまり猪牙船に飽きるほど乗って、やっと不安定な猪牙船のうえでも悠々と排尿ができるというわけだ。
都々逸のほうは悠々と猪牙船で排尿する客を指して「ずいぶんお大尽をしたろうね」という皮肉が効いている。
4年半前、ベッドのうえで私は「猪牙で小便千両」の言葉を思い出していた。猪牙船ならまだしも向こう岸に着くまで我慢するって法もあるが、こちとら出なきゃ出るまで間抜けなツラを晒してなきゃならない。まったくもって往生だ。だいたいが、こんなボール紙製の使い捨てを放り渡して「小便としけ」とは看護師の野郎、ふてぇ野郎だなどと江戸弁を頭ん中で呟いていたら、そのうちに腰の前あたりが温かくなって、無事に初めての尿瓶はなんとかなった。心配性の私はしかし、看護師にちょっと重くなったそれを返した後、こいつは次からが思いやられるぞと気を重くしたのだった。
「猪牙で小便千両」を知ったのは落語のマクラだ。今回、誰のなんという噺だったか思い出そうと、DVDやらCDを探してみた。マクラといや、先年亡くなった柳家小三治。渡し船といえば「船徳」かというわけで聴いたが、そこにはない。こうなると気になるので、渡し船の出る噺をあたってみる。「岸柳島」。いや、こっちのマクラは「さあ事だ、馬のしょんべん渡し船」だな。これは渡し船に乗り合わせた馬が小便を垂れて往生するという都々逸で、まったく獣ってやつはときところを選ばないから羨ましい……いや、情けない。
小三治やじゃくて古今亭志ん朝だったかな。というわけで、志ん朝のCDをだして「夢金」なんて聴いてみる。あれ、違う。寒い冬に船のうえで尿意ってわけかと思ったが、そうではない。ここまでくると噺を聴くのが楽しくなってしまうから、初期の目的を忘れて聴きあさる。なんてしているうちに志ん朝の「船徳」を小三治と聴き比べておこうなんてCDをプレーヤーのトレイに載せる。そうしたらなんと、マクラで「猪牙で小便千両」という。見事に発見した! あとで思い出したが、今をときめく春風亭一之輔の「船徳」のマクラでもこれを言っていた。どこかの落語会で聴いている。
古今亭志ん朝の「船徳」は『落語名人会 (1) 古今亭志ん朝(1)』(ソニー・ミュージックレコーズ)などに収められている。
トイレと想像力と文豪
さあ、困ったぞ。またまた尿意がやってきた。明け方の排尿はなんとか江戸前の力で乗り切ったが、今度はどうしたもんだ?
そこで私は考えた。「しょうべんしよう、しよう」と力むからかえってよくない。床でやっちゃうやつは寝小便だったりするのだ。たいていは、眺望のいい丘のうえかなんかに立ってズボンのジッパーを下ろしてなんて夢見して、明くる朝には布団が冷たくなってる。
これだ。私は閃いた。ボール紙製の使い捨てをあそこへ押し当て、夢を見ればいいのだ。眺望のいい丘なんかよりは、ちゃんとトイレに入る夢を見よう、と。とはいえ、もちろん寝てしまっては心許ない。尿瓶の口が外れたら事だ。渡し船の馬の小便ではかなわない。
そこで私は私が生まれた家の古いトイレを思い出していた。それはトイレというより便所、厠、雪隠というべきところで、私が生まれたのは禅寺だから「東司(とうす)」と呼ばれていたそこを母屋からの渡り廊下、建て付けの悪い引き戸、柱の一輪挿しの南天なんかを夢見のように頭のなかに再現していった。ところが、である。いざ想像の男性便器の前に立ったところで尿意は引っ込んでしまった。ああ、惜しい。
古い厠を想像していると、私はふと谷崎潤一郎に「厠のいろいろ」というエッセーがあったことを思い出した。たしか奈良かどこかのうどん屋の厠が川のうえにあって、便器を跨いで下を覗くと遥か下方に河原が見えたという冒頭だ。排泄物が虚空を舞うなんて、文豪は書く。たしか便所にまつわる古今東西の話、都鄙(とひ)の違いといったことを悠長な文体で述べていくのだ。こんなエッセーがかの名高い「陰翳礼讃」のあとに入っているのだ。続けて読むと、昼間でも薄暗い日本間を抜け出して、虚空に輝く便器に向かうような趣がある。そのときの私もベッドのうえでそんなことを連想した。そうして、また腰の前あたりが温くなり──。今度も、なんとか首尾よく済んだ。
谷崎潤一郎のこれはいろいろに収録されているが、新潮文庫の『陰翳礼讃・文章読本』が昔から変わらぬ装丁で良い。
制度化された知覚はAIに意識をもたらすか
この時から1週間、私は尿意を覚えるたびに、精密に繊細に生まれた家の厠を脳の裡に再現することで難敵を切り抜けた。まあ、実際のところ、数回で慣れてしまって、どんとこいというような心持ちになり、そうなると意にも介さなくなり、看護師がカーテンを閉め終わらぬうちに出てくるという上達ぶりであった。「すぐ返すから、看護師さん、そこで待ってて」ってなもんである。ひどい話だ。
脳内に再現される古い記憶への没入。そのコツは触覚や嗅覚、聴覚といった視覚以外の知覚に訴えるディティールを思い出すことにある。「プルースト効果」なんていう特定の匂いが記憶を蘇らせる作用を指す用語もある。これは、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』全13巻(鈴木道彦訳/集英社文庫ヘリテージ)という長い物語の導入で、主人公がマドレーヌを紅茶に浸した香りで幼少時代を思い出す部分に由来している。(ついに禁を破った。読んでない本は紹介しないという禁だ。さすがにこれは読んじゃいない)
「神々は細部に宿る」という。
私たちの生活世界における記憶や感情を刺激するのは、意識に上らない程度の細部なのだ。かつて世界的映画監督の黒澤明が『赤ひげ』(東宝)を撮影した際、舞台となる小石川養生所のセットには、撮影では決して映ることのない棚の内部にまで時代考証に適った薬瓶が詰まっていたという。こうしたディティールが俳優の知覚を刺激して、演技にリアリティをもたらすと言われた。
もちろん、自然科学的な知覚でいえばそんなことはありえない事象だ。少なくとも数学の言葉で語れる事象ではない。唯物的にはまったくそうだ。
現象学をうちたてたエトムント・フッサールは次のように指摘したと、科学哲学の第一人者である野家啓一は『科学の解釈学』(講談社学芸文庫)に書いている。
「理念の衣、数学的シンボルの衣による生活世界の隠蔽」という事態
近代化とはつまり西ヨーロッパでうちたてられた科学革命による知覚、認識の〈制度化〉のことである。私たちは自然を発見するのではなく、新しい制度の型でくり抜いて自然を“発明”しているのだ。そういう点では自然は可塑的であると野家はいう。自然は客観的絶対にして存在するのではなく、観察する私たちの〈制度化〉された知覚、認識を通じて“つくり直される”からだ。
フロイトがつくりだした精神医学によって私たちは心理という認識を得た。今では中学生でさえ心理を語る。知覚、認識の〈制度化〉とは、ただ気持ちとしてとらえていた動きを心理として説明しうるものにする。不調ともなれば薬を処方してその改変を試みることさえする。フロイトが人間のうちに心理を発見ではなく、“発明”しなければ現代人にこういう認識はない。
であるなら、フッサールが求めたように生活世界における主観的な経験(知覚、認識、直感など)と、科学者たちが共有するパラダイムという枠組みでの理論を分離しなけなければならない。それは客観的な事実などでなく間主観的な事象にすぎないからだ。
一見、宗教的で神秘的な黒澤の手法がどこまで真実であるかは問えないが、一方で芸術を数学の言葉で語ることは意味をなさない。客観的な事実、真実というのはただの制度だからだ。私たちの生活世界における知覚や感情は未だ数学化されていない。それともいずれは脳内の活動として分泌液の量などで測ることが可能になるのだろうか?
ディティールが豊富なビッグデータなら、AIに生活世界における主観的な経験をもたらすことができるだろうか。すなわち心や自己意識をつくりだすことはできるだろうか。
言葉なんてものはずいぶんといい加減に流布する?
「神々は細部に宿る」という言葉もその出自において謎めいている。これだけ人口に膾炙していながら、誰の言葉かいまひとつはっきりしていないのだ。建築家でもありバウハウスの校長でもあったミース・ファン・デル・ローエの言葉として「ニューヨークタイムス」の追悼記事に見つかるという話もあるし、フローベル、アインシュタイン、ル・コルビジェ、ニーチェといった錚々たる面々が口にしたという記述もネットにある。
ローエやル・コルビジェのものであるなら建築のような大きな構造物であってもその本質的な意味はたとえば壁紙の素材といった細部にこそこめられていると言いそうだし、フローベルであれば文芸作品のもっとも真なる部分はたった一語にあるかもしれぬと述べそうだし、ニーチェなら無限の絶対者である神の死後、人々の卑近で些細な感情にこそ真理があるのだとも言っているようだし、アインシュタインであればそれこそミクロの世界である量子の動きを「神はサイコロはふらない」と否定しながらも非常に微細なディティールである量子そのものこそが物理世界の普遍性の源と考えたのかもしれない。いずれにしろ、含蓄のある言葉で脳梗塞患者がベッドのうえで排尿する際にさえ思い出してしまうほどだ。この言葉の解釈は自由だ。一説には語源を神秘主義者のエックハルトまで遡れるようだから、近代以前の生活世界にも通じるのかもしれない。
生活世界における主観的な経験とは歴史に応じて変化するものなのは先のフロイトの例をみても明らかだろう。日本人は明治維新後、西洋に倣って自然科学による制度化を進めることで近代化しようとした。ゆえに日本人は改めて“日本を発明”しなおしたのだ。現代の日本人には江戸期の日本人の生活世界を想像できない。江戸末期に成立した落語であっても、その登場人物の生活世界における経験や感情は私たちと隔絶している。
「伝統を現代に」をスローガンとした立川談志の落語には近代の制度化された知覚や経験が取り込まれていると感じる。フロイトの発明した心理が、江戸の長屋の庶民の裡に構築されているのだ。だから談志はしばしば「狂気」と言ったりする。狂気はフーコーの言う通り、近代化に寄り添う概念だ。近代化された知覚体験が落語に現代でも通じるリアリティを生み出した。立川談志が天才と言われる由縁だろう。
江戸の長屋の庶民の生活世界とはいかようなものであったろうか。つい先ごろ、亡くなった渡辺京二の『逝きし世の面影』(平凡社ライブラリー)では、現代の私たちとはまったく隔絶されてしまった往時の日本人の生活世界を垣間見ることができる。訪日外国人の目を通してみるからこそ、そこには日常の些細な細部がていねいに描写される。その細部によって私たちは往時の日本人の生活世界の手触りをもってしることができるのだ。
訪日外国人が苦労したのは、やはり日本の厠であったろうという想像も容易にできる。
いやいや、最後も尾籠なところへ落ち着けた。
追伸 後遺症で目眩に悩まされている私は「こんなぐるぐる回る家はいらねぇ」と落語「親子酒」のサゲを呟いて我が身を慰める。
おあとがよろしいようで。