量子コンピューターを理解するための 量子力学入門
第2回 量子力学とは何か?
──量子コンピューターは「ミクロな世界を忠実にシミュレーションしうる計算機」
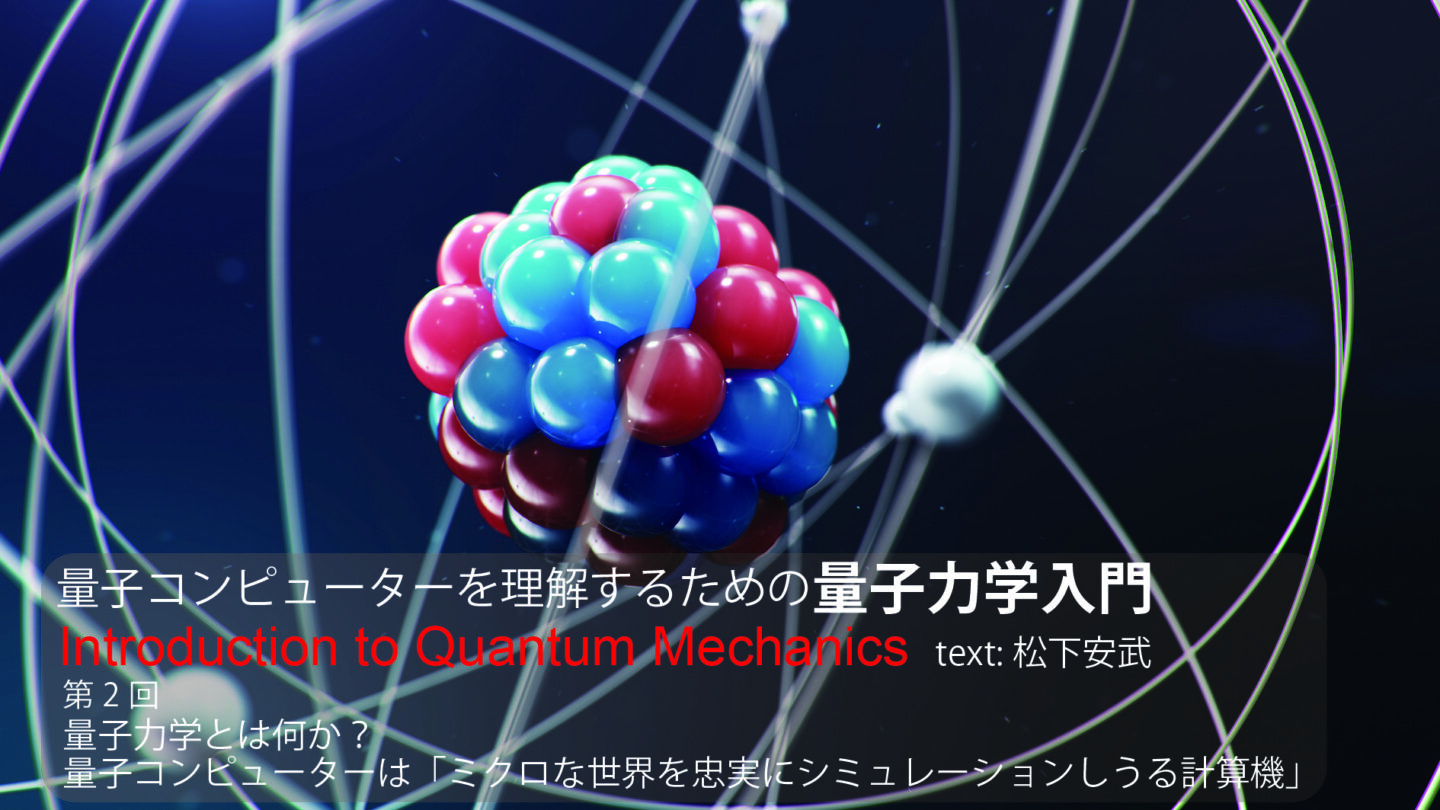
前回は、今や次世代テクノロジーの代名詞とも言えるような存在となった量子コンピューターを巡る4つの誤解を取り上げた。そのなかで強調したのは、量子コンピューターについて理解するためには、その基礎となっている「量子力学」についての理解が不可欠だということだ。今回はそもそも量子力学とはどんな理論なのかについて解説していくことで、なぜ量子コンピューターが社会に革命を起こしうる存在として注目されているのかについて迫っていく。
執筆者プロフィール
松下 安武(まつした やすたけ)
科学ライター・編集者。大学では応用物理学を専攻。20年以上にわたり、科学全般について取材してきた。特に興味のある分野は物理学、宇宙、生命の起源、意識など。
目次
━量子コンピューターが実現すれば、高効率な太陽電池や、画期的な抗がん剤が開発できるかもしれない
━分子の世界をシミュレーションするには、量子コンピューターが最適
量子力学で最も重要な概念「重ね合わせ状態」とは
量子コンピューターが実現すれば、高効率な太陽電池や、画期的な抗がん剤が開発できるかもしれない
将来、量子コンピューターの活躍が期待されている分野に、新素材や薬剤の開発がある。太陽光を効率良く電気エネルギーに変換できる素材や、がん細胞の表面に存在する特定の分子を狙い撃ちする薬剤(分子標的薬)などを分子レベルで設計するシミュレーションに、量子コンピューターが活用できるかもしれないのだ。
量子力学に支配されている現象(原子レベルのミクロな世界の現象)のシミュレーションを行うには、現代で言うところの量子コンピューターが必要だということを初めて指摘したのは、アメリカの物理学者リチャード・ファインマン(1918〜1988)[1]で、1981年のことだという。これはイギリスの物理学者デイヴィッド・ドイッチュ(1953〜)が量子コンピューターの基礎となる理論を発表した1985年の4年前に当たる。そのためファインマンは、量子コンピューターの概念の最初の提唱者だとも言われている。
[1]ファインマンは非常に著名な物理学者であり、量子電磁力学(QED)の発展に寄与した功績で1965年にノーベル物理学賞を受賞している。また、『ご冗談でしょう、ファインマンさん』(岩波現代文庫)などのエッセイ、大学生向けの物理学の入門書『ファインマン物理学』(岩波書店)のシリーズの著者としても知られる。
なぜこのようなことが、量子コンピューターによって可能になると考えられているのだろうか? このことを理解するには、量子コンピューターの基礎となっている「量子力学」が、そもそもどのような理論なのかを理解する必要がある。
量子力学とは、ミクロな世界を支配している法則についての物理学の理論である。ここでいうミクロな世界とは、おおざっぱに言って原子や分子より小さなスケールの世界だと考えてほしい。原子の大きさは種類にもよるが、10-10メートル(1オングストローム)程度である。10-10メートルと言われてもピンと来ないかもしれないが、1メートルの100億分の1、1ミリメートルの1000万分の1であり、普通の顕微鏡(光学顕微鏡)では決して見ることのできない、極めて小さな世界である。
一つのミクロな粒子は、複数の場所に同時存在できる
原子サイズのミクロな世界では、眼に見えるようなマクロな世界での常識が通じない。例えば、電子のようなミクロな粒子は、一つの粒子にもかかわらず、複数の場所に同時に存在することができる。領域Aに20%、領域Bに30%、領域Cに50%の確率で同時に存在する、といった具合だ。どこで電子が発見されるかは観測前には分からず、量子力学で予測できるのはその発見確率だけだ。
ここで注意したいのは、「観測前には分からない」とは、「電子の位置は観測前から確定しているが、観測者が電子の位置を観測前に知らないだけ」という意味ではない 、ということだ。「観測前に電子の位置は確定しておらず、観測によって電子の位置が初めて確定する」というのが、量子力学の標準的な解釈である。初めて量子力学の考え方に触れた人からすると、何を言っているのか分からないかもしれない。心配しなくてもいい。それは正常な反応だ。順を追って説明していこう。
ミクロな粒子は「観測」によって大きな影響を受ける
まずミクロな世界では「観測」という行為自体が、観測対象に大きな影響を及ぼしてしまうということがある。真っ暗な部屋の中で鍵を探すことを考えよう。鍵を探す(鍵の位置を観測する)には、部屋の照明をつけて鍵に光を当てる必要がある。マクロな物質である鍵は、光を当てたところでその場所から動かない。しかし、電子のようなミクロな粒子の場合、どこにあるかを知ろうとして(位置を観測しようとして)光を当てると、光が当たった衝撃でどこかに飛んで行ってしまう。そのため、観測前に電子がどこにあって、どのように運動していたかを正確に知ることは、原理的に不可能なのだ[2]。
[2]位置の不確定さ(Δx)を小さくするほど、運動量(質量×速度:運動の勢いに相当する量)の不確定さ(Δp)が大きくなり、運動量の不確定さを小さくするほど、位置の不確定さが大きくなる。このような関係が有名な「不確定性関係」(不確定性原理とも呼ぶ)である。
光を当てると電子が弾け飛ぶ、と聞いて驚く人もいるかもしれない。身のまわりには、光が当たることで動く物体などないのだから無理もない。太陽の光を浴びると、体が温かく感じることを思い出して欲しい。これは光が当たることで、皮膚を構成している分子が揺り動かされていることを意味する。物体の温度が高い(温かい)というのは、ミクロな視点から見ると、原子や分子の運動が激しい、ということである。光はミクロな粒子(電子、原子、分子など)を動かす能力(運動量やエネルギー)をもっていて、その結果、太陽光が皮膚に当たると、私たちは温かいと感じるのである。
以上の話から分かるように、電子のようなミクロな粒子は「観測」という行為自体によって大きな影響を受けてしまい、位置が”ぼやけて”しまうのである。これだけでも驚くべきことだが、実はそれだけではない。量子力学によると、観測する前からミクロな粒子の位置は”揺らいで”おり、本質的に観測前には位置が確定していないのである。一つの電子は、複数の場所(位置)に、ある意味で同時に存在している、とみなすことができるのである。
ミクロな粒子は、位置だけではなく、速度[3]や自転の方向[4]など様々な状態が観測前には確定しておらず、複数の状態を同時に取ることができる。右に進んでいる状態と左に進んでいる状態を同時に取ったり、時計まわりに自転している状態と反時計まわりに自転している状態を同時に取ったりすることができるのだ。このような複数の状態を同時に取っていることを量子力学では「重ね合わせ状態」と呼んでいる。前回解説したように、量子コンピューターでは、情報の最小単位である量子ビットを重ね合わせ状態にすることで、超高速な計算を実現している(図1)。
[3]正確には「質量×速度」で表される運動量。
[4]正確には「スピン」と呼ばれる、電子の磁気的な性質に関わる量。

観測前の複数の状態は実際に”存在”している
では、なぜ観測前の電子の状態が確定していないと言えるのか? ごく簡単に説明すると、「観測前の複数の状態が互いに影響を及ぼしあい、その後の電子の状態が変化することが実験的に確かめられているから」だと言える。つまり、観測前に複数の状態が実際に”存在”していると考えないと、説明できない実験結果がたくさんあるのだ[5]。
[5]ここでは分かりやすさを重視して、あえて「実際に存在している」という言葉を使ったが、何を「実在」とみなすかは研究者によって解釈が分かれる。
電子を、不思議な忍術を使う忍者にたとえて考えてみよう。忍者は、他の人からは見えない透明な状態になれるとする。ただし、攻撃(物理学実験の「観測」に相当)を受けると、忍者は透明な状態が解除されて、その姿を現わす。
陣地に侵入してきたこの忍者に対し、敵側は多数の手裏剣をランダムな方向に投げて迎え撃った。すると、忍者に手裏剣が当たり、姿を現したが、その出現場所が奇妙だった。とても一人では登ることができないはずの高い壁の上で姿を現したのだ。
この忍者を捕らえた軍師は以下のように解釈した。忍者は分身の術を使って、2つの透明な分身に分かれた(分身Aと分身Bの重ね合わせ状態)。そして分身Aは分身Bを踏み台として、壁の上に飛び移った。こう考えれば、忍者の出現場所を合理的に説明できる。つまり、忍者は攻撃(観測)前には2つの分身をもち、それぞれの分身は互いに触れ合うこと(影響を及ぼしあうこと)ができる。しかし攻撃を受けると、一方の分身だけが姿を現し、他方の分身は消えてしまった、というわけだ。
なんとも奇妙な話だが、電子のようなミクロな粒子は、このたとえ話の忍者のような振る舞いをすることが実験で確かめられているのである。実際にどのような物理学実験が忍者のたとえ話に対応するかは、本連載の別の回で詳しく解説する予定だ[6]。
[6]答えを簡単に述べておくと、忍者のたとえ話は、電子や光子(光を構成する素粒子)の「二重スリット実験」の比喩となっている。
量子力学は、ミクロな粒子がこのような「重ね合わせ状態」を取りうることを基礎として構築されている。重ね合わせ状態を取ったミクロな粒子がどのように運動するかなどを、計算によって明らかにするのが、量子力学なのである。
すべての現代科学は量子力学に通ず
周期表に登場する元素の性質は、量子力学によって解明された
量子力学は、現代物理学の基礎となっている理論であり、現代物理学において最も重要な理論だと言っても過言ではない。量子力学は20世紀初頭に多数の物理学者たちによって構築されていった理論体系であり、量子力学に基づいていない物理学の理論は一般に「古典物理学(classical physics)」と呼ばれる。高校で習う力学(ニュートン力学)や電磁気学などは古典物理学だ。「時間と空間は伸び縮みしうる」という驚くべき事実を明らかにした有名な相対性理論(特殊相対性理論と一般相対性理論)も、古典物理学に分類される。
物理学とは、文字通り「物の理(ことわり)についての学問」であり、あらゆる科学の基礎となっている学問だ。化学、材料科学、生命科学、医学なども、根本原理まで突き詰めて考えると、物理学に行き着く。量子力学はその物理学の土台なのだから、あらゆる現代科学の一番根っこの部分にあたる理論だといっても言い過ぎではないだろう。
例えば、化学の周期表を思い出して欲しい。高校時代に「水兵リーベ僕の船……」と語呂合わせで暗記したアレだ(水素・H、ヘリウム・He、リチウム・Li、ベリリウム・Be、ホウ素・B、炭素・C、窒素・N、酸素・O、フッ素・F、ネオン・Ne……)。これらの元素の性質は主に「原子を構成している電子の数(最外殻の電子の数)で決まっている」と習ったはずだ[7]。実は、原子の中で電子がどのような軌道を取り、原子がどのような化学的な性質をもつか(どのような原子と結びつきやすいかなど)は、量子力学によって解明された。つまり現代化学は、量子力学を土台として構築されているのである。量子力学に基づいた化学は「量子化学」と呼ばれ、化学工業や製薬などの産業を支えている。
[7]原子は、中心にプラスの電気を帯びた原子核があり、その周囲にマイナスの電気を帯びた電子が分布している。原子には様々な種類があり、同じ原子の集合が「元素」である。原子を積み木で例えると、同じ形の積み木の集合が元素だと言える。
分子の世界をシミュレーションするには、量子コンピューターが最適
2018年にノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑氏らが開発した免疫チェックポイント阻害薬は、免疫細胞の表面に存在するPD-1という分子に結合することで、その効果を発揮する。免疫チェックポイント阻害薬の分子がPD-1に結合すると、免疫細胞の活動の”スイッチ”がオンになり、がん細胞を攻撃するようになるのだ(図2・3)。この事例からもわかるように、生命は複雑な”分子機械”だと言える。つまり生命現象を解き明かすには、様々な生体分子の性質について知る必要があるわけだ。そして生体分子の性質の真の理解には、量子力学が必要になってくる。


現代の新素材開発や薬剤開発の現場では、コンピューターシミュレーションが利用されることがある。さまざまな分子どうしが、どのように力を及ぼし合うかをコンピューター上で計算し、再現することによって、目的の性能をもつ分子を設計してやるのだ。しかし従来のコンピューターシミュレーションでは、量子力学を考慮しない計算、もしくは量子力学的な効果を組み入れるにしても小規模な計算か、粗い近似的な計算しかできない(ただし、そのような近似計算で有用な結果が得られるケースも当然ある)。
例えば、100個の原子からなる分子を考えよう。それぞれの原子はAとB、二つの状態を取れるとする。その場合、一つの分子が取りうる状態の総数は、2×2×2×2×2…と、2を100回掛け合わせた数、つまり2の100乗になる。2の100乗は約1.3×1030乗であり、1兆3000億の1兆倍の100万倍に当たる。このように分子を構成する原子の数が増えれば、分子の取りうる状態の総数は指数関数的に増加する。その結果、分子の振る舞いを計算するために要する時間も指数関数的に増加してしまい、従来のコンピューターでは手に負えなくなってしまうのだ。
しかし量子コンピューターであれば、100個の量子ビットを用意してやれば、この分子が取りうる状態を、量子ビットの重ね合わせ状態を使って一度に表すことができる。つまり自然界の仕組みをそのまま再現しながら計算が行えるので、非常に効率が良いわけだ。
この世界のあらゆる現象は、ミクロな視点から見れば、量子力学の法則に支配されているのだから、そのシミュレーションに量子コンピューターが向いているというのは、ある意味で当然のことだと言えるだろう。その意味では、新素材や新薬の開発以外にも、量子コンピューターはミクロな世界のさまざまなシミュレーションに使える可能性があると言える。量子コンピューターが、革命的なテクノロジーになる可能性を秘めているとされる根拠の一つはこの点にあるのだ。
前回も紹介したように、現在は「量子誤り訂正ができない小規模な量子コンピューター(NISQ)」を使って何ができるかがいろいろと探られている段階だ。そのなかでNISQと従来のコンピューターを組み合わせることで、量子化学計算を行う方法が活発に研究されている。量子誤り訂正が可能な大規模な量子コンピューターの実用化はおそらく20〜30年程度は先になるだろうが、NISQと従来のコンピューターを組み合わせた小規模な量子化学計算であれば、もっと早く産業に役立つ成果が出てくるかもしれない。





