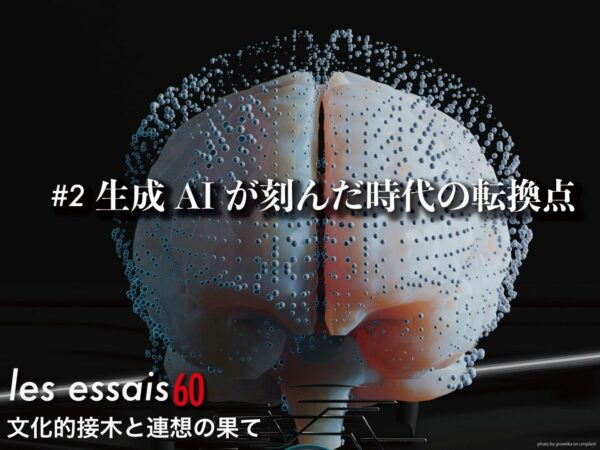情報の非対称性と終末論のなかで社会的ケアを模索する
第2回 スノーデン文書が暴露した超監視体制
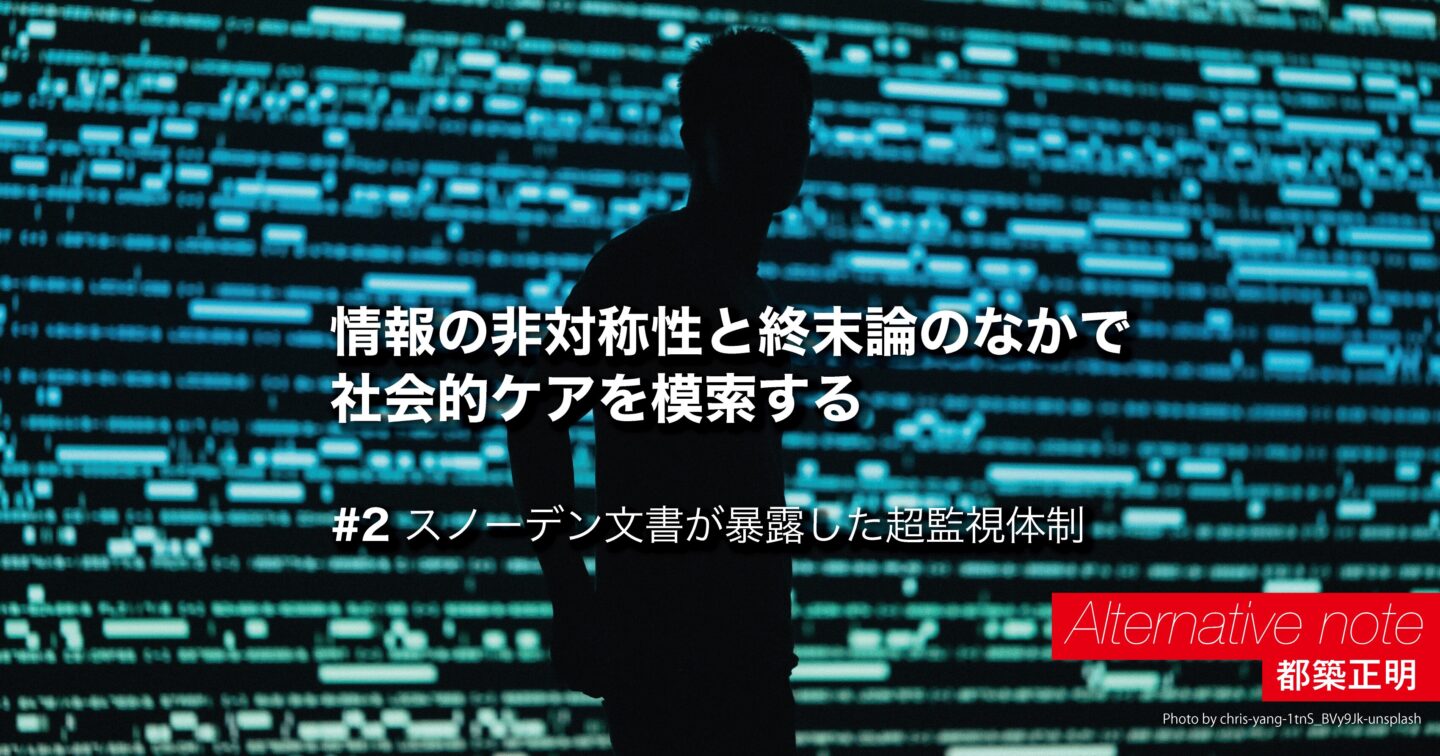
国家と軍、そしてビッグテックが水面下で結びつき、私たちの日常的な通信が密かに吸い上げられていた――スノーデンの告発は、その事実を白日のもとにさらした。暗号化やプライバシーという前提が裏切られるなか、監視と民主主義の境界線がいかに崩れ去ったのかを考える。
目次
“愛国”が位相を変えるとき
2013年には、元CIA(Central Intelligence Agency:中央情報局)職員でNSA(National Security Agency:国家安全保障局)契約職員でもあったエドワード・スノーデンが、アメリカNSAによる大規模監視体制を暴露して世界を騒然とさせた。自伝『スノーデン 独白: 消せない記録』(山形浩生訳/河出書房新社)によると、2001年9月11日にあった米国同時多発テロ事件があったときに彼はコミュニティ・カレッジに通いプログラミングやサーバ管理を学ぶ18歳で、NSA本部のあるフォート・ミードの近くで連邦政府機関に勤務する母親からの電話でテレビをつけ、2機目の旅客機が突入する瞬間を生中継で観たことで、アメリカに奉職する決意を固めたという。軍に志願したスノーデンは、米陸軍に志願するも予備役の特別部隊訓練で骨折し除隊するが、2005年にCIAにシステムエンジニアとして採用される。2006年にはCIA職員として雇用されてコンピュータセキュリティの任に就いたのちに2009年にCIAを辞職して、同年にはNSAと契約を結んでいたDELL社に転職し、日本の横田基地内のNSA関連施設でサイバーセキュリティの指導にあたる。業務のなかで中国が10億人にのぼる自国民の監視体制を敷いていることに驚嘆するとともに、アメリカにも同様の監視システムがあるのではないかという疑念を抱くとともに、のちに赴任するハワイの地下軍事施設KRSOC(Kunia Regional SIGINT Operations Center:クニア地域シギント工作センター)で諜報活動に携わり、実際にそのような監視システムがあることを知って連邦政府に幻滅したことで、内部告発の決意を固めたという。
国家・軍・企業が手を結んだPRISMの衝撃
スノーデンにより暴露されたアメリカの諜報活動は3層からなっていた。1つはテック企業のサーバに直接アクセスしてユーザーの個人データを収集する仕組み、2つめは企業を介さず通信インフラから秘密裡に直接情報を抽出する仕組み、もう1つはメールやブラウザなどインターネットのアクセス履歴から個人をプロファイルするデータ検索・解析システムである。
最も国家と企業への信頼を揺るがせたのは、PRISMと称されるテック企業サーバに直接アクセスするシステムの存在である。これは、各企業から提供された、セキュリティを介さずサーバにアクセスできるバックドアと呼ばれる“抜け道”を経由するアクセス手段で、スノーデン文書により名指された協力企業にはMicrosoft・Yahoo!・Google・Facebook・PalTalk・YouTube・Skype・AOL・Appleなど、誰しもがアクセスしたであろうサービスの提供者が並ぶ。これらは国家安全保障を目的とした秘密監視を承認する非公開の特別裁判所であるFISC(Foreign Intelligence Surveillance Court:外国諜報活動監視裁判所)により承認されたもので、弁護人を立てたり不服申立てをしたりといったことは認められていないため、企業には拒否する権限が与えられていない。この裁判所は1975年に制定されたFISA(Foreign Intelligence Surveillance Act)という根拠法に基づいたもので、CIAやNSA、またFBIが反戦運動や公民権運動を違法監視したり、CIAによる暗殺やマインドコントロール実験などの非人道的な工作活動が明るみになったことが問題視されたことを受けてアメリカ上院に設置されたチャーチ委員会(Church Committee:諜報活動に関する政府活動を調査する米国上院特別委員会)の勧告により、諜報活動の礼状を審査し承認するために設けられていた。しかしスノーデン文書によると、FISA裁判所による1979年から2012にかけての承認率は99.97%で、実質としては監視に歯止めをかけるのではなく、監視を合法化する機関となっていたとされる。
官民が手を結ぶとき
インターネット普及を大きく後押ししたのが、1993年からのクリントン政権下でアル・ゴア副大統領が推進した“情報スーパーハイウェイ構想”だが、同時に政府は通信機器に政府が復号できるバックドアを付与した暗号チップ“クリッパーチップ(Clipper Chip)”の搭載を義務化しようとしていたものの、ACLU(American Civil Liberties Union:アメリカ自由人権協会)やEFF(Electronic Frontier Foundation:電子フロンティア財団)をはじめとした反対や、通信情報に付与されるデータブロックLEAF(Law Enforcement Access Field)の脆弱性が指摘されたことから1997年にこれを断念する。これにより政府によるデータ監視は忌避されたように思われたが、PRISMの存在が顕らかにしたのは民間の暗号で守られた個人ユーザーのデータを、政府が企業を介して閲覧していたという構図だった。超監視社会を描いた作品として、ジョージ・オーウェルの『一九八四』(山形浩生訳/講談社)が挙げられる。本連載でもかつて「破壊せよ、とだれも言わなかった」でも言及した、自由と解放を謳うApple社も、2012年はこの監視体制に与していたことが明らかにされた。2013年に公開されたスノーデン文書が影響したかどうかは不明だが、Apple社は、2015年にカリフォルニア州で発生した銃撃事件の容疑者から押収したiPhoneを閲覧する名目でFBIからバックドアをつくるよう依頼されたもののこれを拒否し、CEOのティム・クックが「民主主義の理念に反する」として裁判も辞さない書簡を公開している。
本連載では前回「無知を問う無知学(アグノトロジー)とジェンダード・イノベーション」ではロバート・N・プロクターは国家や企業、アカデミアが中立性を失った構図から、またロンダ・シービンガーは帝国主義と西洋のアカデミズムが女性や植民地の知と人権を非対称性のもとで毀損した図式から制度的な無知を生じさせたことを記したが、これらの権威的と一般の人々の「有徳な無知」とを併置することの危うさは、現在に通じる情報通信においても看取することができる。
→第3回につづく