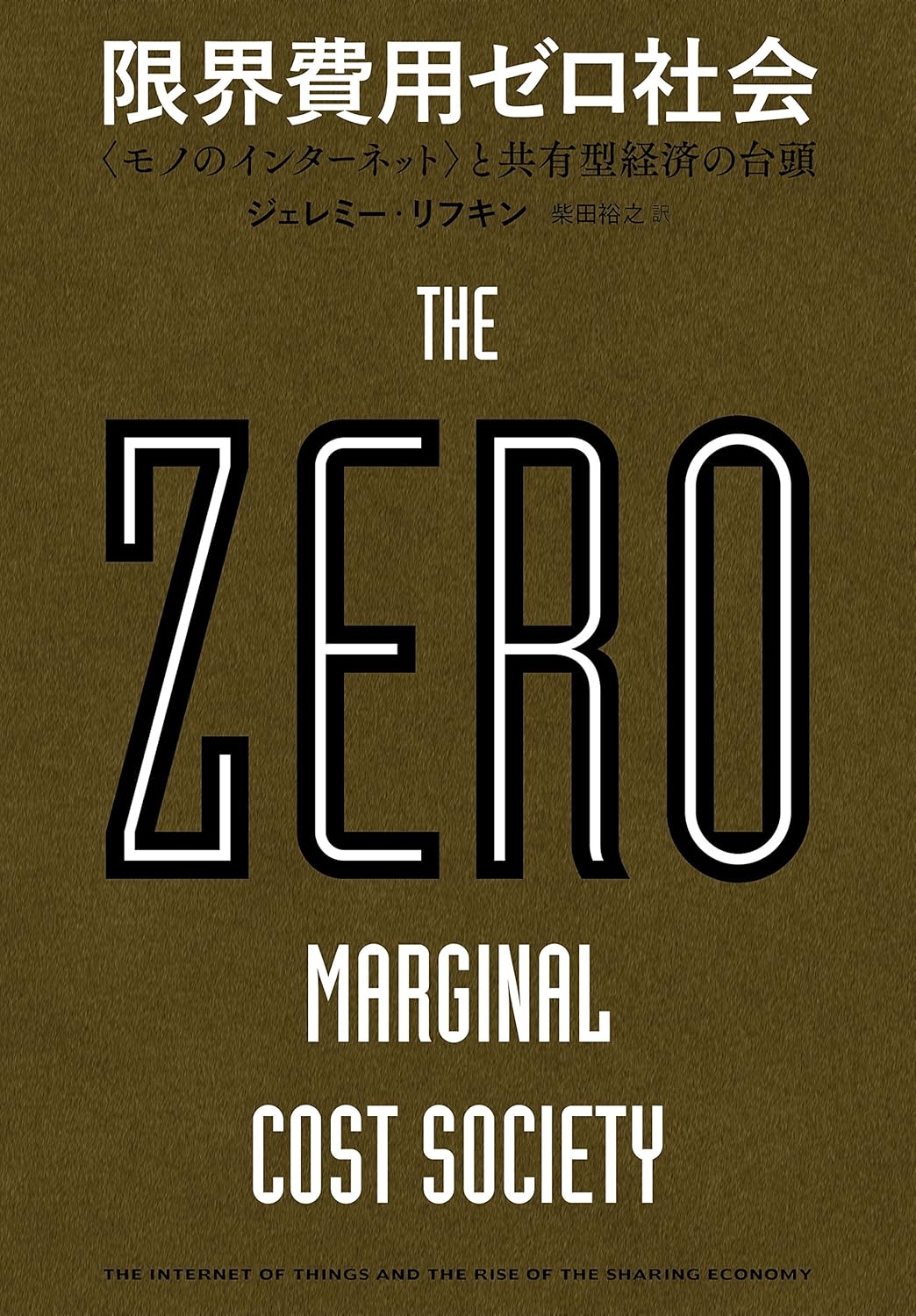京都学派×戦前ポストモダン思想を再検証
近代の超克とは何か
ふたたび遍在と偏在
経済評論家でメルケル時代のドイツの経済施策アドバイザーを務め、『限界費用ゼロ社会 〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』(柴田裕之訳/NHK出版)というベストセラーもあるジェレミー・リフキンと、経済思想家で『人新世の「資本論」』(集英社新書)で話題をさらった新鋭、斎藤幸平の対談を読んだのはすこし前、1月7日朝日新聞の朝刊のことだ。「気候危機と人類の今後」と題した対談では、テクノロジーによる解決を提起するリフキンと、テクノロジーにはあまりにも多くの懸念があり楽観できないという斎藤のあいだで議論がおきる。これもまた、テクノロジーの合理性と、(斎藤が信奉する)マルクス主義の普遍性、それぞれが依拠する正当化のすれちがいだろう。
わたしはまたこの対談に、これまで論じてきた言葉で「遍在」と「偏在」の対照をよみとっていた。テクノロジーはすべての人々を幸せにしうる手段とするリフキンと、一部の者のみが独占するだけだとする斎藤というふうに見えるのだ。
さらに、今回の記事に準えば、小さな物語の多様で複雑な価値と大きな物語としての普遍という対比でもある。現在のAIにまつわる議論、ポストヒューマニズムの議論を読んでいると、それらはまた大きな物語に比する普遍性、正当性への渇望のようだ。レイ・カーツワイルはその典型であるし、多くの加速主義者たちがそのようにみえる。ハラリは渇望こそしてはないが、テクノロジーの進化に普遍性、正当性を譲らざるをえなくなると述べているように思う。
科学を宗教にし、歴史とイデオロギーを新たにし、その正当性で近代を塗り替える。あるいは塗り込めてしまうことこそ、結局のところ、〈近代の超克〉の挫折ではなかったろうか。科学を宗教にした新しい信仰でもヒューマニズムにもとづいたイデオロギーでもテクノロジーが画する新しい歴史でも、結局のところ、形而上学的ファシズムに囚われてしまうのではないか。大文字で書かれた正当性の復活は、そこから決して逃れられないだろう。
わたしたちが目指すのは歴史ではなく、多様性に満ちて遍在する生活ではないのか。個々の言語ゲームをどこまでも共有しうる生活の巨大な広がりこそ目指すべきではないか。生活の巨大な広がりのためにテクノロジーを使うべきなのではないか。わたしはそんなことを考えてはじめている。
新たな歴史ではなく、新たな生活によってしか近代を超克できない。そうできるだけのテクノロジーを個々が手にすることが重要なのだ。遍在こそを求めている。
限界費用ゼロ社会 <モノのインターネット>と共有型経済の台頭
ジェレミー・リフキン (著)
柴田裕之 (訳)
NHK出版
ISBN:978-4891761592
斎藤 幸平 (著)
集英社新書
ISBN:9784087211351
わたしはこの記事を通じて以前から教養ブームを批判してきた。ビジネスパーソンにリベラルアーツの重要性を説いたり、古典の読み込みを薦めたりする似非インテリたちへの違和感とはつまり彼らが大文字で書かれた教養を見せかけの正当化のために用いているように見えることにある。教養というのは、過去の偉人のお墨付きのことだろうか。わたしにはわからない。そんな教養より個々の生活のなかにこそ救いの種はあると思いたい。
そうはいったところで、古今東西、誰しもが追い求めるのは大きな物語だ。自分という存在に正当性が欲しい。安心したいのだから。今も「ビッグヒストリー」がブームだ。わたしも数回前(No.38)で、ヒューマニズムを更新するために新しい「大きな物語」が必要だと書いた。
おそらくは大きな物語と多様な価値観は互いを否定し合うものではないのだろう。これも前々回(No.40「鈴木大拙からスチュワート・ブランドへ ホールアースは宇宙技芸論で語れるか?」)で述べたが偏在と遍在がある種のアンチノミーとして併存するように、大きな物語と多様な価値観も併存するのだろう。わたしたちがしなければならないのは、こうしたアンチノミーに向き合って知的な土壌を耕していくことだ。
──さらに蛇足的追記。
西田幾多郎ふうに、このアンチノミーは“絶対矛盾的自己同一”といえるかもしれないし、この大きな物語と多様な価値観の関係は大きな“主語”と多様な“述語”の関係といえるかもしれない。
わたしは考えている。そんなところに近代を乗り越える思想を掘り起こすきっかけをもう一度、探ることはできないのだろうか?と。