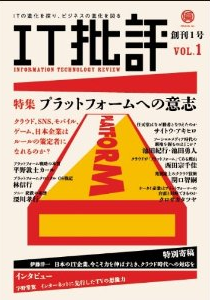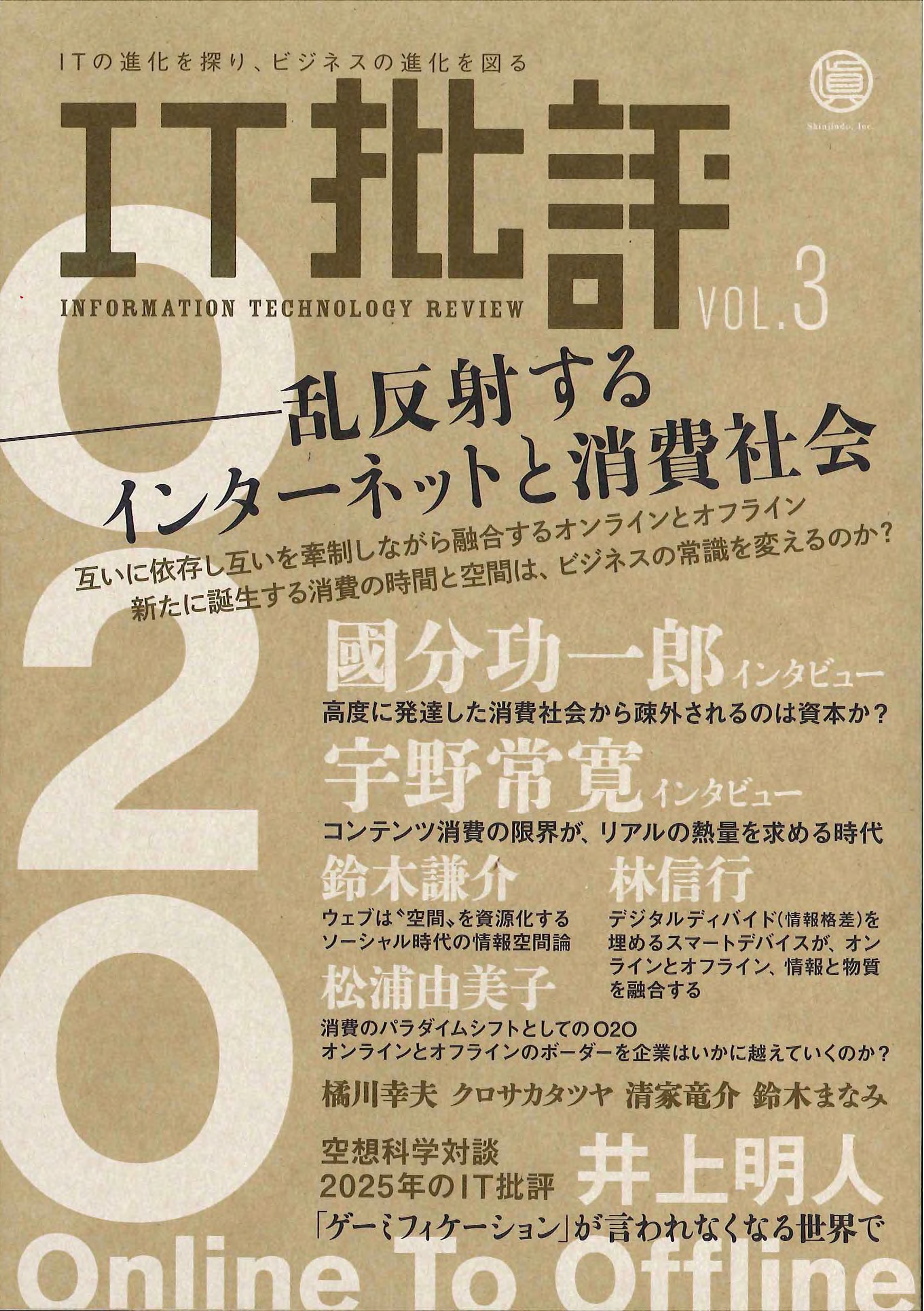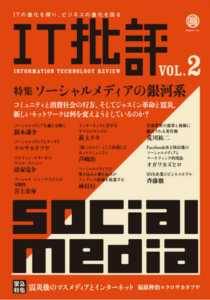ウェブは“空間”を資源化する〜ソーシャル時代の情報空間論 第5回

オンライン(ウェブ)とオフライン(リアル)との間における、ヒト・モノ・カネ・データの交通が激しくなっている。O2O、オムニチャネル、IoT……、キーワードは無数にあり、ウェブとリアルの融合は進む。では、リアル空間がウェブ情報と切り離せなくなったとき、それぞれをどの視点から評価すればよいのか? 内包される問題について、精力的な活躍を続ける社会学者が論じる。
個人情報を買い叩くソーシャルメディア
長い間ウェブのビジネスを支えてきたのは、ウェブサイトを広告媒体と捉え、クリック数などに応じて広告料を取るというモデルだった。多くのサービスは無料で提供され、B2Bの広告費がそれらを支えていたのである。しかしながら2009年頃からインターネット広告の前年比は伸び悩みの傾向にあり、その一方でソーシャルメディアを中心とした利用者の増加、スマートフォンの普及による通信量の増大もあって、サービスを支えるためのリソースコストは高まっているのである。
とはいえ無料で始まったサービスを有料化し、黒字化を達成するのは容易なことではない。そこで近年注目されるようになってきたのが、利用者の属性や行動データに基づいて、個人向けにカスタマイズした広告を表示するというモデルだ。たとえば20代の女性向けには化粧品レビューや体調管理のウェブサービス、30代男性向けにはラーメンの通販といったように、あらかじめ登録された属性情報や嗜好などに基づいた広告を表示するわけだ。
さらに近年では「行動ターゲティング」と呼ばれる手法も登場している。これは、たとえば検索履歴や商品の購入履歴といった、利用者がとった行動から、彼らの次の行動パターンを予測し、広告を出すというものだ。もっともよく知られているのは、アマゾンの購入履歴に基づく「おすすめ商品」の表示だろう。
両者は共に、利用者の情報を利用して広告表示に活用しようとするものだ。そして実は、こうした情報を取得するのに、ソーシャルメディアというプラットフォームは非常に便利だと考えられている。自分がどんな人間であるか、どんなものが好きか、どんなものを買ったかといった情報は、利用者からすれば友達と交流するための格好の「ネタ」だ。しかし事業者から見れば、そうした情報を利用者がソーシャルメディア上に振りまくことで、自社のサービスをより優良な媒体にするための「ネタ」が蓄積されていくとも言えるのである。
事業者にとっての「ネタ」はそれだけにとどまらない。ソーシャルメディア上で利用者が活発なやりとりをするようになると、今度はそのつながり(ソーシャルグラフと呼ばれる)を「口コミ」の手段にできないかと考える者が現れた。テレビのコマーシャルで有名タレントが宣伝するよりも、自分の友達に「その化粧品、私も使ってるけど、よかったよ!」と言われた方が、購買の強い動機付けになると考えられるからだ。
利用者の個人情報や行動履歴、友人とのつながりをビジネスに利用することの詳細な論点や問題点については今回は踏み込まないが、ここで注意しておくべきなのは、これらが「基本無料」が原則となっているソーシャルメディアの世界ならではの収益モデルだということだ。言い換えれば私たちは、タダでソーシャルメディアを利用させてもらう代わりに、個人情報を売り渡しているのである。
特にソーシャルメディアにおいては、不特定多数のネット上のユーザーではなく、現実での自分の友人・知人とウェブ上でも交流することが推奨されている。その背景にあるのが、人々のつながり(ソーシャルグラフ)をビジネスの資源にしようとする事業者の意図だ。こうしたことを可能にするために、これらのサービスは、メールサービスのアドレス帳であるとか、携帯電話の電話帳に登録された相手を、サービス内の「友達」として登録する機能を有していることも多い。現実の人間関係のウェブ化が進むわけだ。
また、(ネットに接続することができれば)あらゆる場所がウェブと結びつくということは、活動している時間はいつでも、ウェブと連動するようになるということでもある。こうしたことを表現するのに、「リアルタイムウェブ」という用語を使う者もいる※4が、重要なのはウェブで公開されている情報が「いま」起きているものかどうかということではない。「いま何が起きているか」ということを、ツイッターやフェイスブックに更新された情報(「タイムライン」という非常に象徴的な名前が付いている)で知るようになるということこそが、その本質なのだ。
私たちは、空間も、時間も、そして人間関係も、私たちを取り巻くあらゆる現実の要素がウェブの情報として取り込まれ、それこそが現実であるかのように感じさせられるようになるという変化に直面している。見方を変えれば、いまウェブは現実のあらゆる要素を取り込んで、もうひとつの現実を作り出し、それをビジネスの要素にしようとしている。つまり「ウェブが現実を資源化している」のである。
こうしたことの何が問題なのか。もっとも大きなものは、「リアル」と「バーチャル」といった二項対立でウェブを捉えることができなくなり、ウェブを客観的に捉える視点が失われてしまうことだろう。たとえば、ウェブ上で関係している人がすべてウェブで出会った人であり、それこそバーチャルな関係でしかないのだとしたら、批判は容易なのだ。「この現実」を足場にして、そのような「にせもの」の関係とは手を切るように指導すればいい。だがウェブ上で交流している相手がみな、現実の生活でも密接にかかわっている相手だとしたらどうだろうか。対面でコミュニケーションをとっているときのかかわりは「ほんもの」で、ウェブ上でのやりとりは「にせもの」なのだから、対面の関係だけに限定して交流すべきだという主張が、果たして説得力を持つだろうか。O2Oとは、こうした「ウェブによる現実の資源化」という傾向の、ひとつの現れに過ぎない。街中を歩いているとき、「この近くで評判のイタリアンレストラン」を検索したり、逆に「あなたの友達が近くにいます!」と通知されたりすることで、その空間の意味が上書きされる。それは私たちが支払うお金の代わりに、私たちを取り巻く現実そのものが資源化され、利用されているということなのだ。
私自身の関心は、現実がウェブによって資源化されることで生じる社会的な葛藤に対してどのように向き合うべきかを考えるところにある。だがより具体的な問題として、たとえばプライバシーの問題、監視社会化の問題を挙げることもできるだろう。あるいはこうした資源化を観光に活かすとなれば、地域社会の問題に展開することもできる。さらに近年、「ジモトに住みたい」と望む若者の増加という傾向を合わせて考えれば、これは若者にとっての新たな空間論の入り口となる現象になるかもしれない。
さしあたって本稿では、そうした議論の入り口となる概念整理を試みたが、本質的に取り扱わなければならない問題は、まだその先にある。近視眼的な流行や利益の追求にとらわれることなくウェブと私たちの社会の未来を見据える取り組みは、今後も続けられなければならないだろう。