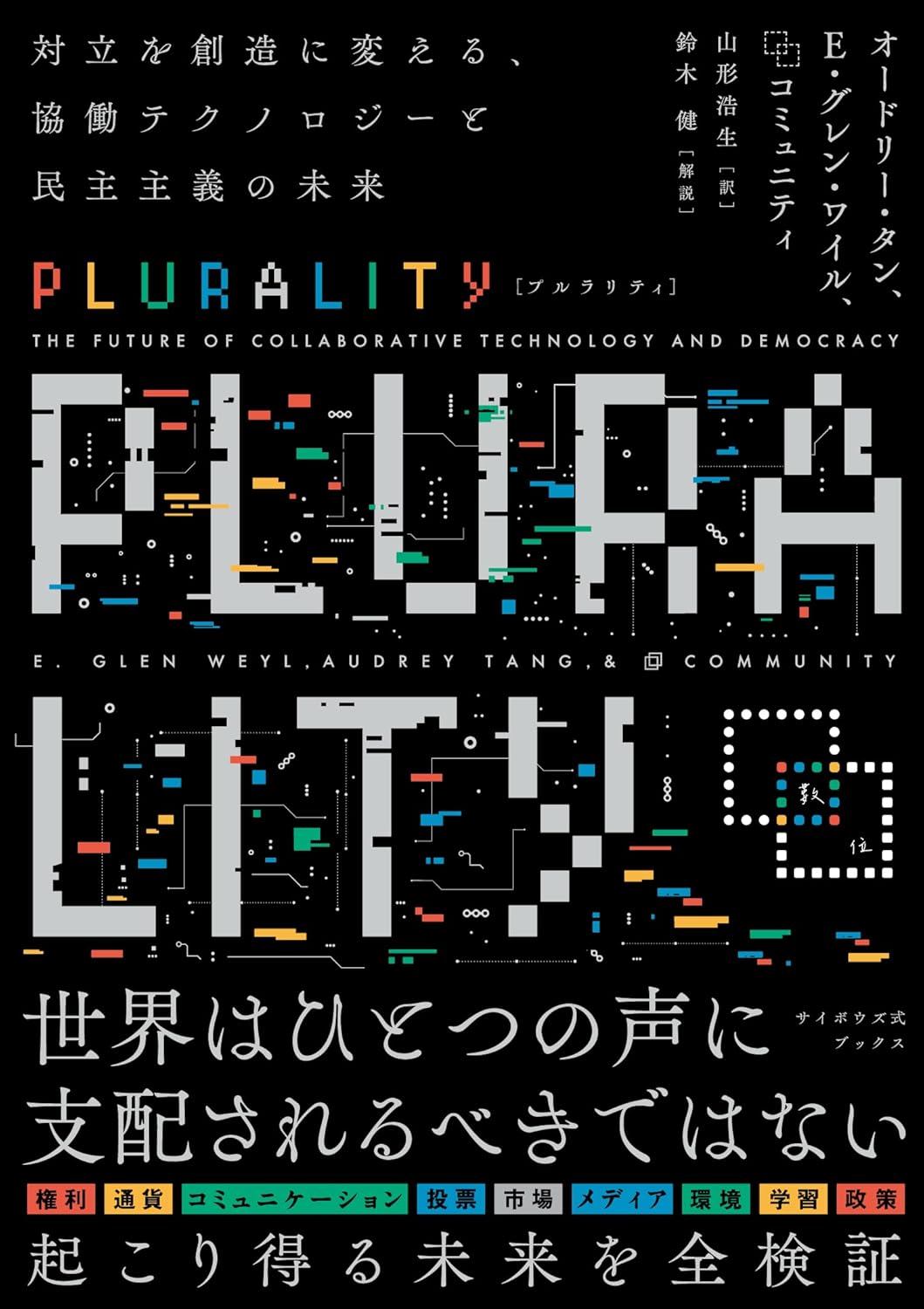AIが顕らかにする社会と個人のありよう
第5回 多数性(Plurality)と分断する個人(Dividual)の時代に

デュルケームが社会を外在的な規範として捉え、群衆を統制すべき対象としたのに対し、タルドは社会を模倣・対抗・発明の連鎖から動的に描いた。その思想はドゥルーズ=ガタリやラトゥールらによって再評価されることとなった。ネットワーク的な社会観としてのこの視点は、現代のAI・SNS時代にこそ意義を持つのではないか。
目次
社会解釈におけるタルド再評価
1902年に、デュルケームはソルボンヌ大学に「教育学および社会学の講座」を持つこととなり、これがフランスではじめての“社会学”を冠する講座となった。また『道徳教育論』(麻生誠・山村健訳/翻講談社学術文庫)や『教育と社会学』(古川敦訳/丸善プラネット)などを著し、キリスト教に依拠しない道徳概念の涵養と国家に奉仕する社会を説いたことで第三共和政にも受け入れられたことから「社会学=デュルケーム学派」という定式は強固なものとして引き継がれることとなった。一方、アカデミック・ポストを持たない法務省の官吏だったタルドの思想は、長らくデュルケームに論破されたものとして記憶されるに留まった。
その後、タルドが再発見されたのは1980年に刊行されたジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの共著『千のプラトー:資本主義と分裂症』(宇野邦一他訳/河出文庫)によることが大きい。第7章 顔貌性(がんぼうせい)のエピグラフには『社会法則/モナド論と社会学』書中の言葉「すべては社会的である、しかし分子的なレベルにおいて(Tout est social, mais à la manière moléculaire)」が置かれている。
この章で語られる「顔貌性」というのは、顔が他の器官とは異なり、外からは視線や表情、皮膚が、そこになにかを読みとる対象として記号化され、内側では目や口、鼻など視線や感情を引き寄せて「内面」を生成する主観化の場所としての二重構造の抽象機械として解されることを示した。その意味、で、顔認識AIは意味と主体の顔への還元を行う高度な顔貌性装置であるし、SNSのプロフィール写真は顔による主観化の演出、また監視カメラとアルゴリズムによる統治は、見る/見られる関係の制度化として今日的に指摘しうるだろう。
タルドの名が直接に示されているのは『千のプラトー』においてのみであるが、ドゥルーズの中心命題である“生成変化”は、タルドの社会論と共鳴するものではある。『差異と反復』(財津理訳/河出文庫)においてドゥルーズは「真の反復とは同じものの再現ではなく“差異を通じての変化の生成”である」と論じている。これはタルドが『模倣の法則』で述べた「社会は模倣によって成り立っているが、模倣は単なるコピーではなく、常に変形と発明を伴う」という論に近似している。『千のプラトー』に先立って1972年に刊行された『アンチ・オイディプス』(宇野邦一訳/河出文庫)のキー概念“欲望機械”における「欲望 – 生産の連鎖」「無意識 – 機械的接続体」「機械 – 接続・断絶の単位」の連鎖のそれぞれのシェーマについて、タルドの「模倣の連鎖 – 社会的創発」「心的作用=外部的関係の反響」「模倣=拡張・逸脱の単位」と置き換えても、さほどの矛盾は生じない。
ドゥルーズ=ガタリの政治的意義を再読して論じる理論家のエリック・アリエズ、『千のプラトー』主要英訳者の1人であるモントリオール大学のブライアン・マスミなどは、タルドをドゥルーズに隣接する社会学者として位置づけているほか、後述するラトゥールは『社会的なものを組み直す』において、タルドを「最もドゥルージアンな社会学者」と明言している。
エミール・デュルケム (著)
麻生誠, 山村健 (翻訳)
講談社
エミール デュルケム (著)
古川 敦 (翻訳)
丸善プラネット
ネットワークにより解釈するタルドの優位性
タルドを顕著に評価し、理論的に継承したのは、本連載「AIの倫理とその再配置を考える」でも紹介した、社会学を出自とするブルーノ・ラトゥールによるアクター・ネットワーク理論(Actor-network-theory:略称ANT)である。世界のあらゆるものを、絶えず変化するネットワークの結節点として扱うANTでは、人・モノ・技術それぞれがアクターとなって連関し、翻訳されることで形成されるものとしており、社会もその例外ではない。ラトゥールはアクターを外部から切断しブラックボックス化する社会を問いなおすプロジェクトにおいて、アクターを拘束する外在的なデュルケーム的社会を批判するなかで、理論的オルタナティブとしてのタルドを再発見する。模倣・差異・発明の連鎖により構成され、小さな差異が拡大されて社会になるというタルドの視点は、あらゆるものが諸アクターの連関により現出するというANTの動的なヴィジョンとも一致するものだった。ラトゥールは『社会的なものを組み直す――アクターネットワーク理論入門』(伊藤嘉高訳/法政大学出版局)においてタルドの社会観の優位性を記し、共著『Gabriel Tarde and the End of the Social』(未訳/Routledge)では「オルタナティブな社会科学のためのオルタナティブな出発点(an alternative beginning for an alternative social science)」と評している。
ブリュノ ラトゥール (著)
伊藤 嘉高 (翻訳)
法政大学出版局
相互浸透するテクノロジーと社会のなかで
ここで、第1回冒頭の生成AIが起因となった2つの事件を思い起こしてみよう。いずれも外形的には、生成AIが社会規範から逸脱した架空のキャラクターを奉じたユーザーによる不幸な結末として語られることが予期される。それは、ニューメディアから生じたフィクションが――主として孤独な――若者に悪影響を与えるメディア悪玉論の延長線にあるものだ。
しかし、AIをアクターとして考えるとどうだろう。デュルケーム的なパターナルな社会ではなく、個々の関係性のなかでネットワーク的にもたらされるものを社会であると考えれば、対話的に模倣・対抗・発明というスキームのなかで生成されるものは、コクーニングされているといえど社会の形成に近似しているようにもみえる。たとえ反復におけるズレにおいて、一般的な規範から逸脱したものだとしても。
ハンナ・アーレントは主著『人間の条件』(千葉眞訳/筑摩書房)において「人間は複数である(Men, not Man, live on the earth)」と述べる。アーレントは抽象的な1人の人間(Man)というものは存在せず、世界に生きるのはだれ1人として同じでない個別具体的な人間たち(Men)であるとして、この“多数性(plurality)”にもとづく各人の対話と行為により公共性、つまり社会が存立するのだという。言い換えれば、多数性を包含し得ない社会が排除を生むのだとする。このアーレントの「人間の条件」に呼応して、AIテクノロジーを用いて透明性・共同設計・市民参加を確保することで、多くの声を受け入れた合意形成に基づく政治を構想するのが台湾のデジタル担当閣僚を努めたオードリー・タンである。マイクロソフト・リサーチの主席研究員でもある経済学者グレン・ワイルとの共著『PLURALITY:対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』(山形浩生訳/ライツ社)は、タイトルもそのものながらタンが幾度もアーレントを参照している。
アーレントの多数性は、社会だけでなく個人にも向けられる。『精神の生活』(佐藤和夫訳/岩波書店)において、アーレントは「思考は自己との対話(two-in-one)」であるとしたうえで、内的対話を持たない人は“凡庸な悪”に陥りやすいと断じている。またドゥルーズは規律社会から管理社会への移行を論じた1990年の小論「管理社会についてのポストスクリプト」において「個人は分割的存在(dividual)となり、大衆はサンプル、データ、市場、バンクとなった(Individuals have become ‘dividuals’, and masses have become samples, data, markets, or ‘banks’.)」と論じ、ミシェル・フーコーの論じた規律管理社会ののちにやってきた管理社会では、主体はデータベース・コード・パスワード分割され数値化される「分割的存在(dividual)」になったと論じている。これは、ルソーやカントが論じたような国家の主権的個人「in-divid-ual(分割できないもの)」が溶解したと読むことができる。
表記の事件が、生成AIを介した陰惨な事件であることは間違いない。しかしながら、私たちがここから考えることができるのは、すでにAIを包含した社会というものが流動的で暫定的であること、そして個人というものを、もはや1つの側面に基づいた個体として“属人的”に考えるべきではないということなのかもしれない。もしくは現在のAIが持つ準-人間的な側面と非-人間的な側面について。読者の方々にとっては弥縫的な結論づけのように思われるかもしれないが、複数の構成要素からなる社会と、複数の自己からなる個人とについては、改めて論を立てたいと思う。<了>
ハンナ アレント (著)
志水 速雄 (翻訳)
筑摩書房
PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来
オードリー・タン, E・グレン・ワイル (著)
山形浩生 (翻訳)
ライツ社
ハンナ アーレント (著)
佐藤 和夫 (翻訳)
岩波書店