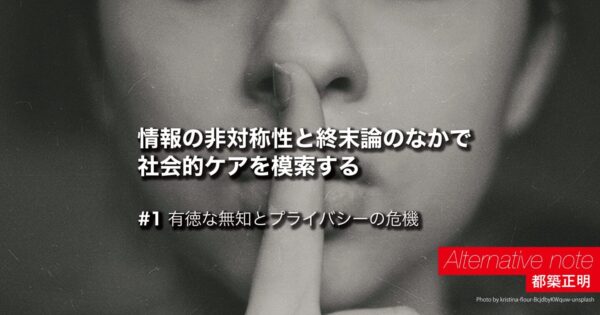AIが拡げる生命科学の可能性─藤田医科大学教授・八代嘉美氏に聞く
第3回 研究開発と臨床、医療と社会実装を架橋する
脳死の議論をきっかけに生命科学に関心を抱く
学部を卒業されてから、生命科学を専攻されたのはどのようないきさつからでしょうか。
八代 高校生のときに、立花隆さんと利根川進さんの対談『精神と物質』(立花隆・利根川進著/文藝春秋)や『21世紀 知の挑戦』(立花隆著/文春文庫)を読んで分子生物学に強い関心を抱きました。当時は臓器移植法の議論があり、脳死の問題がクローズアップされていました。立花さんが『脳死臨調批判』(立花隆著/中央公論新社)で脳死臨調(臨時脳死及び臓器移植調査会)について書かれていて、それを読んでいくなかで、脳死は不可逆的なものとして規定されているけれど、これはいつまで不可逆なのだろうという疑問を抱きました。生命科学や医学が発展することで不可逆ではなくなるポイントがきたら、それまで臓器移植で救われていた患者さんを救えなくなるのではないかと危惧を抱きました。他にアプローチがないだろうかと考えて、再生医療の可能性について考えるようになりました。
再生医療そのものについては、どのような経緯で関心を持たれたのでしょう。
八代 当時はES細胞の話がよく報道されていました。ヒトES細胞といえば、1998年に樹立され、1999年に日本で最初に再生医療の製品を承認されたJ-TEC(株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング)という再生医療ベンチャーが愛知県に設立されました。J-TECの創立にも携わった名古屋大学医学部の上田実先生が再生医療黎明期のスター研究者で、地元でもあったので、よく新聞などでも話題になっていたんです。それらの記事を読んで再生医療を知り、興味を持ったのが大学入学の直前のことでした。
学部生のころから生命科学に携わられていたのでしょうか。
八代 当時の名城大学薬学部には細胞生物学を研究しているところがなく、学部では古典的な生化学の研究室にいました。そこは糖尿病を研究する教室だったのですが、肝臓は糖代謝に重要な役割を果たすんですが、人間の臓器のなかで唯一、大人になっても再生能力を持っている臓器です。なので、まずは肝臓をやろうと思ってそこに行ったんですね。准教授だった豊田行康先生が、私が再生医療に関心を持っていて東京大学の大学院に行きたいという希望に理解を示してくれて、分子生物学や細胞生物学に行っても使えるだろうということで、古典的な生化学実験をいろいろと教えてくださいました。
大学院から本格的に再生医療の研究をはじめられたのですね。
八代 東京大学医科学研究所の中内啓光先生の研究室に入りました。中内先生は造血幹細胞を専門にされている方で、現在は東京大学医科学研究所特任教授のほか、スタンフォード大学医学部教授と東京科学大学の特別栄誉教授をされています。ドクターの1年目には中内先生とは共著で『再生医療のしくみ』(八代嘉美・中内啓光共著/日本実業出版社)も執筆しました。
同書は中見出しがそれぞれSFの名作へのオマージュになっていて、SFへの愛を感じます。
八代 いまは日本SF作家クラブの会員でもあります。小難しいとかオタクくさいという人もいますが、そしてそれも否定はできませんが(笑)、科学への想像力を育むには、もってこいのジャンルだと思います。
『iPS細胞: 世紀の発見が医療を変える』(平凡社新書)終章にはフランケンシュタインの話をきっかけに、生命科学の進歩とSF小説との関係を論じられていて引き込まれました。本サイトでも、AIへの不安や現代のラッダイト運動について“フランケンシュタイン・コンプレックス”を挙げて考察したことがあります。
八代 『フランケンシュタイン』(メアリー・シェリー著/小林章夫訳/光文社古典新訳文庫)は、テクノロジーへの畏れを描いた作品として、いまでも重要な作品です。ダーウィンの進化論や細胞説が成立した19世紀前半に書かれた作品でもあります。この時代が、テクノロジーが生命に近接する予感や不安が生じているのだと思います。