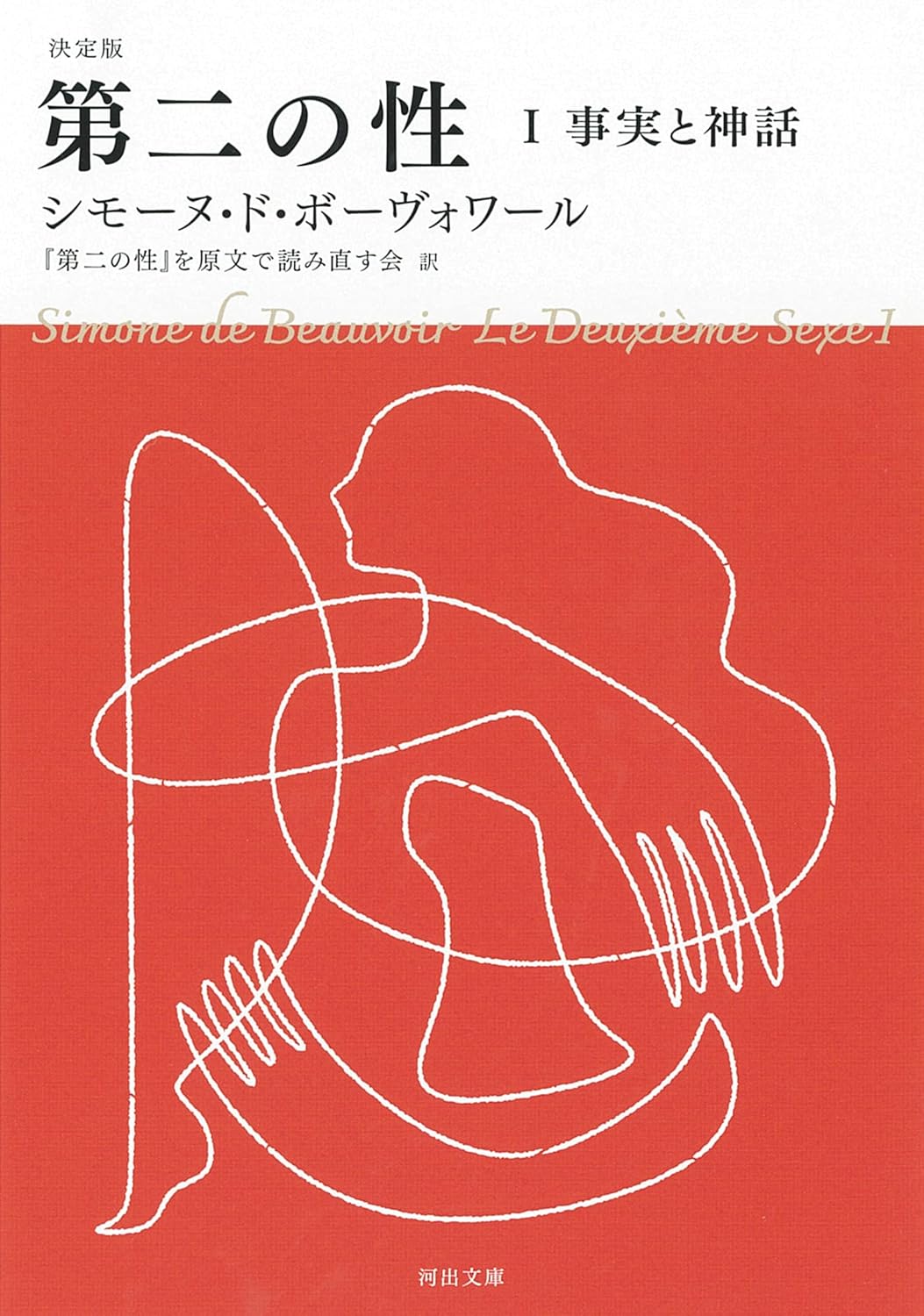サイボーグ・フェミニズム前史
第4回:再定義される性とジェンダー

人について考えるさまざまな思想は、相互に関連しながら展開されてきたが、人文学という呼称が示すように、それは言語に特権的な地位を与えてきたロゴス中心主義的な側面を強く有していた。20世紀後半には、それを相対化する思潮が芽生えたが、それもまた乗り越えられていくこととなる。
ボーヴォワールの『第二の性』からレヴィ=ストロース、フロイト/ラカンまで──構造主義・精神分析を経て再考される性-ジェンダー規範論を解説する。
目次
再考される「性-ジェンダー」規範論
ドイツ観念論の哲学者ヘーゲルは『精神現象学』のなかで、自己は理性においてではなく、他者のなかに存在する自己を見出すことによって認識されるという相互承認論を提示した。
シモーヌ・ド・ボーヴォワールはキャリア初期に、のちにレーモン・クノーによる講義録『『ヘーゲル読解入門――『精神現象学』を読む』』(上妻精・今野雅方訳/国文社)として刊行される、アレクサンドル・コジェーヴのヘーゲル講義に大きな影響を受けている。
1949年に著した『第二の性』執筆に先立つ1947の評論「両義性のモラル」(『ボーヴォワール著作集 第2巻』所収/青柳瑞穂他訳/人文書院)ではこの承認論を「個別性に欠ける」として批判している。
人口に膾炙して久しい「女は女に生まれるのではない、女になるのだ」という言葉は、男というカテゴリーから疎外された他者として強制された社会的な構築物として女のジェンダーを定義づけたものとされ、その立場を脱して実存的な主体となるための女性の権利を獲得しようとする運動の理論的支柱となった。
その背景には、非対称的なジェンダーのもとで、新たな男女の関係を弁証法的に産出することは不可能であるという断念があった。
ボーヴォワールが戦略的に採用したのは、社会規範や慣習を形成している男性的な言説中心主義に、欲望の対象としての女の身体を対置することだった。
女性は普遍的な規範からの他者として脱文脈化されているが、女の身体に他者性をしるしづける男性的なロゴス中心主義の意味機構のほうは、脱身体化されているではないか、という批判である。
だからこそ、ボーヴォワールは自由な身体に基づいて女が主体性を持ちうる道筋を説いたのである。
とはいえ身体と精神とを対立させる二分法がプラトンからデカルトに連なる心身二元論の延長としても捉えられるだけでなく、通時的な理解においても齟齬を生じさせる。
ボーヴォワールの言うように、男性的な社会文化的な強制においてジェンダーとしての“女になる”のであれば、それ以前はなにとして生まれるのかという疑問がある。
他の多くの動物のように、生物学的な雌雄としての性があるというのが性(セックス)と性別(ジェンダー)を区別する一般的な認識ではあるが、その認識を敷衍すれば、生物学的な性が先験的に社会文化的なジェンダーを受け入れる準備をしていることになり、その生物学的な性は、女性がジェンダーの役割に基づいて出生した一方の性差として発生したという無限後退を辿らざるを得ないこととなる。また、男性的強制によりジェンダーがもたらされるというこの定式からは、セクシャル・マイノリティに属する人々の性自認がいかに発生するのかは不鮮明になってしまうことからも、少なくとも現代においては再考の余地が残されているように思われる。
アレクサンドル コジェーヴ (著)
上妻 精 , 今野 雅方 (翻訳)
国文社
ISBN:978-4772001694
シモーヌ・ド・ボーヴォワール (著)
『第二の性』を原文で読み直す会 (翻訳)
河出書房新社
ISBN:978-4309467795
ボーヴォワール (著)
青柳 瑞穂 (翻訳)
人文書院
ISBN:978-4409110027
構造主義と精神分析におけるジェンダー観
ボーヴォワールとはフランスの哲学教授資格試験アグレガシオン取得後の教育実習の同期生でもあったクロード・レヴィ=ストロースは、2校のリセ(フランス中等教育学校)で哲学教員として勤務した後に、ブラジルに新設されたサンパウロ大学で社会学教授として招聘される。
大学での講義の傍らブラジル少数民族を訪ねる文化人類学のフィールドワークを行うほか、任期終了後もブラジル横断の長期調査を行うなかで親族と部族間の構造論を着想する。
その後一旦は帰仏するものの、ナチスによるユダヤ人迫害を逃れるためにアメリカに亡命し、移民知識人のコミュニティで文化人類学の講義を行う。
このコミュニティで出会った言語学者ローマン・ヤコブソンに構造言語学の方法論を学び、それを援用した部族間の構造分析『親族の基本構造』(福井和美訳/青弓社)を執筆したのちにまた帰仏する。
1949年に刊行された同書では、あらゆる親族組織には、身内の女性を花嫁として贈与する普遍構造が存在すると述べられる。
結婚制度の構造には、親族関係を強化するとともに差異化するという意味作用があり、また親族婚と同性愛を禁止の規範を非言語的に維持されているとされる。
この関係においては、親族とは父権的氏族であり、女性は関係項として機能することとなる。
親族論を記号論的に捉えたレヴィ=ストロースの思考は、実存主義にかわる新しい思想として注目を集め、フィールドワークを回顧的に記した1962年の著作『野生の思考』(大橋保夫訳/みすず書房)がベストセラーになると、かれは構造主義の祖として新思潮の旗手とされた。
『野生の思考』終章では、サルトルの主著『弁証法的理性批判』(竹内芳郎他訳/人文書院)への批評を通じて、実存主義を「主体偏重の思想である」とした痛烈な批判が記されている。
親族婚について、フロイトの提示したエディプス・コンプレックスを想起する人も多いだろう。
簡単に紹介すると、男児は小児期において無意識に身近な異性である母親に性愛感情を抱き、父親への敵意を抱くもののそれが断念され、やがて父への同一化を求めて母親の愛情を得ようとするなかで倫理観のような超自我を獲得し、性自認を得るというものである。
フロイトによると女児は父への同一化を望むなかで父親を羨望し、性自認を得るとされる。フロイトの直系を自認したジャック・ラカンはそれを推し進め、母親への愛情を得ようとする幻想界に安住することは“父の名”において断念されることとなり、それを埋め合わせるために象徴を獲得するとする。
この象徴界が言語コミュニケーションを行う場であるとされ、人は象徴界を通じて現実界と関わるというのがラカンの大まかな人間理解である。付記すると、ラカンもまた、パリの高等研究実習院でコジェーヴのヘーゲル『精神現象学』についての講義を受講したひとりである。
クロード・レヴィ=ストロース (著)
福井和美 (翻訳)
青弓社
ISBN:978-4787231802
クロード・レヴィ=ストロース (著)
大橋 保夫 (翻訳)
みすず書房
ISBN:978-4622019725
ジャン・ポール・サルトル (著)
竹内芳郎 , 矢内原伊作 (翻訳)
人文書院
G.W.F. ヘーゲル (著)
長谷川 宏 (翻訳)
作品社