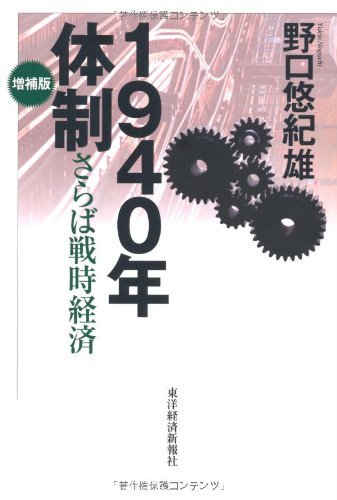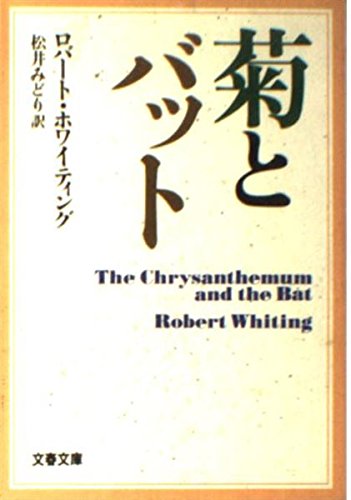WBCから1940年体制まで。野球と科学技術の日本近代史
科学と野球の150年──日本の近代化とサムライジャパンの進化
科学立国が求めた1940年体制
明治以後、日本への科学技術の流入と受容を論じたのは、山本義隆の『近代日本一五〇年——科学技術総力戦体制の破綻』(岩波新書)である。明治以降の日本が、殖産興業・富国強兵を第一義にして科学技術をいかに振興してきたかを闡明することができる。山本は次のように述べる。すこし長いが本稿の論旨を強めるものだから引いておく。
大部分の日本人にとって、近代西欧文明の優越性は、社会思想や政治思想によってではなく、欧米の科学によって表されていたのであり、しかもその科学は、「黒船」つまり強力な大砲を備え蒸気を動力とする軍艦、すなわち軍事技術に体現されていたのである。
近代日本の150年とは、その半分が戦争の時代である。殖産興業・富国強兵が求めるのは挙国一致の軍需産業の推進であり、山本が「科学技術総力戦体制」という国のかたちである。「末は博士か大臣か」という立身出世のモデルに表れる博士は、端的に工学博士であり、それが御国のためと信じられていたのは、ついこのあいだまでのことだ。
私たちは短期間で国際競争に勝つために、原理主義的ともいえるほど過激に科学化を推し進めた。そこに(社会思想・政治思想をふくむ)倫理は抜け落ち、国を挙げて破滅へと戦争の道を邁進し、その反省もおろそかなうちに工業によって経済成長を成し遂げてきた。山本の同書にもあるのだが、ハーバー・ボッシュ法によって空気中の窒素からアンモニアが生産され、それは火薬の原料となり世界大戦の資源となり、戦後は肥料として日本の農業に欠かせない存在となった。日本窒素肥料株式会社が高度成長期に水俣病を引き起こしたことは有名だ。この会社の創始者である野口遵は、先に書いた世界初の総合大学の工学部である、東京大学工学部を出たエンジニアである。山本が同書でいうように第2次世界大戦の敗因として「科学戦に敗れた」と言いながら、科学者たちへの追及も科学者たちの反省もついぞ聞かれなかった。なぜなら、科学戦の敗北を取り戻すべく「科学振興による平和国家の建設」という新たな題目がどこからともなく与えられたからである。
科学の挙国一致体制は戦時中だけの話ではなかったことは、野口悠紀雄の『1940年体制—さらば戦時経済』(東洋経済新報社)でも明らかだ。戦前期にまさに戦争に勝つために生まれた「日本型経済システム」として挙国一致体制は戦後もその目的を経済成長にシフトして生き残りつづけた。わかりやすい例でいえば、大手広告代理店の電通は戦前、政府による情報通信機関の一元化の方針によって大手通信社が合併され設立した同盟通信社がその巨体のまま残ったものである。これは多くの国内産業においても同様であったし、そういう時代はついこのあいだまで続いてきた。私たちはある意味、ずっと戦時下にあったともいえる。
野口は同書で1940年体制の特徴を「生産者優先主義」と「競争の否定」としている。国を挙げての「産めよ、増やせよ」であり、「護送船団方式」「株の持ち合い」という強く大きい者だけを優遇する産業構造によってひたすら経済成長に集中したのだ。科学技術は日本政府にとって絶対の価値であり目標であり続けた。歴史も伝統も顧みられることはなかった。倫理は抜け落ちたままであった。
ところで、山本義隆は東大全共闘のリーダーとして名を馳せた人である。東大の物理学研究室でノーベル賞を期待されるほどの科学者だった。山本は高度成長を進める日本において、倫理の抜け落ちた科学技術に疑問をもった。それを推し進める大学、政府に疑問をもった。倫理を取り戻そうとした。それは全共闘運動に参加する多くの若者に共通する疑問であった。全共闘の時代は、ヒューマニズムを第一義とする実存主義の時代でもあった。科学技術に対する反省から、人間の実存が問われた。新実存主義が登場した現代は、全共闘の時代にし残した反省をいま一度しなおすべき時代なのかもしれない。
山本義隆 (著)
岩波新書
ISBN:9784004316954
野口悠紀雄 (著)
東洋経済新報社
ISBN:9784492395462
職人が求めた技術の先鋭化
明治維新のところで「西欧化」といった。ここに込めた意味はここまで見てきたように科学化のことを一面とし、そのほかの面には宗教と文化がある。
日本が近代化を進めるうえで、もうひとつ受容を余儀なくされたのはキリスト教である。「和魂洋才」はむしろ抵抗のスローガンとしてあったと考えるべきだと、村上陽一郎は『科学史・科学哲学入門』(講談社学術文庫)で論じる。西洋が求める普遍的な価値観の背骨にキリスト教をみるのは当然である。神道も仏教も当時は思想性を失って儀式化していたのだから流入に対する障壁もない。日本の近代化を、キリスト教を基盤とする科学思想の受け容れにあると、村上の同書はいう。
しかし、私に残る疑問は日本がキリスト教を背骨として科学技術を受容したのであれば、なぜに倫理が抜け落ちてしまったのかという点である。
私はそこに科学と技術を同一視したことによる弊害を見てとる。日本は古くから職人の国である。それこそ司馬遼太郎の短編集『酔って候』(文春文庫)に収録されている「伊達の黒船」の主人公である前原巧山は金物細工の職人だったが、藩の命令で長崎に留学、初めてみた蒸気機関をわずか4年で製造してしまう。江戸末期の職人で日本の近代化に寄与した人物は、からくり儀右衛門と呼ばれ東芝の元を創立した田中久重など数多い。田中は鼈甲細工の職人であった。
こうした優秀な職人は近代技術の取り込みに大きな功績があったのと同時に、思想としての科学の受容を妨げた可能性を感じるのだ。トリビアリズムを追求するのが職人だからだ。「神は細部に宿る」のである。普遍性や標準化よりも、個性や独自の工夫を欲するのが職人のアイデンティティではないだろうか。優秀であれば、さらにアイデンティティは強化される。技術の先鋭化をこそ後押しする状況ができあがる。
海外からの文物の流入は、なにも明治期日本に限らず思想よりも具体的な物や技術が先行するのも常ではある。物や技術が先行する、つまり目的より手段が先行してしまうと、手段は容易に先鋭化し過激化する。技術そのものを目的としたことが日本の近代技術の振興を支えたのも事実だが、それ自体が目的となれば容易に暴走を許す。本来は手段であるべき技術から倫理(目的)が抜け落ちる。時間的な秩序と倫理の関係は、この目的と手段の順番(秩序)が狂うことだからだ。
村上陽一郎 (著)
講談社学術文庫
ISBN:978-4-06-522839-5
司馬遼太郎 (著)
文春文庫
ISBN:978-4-16-766310-0
「サムライ」は何を象徴するか?
私はこの問題は現代のAIを象徴とする情報科学技術の振興にまで通底していると考える。それは、科学であるより技術であることを優先しているように見えるからだ。サイエンスよりもエンジニアリングを追うことは、なによりも経済成長にとって理にかなっている。
AI研究における倫理観が、たとえば先端技術のひとつであるゲノム編集のそれに比べて非常に遅れているように感じるのは、一方が端的にエンジニアリング重視であることに対し、もう一方がサイエンスを重視していることにあるようにも思うし、また歴史や伝統という論点でも医学や生理学はなんらかの文明を有した国であればたいてい長い歴史があるし、私たちの生活に根を下ろさざるを得ない分野でもある。
AI研究において、倫理を担保するはずの目的と手段の秩序が狂ってはいまいか? そのことを真剣に問い直さなければならない。歴史の流れと生活の根とを見出さなければならないのではないか? そう思っている。
この稿は野球について書き起こすことで始めた。野球にはすでに150年以上の歴史を日本のなかに紡いできた。それは、常にメジャーリーグという本物に対する劣等感と同居する歴史であった。本物に追いつくことを目標にしつつ、その手段は旧弊な根性主義でありつづけた。挙国一致体制の残滓のような高野連にも、高度経済成長期社会の匂いの残る日本野球機構にもどこかに封建的な錯誤があった。高校球児の多くがいまも坊主頭である様子に軍隊を見出すのはそんなに難しいことではない。
日本人はグループ思考や協調性を重んじ、何事にも努力を求め、年長者を敬い、面子にこだわるが、彼らのこうした生活観がこのスポーツのすみずみにまで浸透し、独特の性質をもたせるようになった。
『菊とバット』(松井みどり訳/文春文庫)で、こう書いたのはロバート・ホワイティングである。1970年代も終わりのことだ。目次には「野球武士道」、「スーパー・サムライ」といった言葉が並ぶ。日本野球の特異さを際立たせ、アメリカのベースボールとの違いに日本文化の本質を見出す。当時は読売ジャイアンツの全盛期であった。当然、ジャイアンツの話題が多くを占める。ジャイアンツこそ、1940年体制(正確には戦後、CIAの意図を汲んで正力松太郎が創始したのだが)の権化のような存在であった。現在でもオーナー企業の多くが1940年体制の残滓に与するように見える。ライブドアによる近鉄買収の際のオーナー会議の団結や1リーグ化構想で選手会と揉めた際の渡邉恒雄の発言にも、1940年体制の2つの特徴が如実であった。
1970年代終わりといえば、経済的にもアメリカに打撃を与えていた日本に対する関心が高まっていた時期で、日本的経営を高く評価したエズラ・ボーゲルの『ジャパン・アズ・ナンバーワン—アメリカへの教訓—』(広中和歌子、木本彰子訳/阪急コミュニケーションズ)が刊行されたのは『菊とバット』とちょうど同じ頃だ。ボーゲルは同書でまさに1940年体制を維持して経済成長に邁進する日本を評価したのだともいえる。
野球の国際大会に参加する日本代表の名称は「サムライジャパン」である。しかし、ここに付けた「サムライ」と、ホワイティングが指摘した「サムライ」には隔世の感がある。
いつしか日本プロ野球はメジャーリーグに劣後するものといった認識はアメリカ国内にさえなくなりはじめている。かつての「サムライ」がエラーに対し切腹も辞さない悲壮感の象徴であったとしたら、現在の「サムライ」は挑戦を求める求道者とゲームへの敬意に満ちた様式美の象徴である。それこそは、勝利の前に正しく勝負することという、目的と手段の秩序を徹底した倫理観があるように思う。私は日本のプロ野球の成熟を見た気がした。野球に比べて、日本の科学はどうなのだろう。
ロバート ホワイティング (著)
松井 みどり (翻訳)
文春文庫
ISBN:978-4167309176
エズラ F.ヴォーゲル (著)
中 和歌子, 木本 彰子 (翻訳)
阪急コミュニケーションズ
ISBN:978-4484000497
最後に──。
この頃、ネット言論界隈でよく耳にするようになった「老害」という言葉だが、その定義は物分かりの悪い高齢者を指すのではなく、1940年体制で甘い汁を吸った人を指すべきだ。大企業、大メディアで肩でかぜ切ってきた人のほとんどがかつての信用を失っている。彼らは往々にして反省がない。未だに手段と目的を履き違えていることに気づけない。
だから、形骸化した「資本主義批判(みずから資本主義で肥え太ったのを忘れている!)」「権力批判(みずからが権力側なのを忘れている!)」だけで偉そうにしていられるわけだ。目端のきく連中は若手の論客に積極的に擦り寄って、自分だけは「老害」ではないような顔をしてやがる。敗戦の反省をしなかった78年前の大人たちとまったく変わりゃしない。
翻って若者に言いたいのは、「老害」批判を市井で苦労を重ねてきた人たちに無闇に向けるべきではないということだ。