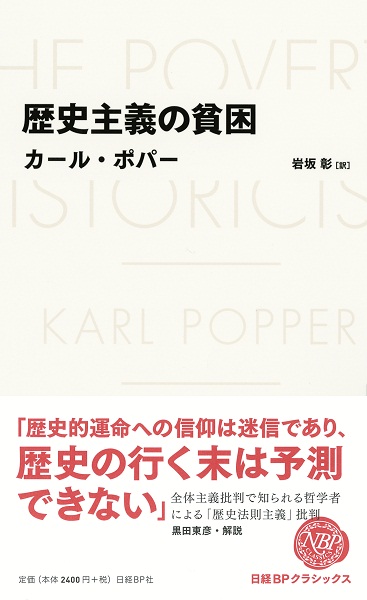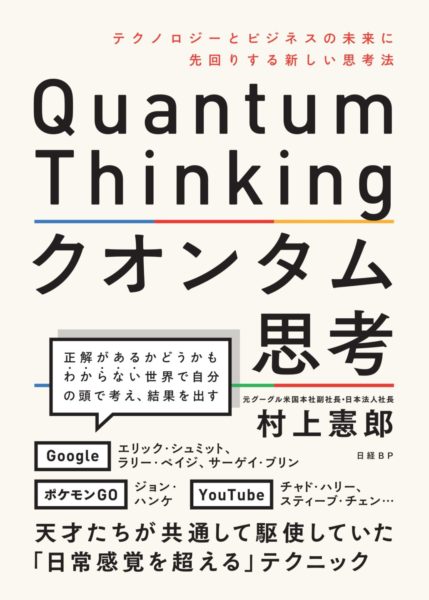量子コンピュータをめぐるプラトン主義
アインシュタインとボーア、ペンローズとホーキング
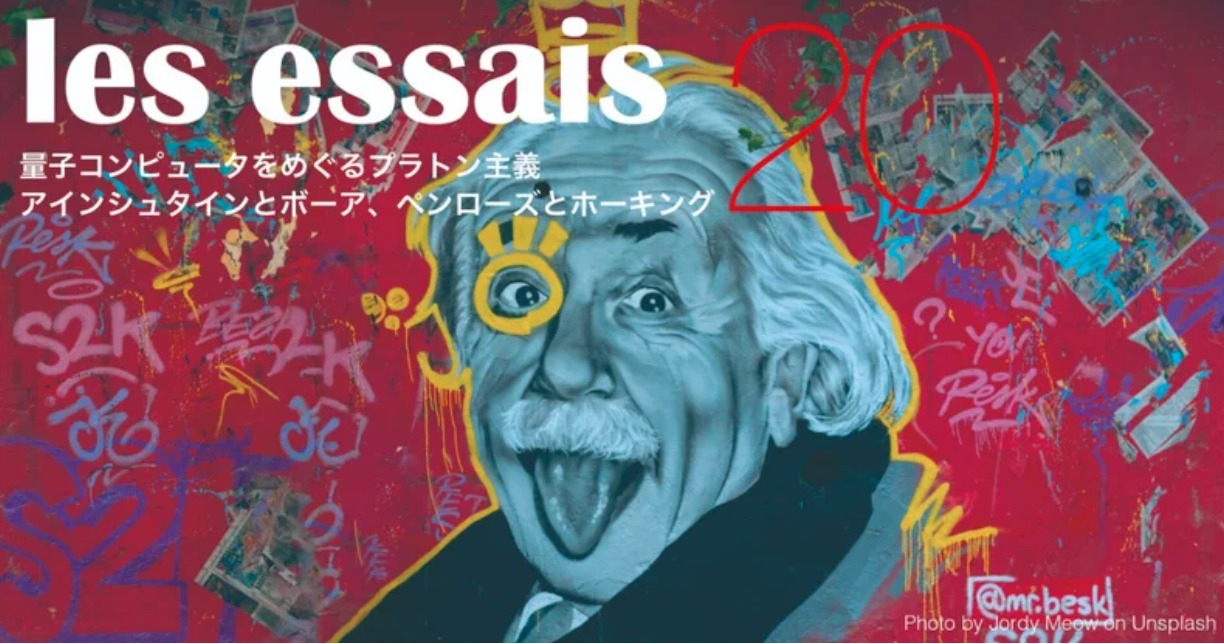
岸田内閣が先端テクノロジー分野を明確に国家戦略に位置づけると発表したのは3月のことである。「新しい資本主義実現会議」で策定されまとめられた実行計画には先端テクノロジーとして5つの分野を重点化している。そのなかで私の目を引いたのはAIと量子技術だった。
目次
量子力学の成立に潜む思想的な対立
「神」か「なんでもあり」か
歴史は「神」のものではない
知的な対立がもたらす多様な可能性
AIが意識をもつとき、合理性が人を支配する
量子力学の成立に潜む思想的な対立
前回の記事の最後で、ペンローズの量子脳について触れた。イギリスの数理物理学者であり科学哲学者でもあるロジャー・ペンローズは人間の意識、脳の働きとは量子力学の知見によっていずれ解き明かされる。物理学のロジックで人間の心を論じることができるようになると言う。人の脳の仕組み、意識や感情も未来には数式化できるということだ。
これに対し、ロジャー・ペンローズの盟友であったスティーヴン・ホーキングはペンローズのそれをプラトン主義と批判し、人間の脳は普遍的な方法で記述できないと反論する。ペンローズの考え方はイデア論に通じている。今はまだ解き明かされてはいないが、いずれ宇宙の全てを記述しうる唯一の普遍的統一法則が存在するとする思想だ。これに対しホーキングの思想は経験論あるいは実証主義に基づいている。
唯一無二の真実が司る世界と、多様に変化しうる経験が蓄積されていく世界。大きく2つの考え方で人間は世界を眺めてきた。それこそプラトンの時代から何千年も──たとえば私たちは演繹的ロジック、帰納的ロジックなしに事実を扱うこともできない。
2つの思想の差異は100年ほど前の物理学における歴史的大論争の各々の立場の違いにも表れていた。アルバート・アインシュタインとニールス・ボーアの両派に分かれた量子力学をめぐる論争である。この論争はホーキングとペンローズのそれに先行していた。
大論争では、世界は絶対的な因果律に支配されているとする決定論と、因果律などなく相対的で見方(観測、解釈)によって変化するものだという非決定論が鋭く対立した。有名なアインシュタインの「神はサイコロをふらない」という言葉は、因果律で語れない世界など受け付けないということである。これに対し、ニールス・ボーアは、原子を扱うミクロな世界は因果のみでは記述しきれないものであることを次々と示していった。
量子物理学の黎明期からこの論争は長く続いた。原子は波であるのか粒子であるのか。現象なのか物質なのか。そのどちらかであるとするアインシュタインと、そのどちらでもあり観測によって変化してしまうとするボーア。ミクロの世界を波動として記述しうるとエルヴィン・シュレーディンガーが方程式を発表しアインシュタイン側に与したのに対し、ヴェルナー・ハイゼンベルグは行列力学を提唱し不確定性原理を発表して、波動でもあり粒子でもある世界を説明する。
ボーアは、偉大な物理学者であり、光が波でも物質でもあること最初に理論立てたアインシュタインとの対立に苦悩したことは有名だ。そのことは量子物理学の解説によく取り上げられるエピソードだが、特に読み応えがあり、両派の対立をわかりやすく語っているのは『量子革命 アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の衝突』(マンジット・クマール著/青木薫訳/新潮文庫)だ。量子力学の誕生に携わった多くの天才たちの物語が、その立場や思想、理論を浮き彫りにしながら語られる。
「神」か「なんでもあり」か
アインシュタインが死ぬまで追求し続けたのが、自身がうち立てた一般相対性理論と量子物理学の統一であった。言ってみればそれは世界の真実を唯一の普遍として記述しようとする試みであり、統一理論と呼ばれ理論物理学の夢とされるものだ。統一論とはまさにプラトンのイデア論の子孫であり、人の知性は世界の真実をめぐって何度目かの周回にいる。
世界はたった一つの真実によって論じることができるという思想は、近代以降の歴史のなかで繰り返し批判を浴びてきた。たった一つの真実とは「神」と言い換えることもできるだろう。この論点についても語りうることは枚挙に暇がないほどだが、この記事では「神」は宗教である必要はないとだけ述べるに止めたい。
さて、このプラトン主義、イデア論に痛烈かつユニークに批判を加えたのは科学哲学者であるポール・ファイヤアーベントである。知的なアナキストであったファイヤアーベントは「なんでもあり(anything goes)」と嘯き、何ひとつ科学的に正しいなどと言えるものなどない、科学的理論は人間が勝手にでっち上げたものだと言い放つ。あまりに過激な言論のために、ファイヤアーベントは“科学の敵”とまで言われ、異なる理論を同じ基準で比較検討できないという「共約不可能性」を武器に、科学が最も正しく世界を記述しうるという傲慢さに真っ向からぶつかる。
世界はどこまでも相対的であり、科学的な合理性など人々に絶対を押し付けて洗脳し奴隷化してしまう。こうしたファイヤアーベントの論は私にとって大いに刺激になる。どことなく西洋的な価値であるイデア論に対しアジア的な相対論、仏教的な因縁論の擁護にさえ感じられるからである。だいたい、仏教思想はそもそもにして偉大なる相対論でありアナーキズムであり唯一神の否定であり……、このあたりも踏み込んで語るには紙幅も知識もないのでここまでにしよう。
このファイヤアーベントがプラトン主義を痛烈に批判しているのは『知についての三つの対話』(村上陽一郎訳/ちくま学芸文庫)のあとがきだ。引用しておこう。
プラトンは演劇を拒否し、それによって、われわれの文化をかくも長い期間にわたって支配してきた論理偏重への貢献を成し遂げた。
前回の記事で触れたようにこの世の出来事は洞窟の壁に映った幻影に過ぎないとするプラトンは、演劇など幻影の幻影であり最も不義なものとする。あらゆる芸術を同様に否定する。ファイヤアーベントは世界に対し、わたしたち人が持っている感情や心の動きを離れて論じることはできるはずもなく、従って情動を省いた科学的な真実などないと言う。そして、人の情動を取り込み、世界を記述する古代ギリシャの知的戦略だった演劇を拒否するプラトンをこそ批判するのだ。
このあとがきは非常に痛烈なので続けてもう一箇所だけ引用しておこう。
権威ある正統性(それを私はこけにする)、委託(専門家に判断を委ねてしまうこと=これを私は拒否する)、そして委託の底流にある術語の曖昧さと専門家の無知である。
歴史は「神」のものではない
ファイヤアーベントのプラトン批判の元祖は、ファイヤアーベントの師匠である哲学者、カール・ポパーである。その著作『開かれた社会とその敵 第1部: プラトンの呪文』(内田詔夫、小河原誠訳/未来社)で、そのままタイトルにあるようにプラトン主義を批判した。この第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に書かれた大著によって、ポパーはプラトン的な純粋性つまり統一されたイデアという世界観は、プラトンの政治哲学を通じて全体主義の温床になっていると断罪する。世界に唯一の真実という呪いは、私たち人間を容易に奴隷にしてしまうのだ。
ポパーは『歴史主義の貧困』(岩坂彰訳/日経BPクラシックスシリーズ)でも、歴史に法則がありそれが発展していくという考え方を貧困なもので、論理的に成立し得ないと徹底して批判する。歴史の法則とは、このレビューでも取り上げたヘーゲルの歴史哲学のような進化発展する歴史観、それを元にしたマルクスの唯物史観などが代表例であろう。
歴史の法則は、いずれ世界は進化の果てに唯一の理念(イデア)に到達するというものだ。ポパーはこれを受け付けない。科学的な方法によってあたかも絶対的な真実があるかのように人間社会を論じることへの強烈な違和感がもとになっている。
有名な「反証可能性」という方法を持って、反証し得ないものは科学理論とは言えないと論じたポパーは、絶対ではなく相対としての歴史を、私たちの世界を、論じる。
今では批判も多いものだが、ポパーの考え方は知性というものを捉える道具として非常に有用なものだと考えている。
知的な対立がもたらす多様な可能性
過去の歴史も、未来における発見に影響される。
こんなポパーの名言をエピグラフに置いているのは『ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い10分間の大激論の謎』(デヴィッド・エドモンズ、ジョン・エーディナウ著/二木麻里訳/ちくま学芸文庫)である。タイトルの通り、ポパーと天才(奇才というべきか?)言語学者であるルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの論争を素材に、二人の評伝を絡めながら、この時代の哲学の潮流を物語るノンフィクションである。
原題は「ウィトゲンシュタインの火かき棒」とある。物語は1946年ケンブリッジ大学のあるセミナールームで起きた二人の論争に端を発する。このとき、激昂したウィトゲンシュタインは暖炉にあった火かき棒を掴んでポパーに食ってかかった。そこはさるものポパーも怯むことなく「私を火かき棒で脅すな」と怒鳴り、ウィトゲンシュタインを退出させた。
どのような論点で議論となったのかは諸説あり、真相は推測するよりないのだが、激烈なポパーが反証不可能な言語哲学を提唱するウィトゲンシュタインを論難したことは想像に難くなく、ひときわ感情的で孤独を募らせていたウィトゲンシュタインが激昂したこともおそらく真実だろう。
この二人の10分間の論争の思想的な本質がいったいどこにあるのかは未だもってわからないのだが、天才同士の衝突は私たちに大きな示唆を与えるし、理論を相対化して眺め直すのにはもってこいかもしれない。
冒頭のアインシュタインとボーアの間の論争も、互いの主張のやり取りのなかに新しい物理学の本質を体感的に掴みうる。ことに物語として、互いの生い立ちを追った上で人物を理解して、論争を見直すこと、対立を思うことは何らかの知的な活動の助けになる。これこそ、ファイヤアーベントが古代ギリシャにおいて演劇が持っていた機能を指すものだろう。つまり人間の情動を、その対決を通して表現することこそ世界の記述の意味をなすものではないかということだ。
しかし、この知的な対立という考え方そのものはヘーゲルの弁証法のテーゼ→アンチテーゼ→ジンテーゼのように発展を望まれているようであるが、私自身は知的な対立は事物に対する解釈の多様性の素地として価値があると考えており、それ自体に発展を期待するわけではない。
かつて「朝まで生テレビ」のような討論番組を非難して、「反対だけで代案も結論もないからよくない」という人がいたが、討論に求められるべきは代案や結論ではない。議論の多様な可能性を開いていくことであるべきだ。

ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い一〇分間の大激論の謎
デヴィッド・エドモンズ 著 , ジョン・エーディナウ 著 , 二木 麻里 翻訳
ちくま学芸文庫
ISBN:978-4-480-09759-0
AIが意識をもつとき、合理性が人を支配する
量子力学に戻ろう。量子コンピュータはアニーリングという方式によって既に実用の域に達している。もちろん仮想的な量子世界の応用であるアニーリングよりも、より本質的に量子状態を電子計算にとりこむゲート式での実用には至ってはいないのだが。
今では、解釈と確率的な世界観である量子論は広く受け入れられ(しかし、理解されているとは言えない)、量子アルゴリズムが開発されコンピュータへと応用されようとしている。
波でもあり物質でもある性質が、0と1で世界を記述する古典コンピュータから0と1を重ね合わせ、莫大な同時進行状態をもたらして複雑で大量の計算を成し遂げてしまう量子コンピュータは世の中を一気に変えてしまうテクノロジーだ。だからこそ、岸田内閣も国を挙げて取り組もうとしているわけだ。
私は個人的には、量子的な方法によってAIが自己意識に近いものを持ちうる可能性について非常に興味を持っている。この辺りについては、Googleの元副社長である村上憲郎氏の『クオンタム思考 テクノロジーとビジネスの未来に先回りする新しい思考法』(日経BP)で、量子力学で「自己意識」は定義できるのかが論じられている。
このレビューでも何度か、AIが意識を持つこと、意識というものの定義をめぐってさまざまな考えを紹介してきたが、量子論と意識がつながっていくとすれば非常に面白く、またペンローズの量子脳の考え、その根底にあるイデア論との関係も見極めていきたい。なぜなら、意識を持つ人工的な知性が誕生した場合、それはファイヤアーベントやポパーが危惧したように人間を科学的合理性の奴隷にするものになるかもしれないからだ。
そういう時代はもしかすると私が生きているうちにやってくるのかもしれない。