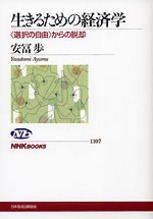街頭のAIカメラが迫る社会の成熟

JR東日本が駅構内に設置した防犯カメラの運用をめぐって議論がおきたのは先日のことだ。ニュースになるとJR東日本は即座に撤回して議論もしりすぼみした。これに限らず近年、街角に設置されるカメラの台数は増加している。果たしてそれは私たちに利益をもたらすのか、それとも害をもたらすのか。街頭のカメラは、わたしたちの足元を照らす灯りなのか、それとも私たちを区分けする見えない壁なのか。
目次
1 足元を照らす灯りと切り裂きジャック
JR東日本が駅構内に設置した「防犯カメラ」は顔認証AIを搭載しており、重大犯罪で服役した出所者や仮出所者を検知するために導入された。これをメディアがとりあげるところとなり、JR東日本は即座に「社会的合意が不足している」との意見を公表し、当初の方針を撤回した。このニュースについてSNSなどインターネット掲示板では “犯罪予備軍”に対する処置として理解を示す投稿が多く見受けられた。それだけでなく、駅構内は犯罪発生率も高く、犯罪者の検知に適した場所として積極的に導入を推す意見さえ目立っていた。
JR東日本が設置した数千台のカメラは「防犯カメラ」と呼ばれる。その目的も当然、公共安全である。しかし、カメラはカメラ。目的は扱う人間次第なのは言うまでもなく、他者を向けば「防犯」、自分を向けば「監視」といった違いしかない。
話は逸れるが、暗い夜道を照らしてくれる街灯にも「防犯灯」という呼び名があることをご存知だろうか。もちろん「防犯」といって即座に犯罪抑止だけを第一義としない。夜間、生活道路を(転倒しないで)安全に通行できることも目的だ。
遡れば街路灯の歴史は19世紀、ロンドンのガス灯に至る。その頃、ロンドンの人口は急激に増加。それにともなって犯罪も増加した。あの切り裂きジャックの時代である。街角の灯に防犯の意図があったことは想像に難くない。
GDPR(EU一般データ保護規則)以来、公共の場へのカメラ設置など個人情報の取得に敏感なヨーロッパで、街角に最もカメラが多い都市のひとつがロンドンというのも何か暗示めいたものを感じてしまう。
ところで、件の切り裂きジャック、現場の慰留物をDNA鑑定して真犯人を突き止めたとのニュースが流れたのは2019年のことである。法医学ジャーナル誌「JOURNAL of FORENSIC SCIENCES」2020年1月号に「Forensic Investigation of a Shawl Linked to the “Jack the Ripper” Murders」(Jari Louhelainen Ph.D., David Miller Ph.D.,)という記事が掲載された。殺害現場に残された被害者のショールから、ポーランド人理容師のDNAが検出された。夜の灯りを避けた娼婦たちを襲った悪魔が白日の元に晒されたというわけだ。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1556-4029.14038
2 フーコーが掘り起こした壁
カメラは暗い夜道を照らす灯りであり、同時に市民に安全をもたらす目的をもっていた。しかし、それをひとたび「監視カメラ」と呼べば不穏になる。
今回のJR東日本のカメラ導入の目的、そして、撤回後のネット上のコメントに表れていたのは、社会のなかに見えない壁を求める意識である。壁によって、一般市民と犯罪予備軍を隔てる。こうした隔離が、AIを搭載したカメラが映し出そうとしているもう一方のもの、つまり私たちのアイデンティティを維持しているといえば飛躍しすぎだろうか。隔離や区別が私たちのアイデンティティを担保すると言いたい訳だが──。
私はここで、「アイデンティティ」という音葉を「近代的自我」の意味で使っている。近代が確立した自我とはあらゆる差異のうえに成立している。「私は私である」という自己の同一は差異によって明確になる。同一性と差異こそが自他の区別をもたらす。
区別の探究という思考の戦略は古典主義時代に萌芽し、近代に入って科学を通じて分析というコンセプトを確立していった。ミシェル・フーコーは『言葉と物:人文科学の考古学』(渡辺一民、佐々木明訳/新潮社)でそう論じたはずだ。いまどき気の利いたビジネスマンなら口癖にすらなっている「パラダイム」(トーマス・クーン)という術語をさらに推し進めて、「エピステーメー」と名付けられた知的概念の地層を掘り起こした。
本稿のテーマにおいてフーコーの『狂気の歴史:古典主義時代における』(田村俶訳/新潮社)、そして『監獄の誕生:監視と処罰』(田村俶訳/新潮社)も重要となる。すべてを本稿に合わせて論じ直すには私は力不足であるから、直感めいて聞こえることを恐れず要点だけ述べたい。
フーコーが述べるには、17世紀、西欧では理性を探究するために狂気を排除しはじめた。それがやがて狂気の閉じ込め、つまり狂人、浮浪者、失業者、虚弱者、孤児といったアウトサイダーの監禁につながっていく。公共の安全のためである。彼らは壁のなかに監禁された。そうして近代、精神医学が生まれ病名を付与されて狂気はますます社会から隔離される。
私が現代において街頭のカメラを「壁」と述べたのはここで意味を為す。カメラとAIによって、私たちは犯罪予備軍と市民を隔離しようとしているわけだ。先に見たように、それに賛意を示す人々もすくなくない。
カメラを監視カメラとしたとき、フーコーはみたび、召喚される。「パノプティコン」である。功利主義を創始したジェレミー・ベンサムの考えた中央監視型の刑務所施設のあり方からヒントを得た、中央権力からの効率的監視と、常時、監視を意識することで規律化されていく個人を生む仕組みを言う。街頭のカメラが抑止力となるのは、この仕組みによってであり、見えない「壁」を社会に設けるのもこれによってである。
3 壁を求める意識、権威主義的パーソナリティ
犯罪抑止として公共の場へのカメラ設置に理解を示す声がすくなくないことは先に述べた。「監視カメラ」ではなく「防犯カメラ」として、一般人である自分と、アウトサイダーである犯罪予備軍を隔離するための壁を求めて──。
しかし、私たち一人ひとりがいつ壁の内側に閉じ込められる身になるかはわからない。昨今のコロナの狂騒で言えば、ワクチン未接種であるだけで壁のなかへ隔離される社会は目の前だ。前科や犯罪未遂は必要ない。
社会に設けられた見えない壁が高くなるごとに、さらに多くの私たちが監禁される側になる。大きな権力なら、この壁を高くすることはそれほど難しいことでもない。ナチスがユダヤ人を監禁したように、だ。ナチスの思想と、街頭のカメラやAIによる個人特定が孕む問題は案外と簡単に通底する。
さらに考えを進めてみる。監視とは、ただ不快で不安なものだけであろうか。壁は外に残る者には非常に居心地のよいものであるだけでなく、内側への想像を遮断しうる。想像の遮断は、むしろ心地よい。ある意味、選択肢を区切られて不自由なようでいて、不快でも不安でもない。自由を失うことは同時に責任を回避(転嫁)できることでもあるからだ。
SNS上に散見されたJR東日本駅構内に無数に設置されたカメラに賛成する意見のなかにも、そういう意識が潜在しているように感じられる。なぜならSNSそのものが、炎上というかたちでアウトサイダーを炙り出し狭いところへ監禁する機能をいつも充実させているからだ。そのユーザーたちが何か大きな機構や仕組みに守られ責任を回避したいと思うのは意外でもなんでもない。
こうした性格をドイツの心理学者、エーリッヒ・フロムは『自由からの逃走』(日高六郎訳/東京創元社)のなかで「権威主義的パーソナリティ」と呼んだ。強者や権威を無批判に受け入れ少数派を憎むパーソナリティが、ファシズムを受け入れナチスを支持した原因とした。
私たちのアイデンティティは、権力側に属しアウトサイダーを監禁(排除)するほうを指向する。デジタルアイデンティティも同様だろう。ネット上での活動はSNSの炎上のみならず、消費活動ですらレビューやレコメンドをもとに、何かに属し何かを排除することで強化されていくからだ。
断っておくが、私はいたずらに防犯カメラや個人情報取得への危機を煽り、恐れを抱く者ではない。むしろ危険性を見落とさず歴史に学べば、カメラは壁でなく灯りとなると信じている。
4 生きにくさの理由につながる意識
私たちの生きにくさは、何かの犠牲のうえにアイデンティティを確立しているためではないか。自由を確保するがためにかえって寄る辺のない不安を抱えているのではないか。私にそう教えてくれたのは、東京大学東洋文化研究所・安冨歩教授の『生きるための経済学 〈選択の自由〉からの脱却』(NHK出版)だ。
安冨はこの著作の冒頭で、経済学が物理法則に反したものであり、経済学を信じるには自己欺瞞に浸るしかないことを論じる。なぜなら、経済学(ことに古典経済学)でいう合理的経済人とは、ほとんどAIのごとく利益を最大化し損害を最小化する者たちだからだ。そんな者がいるはずがない。しかし、それを信じなければ経済学、もっと言えば資本主義は成り立たない。だからこそ、自己欺瞞が行われるのだ。敷衍して言えば、個々人が資本主義社会で幸せを感じるにはなんらか自己を欺瞞するしかない。私たちは日常に合理を求めるために、選択肢を見つけようとする。生活であれ、仕事であれ、どこにもかしこにも選択肢は溢れていて、正しく選ぶことをいつも自分に強いる。そして、この選択肢が豊かであるほど、日常が豊かになると思い込んでいる。
高度な資本主義社会に生きる私たちは選択肢という“資産”を蓄積することで、未来の自由を確保しようと励む。金銭は人類史上最大の交換材であるために無限の選択肢となる。資本主義社会では金銭さえあれば、ほとんどどんな選択もしえる(マイケル・ジャクソンは度重なる整形手術で人種さえ選択した)。
私たちは選択肢の蓄積を望む。だから選ばないことで選択肢が蓄積する。ちょうど、いつか読むだろうと積読されていく書籍がそれだけで未来の選択肢であるように、もっと素晴らしい人に出会うかもしれないと婚期を逸する恋人たちのように。そうして、いよいよ気づくのだ。選択の自由はまったく幸福ではないことに。
自由であることは不安をもたらす。だから、やがて潜在的に自由からの逃避を企みはじめる。そのようにして、自分とは違うというだけでアウトサイダーの監禁に賛成する。不自由であるがゆえにある種のアイデンティティが強化されていく。選べないことで自己の同一性を思い出すのだ。自由と不自由の往還によってアイデンティティがきりきりと私たちを締めあげている。他人の不自由によって自らの自由を確保したようで、かえって不自由になっているという往還。とかく私たちは生きにくい。
私たちは社会に見えない壁を求めるのではなく、灯りを求めているはずだ。街頭のカメラを壁にするもの灯りにするのも、人間社会の成熟以外ない。問われているのは、私たち一人ひとりなのだ。
5 一つの危機
最後にもう一度、エーリッヒ・フロムに戻ろう。長くなるが、『自由からの逃走』から引用して本稿を終わりにする。文中にある「積極的な自由」については、アイザィア・バーリンとの議論もあることも付記しておく。
近代人は伝統的な権威から解放されて「個人」となったが、しかし同時に、彼は孤独な無力なものになり、自分自身や他人から引きはなされた、外圧的な目的の道具となったということ、さらにこの状態は、かれの自我を根底から危うくし、かれを弱め、おびやかし、かれに新しい束縛へすすんで服従するようにするということである。それに対し積極的な自由は、能動的自発的に生きる能力をふくめて、個人の諸能力の十分な実現と一致する。自由はそれ自身のダイナミックな運動法則にしたがい、自由の反対物に転換しようとする一つの危機に到達した。