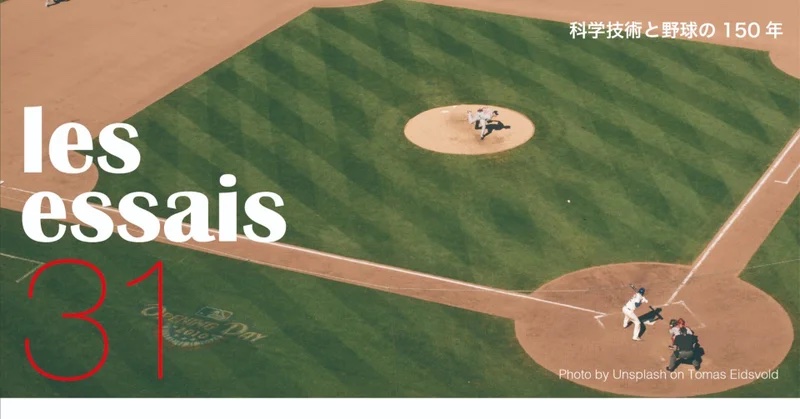行動経済学と機械学習で、人の「ココロ」がわかる?
――京都大学大学院経済学研究科教授 依田高典氏に聞く(1)

バイアスとナッジの行動経済学ブームと第 3 次 AI ブーム。ともに統計学を出自とする経済学とデータサイエンスが融合して、その行動の解析を通して人間観を問い直そうとしている。ミクロ経済学・マクロ経済学・計量経済学からなる主流派経済学に加え、行動経済学・実験経済学・ビッグデータ経済学の 3 本柱からなる「エビデンス経済学」を提唱する依田高典氏に話を聞いた。ときに非合理な人間の「ココロ」をとりもどす経済学の先にあるものとは。
取材:2023年1月26日 オンラインにて
 |
依田 高典(いだ たかのり) 京都大学大学院経済学研究科研究科長・教授 1965 年新潟県生まれ。1989 年京都大学経済学部卒、1995 年京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。現在、京都大学大学院経済学研究科教授。同研究科長(2021 〜 2023 年度)。その間、イリノイ大学、ケンブリッジ大学、カリフォルニア大学客員研究員を歴任。専門は応用経済学。情報通信経済学、行動経済学の研究を経て、現在はフィールド実験とビッグデータ経済学の融合に取り組む。主な著書に『Broadband Economics: Lessons from Japan』(Routledge)、『スマートグリッド・エコノミクス』(有斐閣、共著)、『ブロードバンド・エコノミクス』(日本経済新聞出版社)、『行動経済学』(中公新書)、『「ココロ」の経済学』(ちくま新書)などがある。日本学術振興会賞、日本行動経済学会ヤフー論文賞、日本応用経済学会学会賞、大川財団出版賞、ドコモモバイルサイエンス奨励賞などを受賞。 |
目次
ビッグデータ時代に誕生した、新しい行動経済学の時代
都築正明(以下、――)現在、行動経済学やナッジの概念が注目されています。先生にはまず、行動経済学の発生と経緯について伺いたいと思います。
依田高典氏(以下、依田) 行動経済学は、経済学で仮定されていた、自己の利益を最大化させる合理的な経済人=ホモエコノミカスという人間観を疑いました。1978 年にノーベル経済学賞を受賞したハーバート・サイモン*1は、生身の人間が完全に合理的であることはない、という限定合理性を唱えるとともに、熟考を伴わないヒューリスティックスという非合理な行動があることを示して、伝統的経済学を批判しました。その後、心理学者であったダニエル・カーネマン*2とエイモス・トヴァルスキー*3が共同で、人間がときに非合理な意思決定をすることを説明したプロスペクト理論や、その際にはたらくバイアスを提示しました。トヴァルスキーは若くして亡くなってしまうのですが、カーネマンは 2002 年に心理学者としてはじめてノーベル経済学賞を受賞しました。カーネマンの後継者――「追っかけ」であったというほうが近いのですが――であったリチャード・セイラー*4は、人間の行動変容を促すナッジ(Nudge)を示し、2017 年にノーベル経済学賞を受賞しました。最初は異端としてみられていた行動経済学も、このあたりから主流経済学の流れに汲み入れられていくことになります。
*1ハーバート・サイモン(1916-2001)政治学に始まり心理学、コンピュータサイエンス、組織論、経営学にも深く通じていた。AI 研究にも多大な影響を残している。1978年にノーベル経済学賞を受賞。
*2ダニエル・カーネマン(1934-)イスラエル生まれの認知心理学者・行動経済学者。不確実な状況下における意思決定モデル「プロスペクト理論」を経済学に統合した。2002年にノーベル経済学賞を受賞。
*3エイモス・トヴァルスキー(1937-1996)イスラエル出身の心理学者。カーネマンとの共同研究を通じて行動経済学の基礎を打ち立てた。
*4リチャード・セイラー(1945-)アメリカの経済学者。行動科学と経済学の理論家として知られる。法学者キャス・サンスティーンとともに「ナッジ」の概念を広めた。2017年にノーベル経済学賞を受賞。
――ここまでが、現在の行動経済学ブームでいわれていることですね。これを「古い行動経済学」とすると、その先にはどのような進展があったのでしょう。
依田 次に、フィールド実験という学問分野で、行動経済学者がノーベル経済学賞を受けることになりました。コントロールグループとトリートメントグループを設定して、RCT(Randamized Controlled Trial:無作為比較対象法)によって因果関係を識別する、というものです。医薬の臨床実験では対照群と治療群とをわけて、対照群にはプラセボを、治療群には治療薬を投与して効果を判断しますが、同じことを社会実験としても行えることを示したのです。2019 年には開発経済学においてフィールド実験、RCT ランダム化の社会実験を行った MIT のグループにノーベル経済学賞が授与され、 2021年には自然実験において原因と結果とを統計学的に正しく識別できることを理論的に証明したグループに授与されています。流れとしては、行動経済学が第 1 の革命、この因果推論が第 2 の革命となっています。いままでの経済学は非常に抽象的な学問で、 実験できるデータが非常に限られているために、数学的に証明することで「わかったつもり」になる学問だったんです。
――「微分積分」の「積分」の間にレ点をふって「微(かす)かに分かって・分かった積もりになる」と陰口を言う学者もいました。
依田 それが、いまはビッグデータの時代になり、IoTで、人間の行動履歴に関わるデータが、スマートフォンやスマートメーターなどのスマートデバイスを経由して、どんどんサーバやクラウド側に蓄積されるようになってきています。その結果、私たち研究者や GAFAMのようなビジネス側が、私たちの毎日の行動を、非常に高頻度なビッグスケールのデータとして使えるようになってきました。ここで、行動経済学と因果推論の融合が起こります。
――実データを分析して、私たちの行動そのものを分析できるようになるわけですね。
依田 カーネマンやセイラーの時代の行動経済学は、ある意味ではわがままな経済学でした。きちんとしたエビデンスはないけれど、人間というのはだいたいこういうものです、と示すに留まっていました。
――研究室の学生にアンケートをとったらバイアスがみられた、統計学の学生でも同じバイアスがみられた……という質問紙形式ですね。
依田 はい。大学生 100 人に聞きました、という程度のレベルのエビデンスで人間のバイアスというものを特定したつもりになっていました。この時点でノーベル賞を受賞した人たちのいうバイアスには、エビデンスが弱く再現性が取れないものもあります。それは、実験のやり方、さらにいえば因果推論の識別が甘かったからです。 しかし、いまビッグデータの時代になって、因果推論が可能になってきていますから、きちんとした行動変容の仮説検証ができるようになってきました。
――よりリアリティのある学問になってきた、ということですね。
依田 20 世紀の経済学は、データが不足していてエビデンスがないにもかかわらず、数学的な証明を用いることで科学としての意匠をまとっていた、といえるかもしれません。21 世紀には十分なデータが採れるようになり、データに基づいて実験的な手法に基づいて因果推論を行うことが可能な学問として、経済学が生まれ変わりました。行動経済学と因果推論が融合して、実証的な行動科学というのが完成した。これが、21世紀の新しい科学的・実証的なエビデンスの学問としての経済学の姿になっています。 近年ノーベル経済学賞が頻出される分野になってきているのも、その現れでしょう。
バージョンアップした経済学で「原因と結果」を導き出す
――これからの経済学は、どのように変わっていくとお考えですか。
依田 機械学習――広い意味で人工知能ですが――が非常に発展してきていて、 第 3 次人工知能ブームのなかにあります。ここには 2 つの潮流があって、 1 つは言うまでもなく、2012 年に大ブームとなったディープラーニングです。基礎研究は日本でも以前からありましたし、ヒントン*5の発明もありましたが、 それが画像認識や音声認識で大きなブレイクスルーを果たしたのは間違いありません。 ただ、ディープラーニングは、経済学の分野で、今ひとつ役に立たないこともわかってきました。
*5ヒントン ジェフリー・ヒントン(1947-)イギリス生まれのコンピュータ科学の研究者。2012年の画像認識コンペティション(ILSVRC)においてディープラーニングの手法を用いたモデル「AlexNet」を使い、画像誤認識率16.4%という圧倒的な結果を出し優勝。トロント大学とグーグルに籍をおく。
――それは、どうしてでしょう。
依田 ディープラーニングが役に立つのは、画像や音声のようなリッチなデータや稠密なデータです。ところが経済学で使うデータというのは、所得や年収、金利といった、数字に置き換えられた非常にスパース、つまりまばらなデータになっているのです。そうしたデータをディープラーニングやニューラルネットワークを用いて畳み込んでも、普通の回帰分析で得られるものと、さほど変わらないのです。
――イメージとしてはわかります。では、既存の経済学のほかに機械学習が役立つ分野はあるのでしょうか。
依田 先ほど述べた因果推論の分野です。きちんと統制されたデータのなかで「原因と結果」の形式をたくさん見つける、因果推論的な機械学習が注目を浴びています。多次元のデータから因果関係を見つけようとする際には、古典的な機械学習のアルゴリズムがかなり役立ちます。機械学習のアルゴリズムでは、説明変数を選択したり、 母数の線形性やパラメトリック(分布)を仮定したりする必要がなく、大量の説明変数を同時に投入して、一気に推定することができます。これは従来の統計学、経済学を大きく補完するものです。
――異質なものを介入した効果を測定しやすくなる、ということですね。
依田 そうなんです。その延長として出てくるのが、ポリシーターゲティングという流れです。ターゲティングという言葉は「ターゲティング広告」のように、対象を絞ることとして使われますよね。こうした 一人ひとりにどんな介入をすれば最も効果があるのか、という異質介入効果の識別に、機械学習的なアルゴリズムが役に立つことがかなりわかってきました。次の 10 年から 20 年以内には、ほぼ確実にこの分野にノーベル経済学賞が授与されることになると思います。
――ミクロ経済学はまず、合理的個人を仮定しました。しかし、個人の原理だけでは解決できないこともあるので、そうしたことを国家単位で説明するマクロ経済学が登場しました。意思決定を考える行動経済学では、再び個人単位で物事を考えるようになっている、という理解でよいのですか。
依田 そうですね。そして残念なことに、マクロ経済学の存在意義が問われているのです。
――どのような点においてでしょう。
依田 人間についてのデータがフィールド実験を通じて仮説検定ができるというのは、物理学で素粒子革命が起こったようなものです。原子のなかを解明するように、RCT(Randomized Controlled Trialrct:ランダム化試験)を通じて因果性を検証することができるわけです。そういう意味では、マクロ経済学で扱う事象――アベノミクスや黒田バズーカなど――について実験をすることはできないので、結局のところ水掛け論になってしまいます。たとえば、政府支出を増やせば定義的に経済成長になる、というような議論が盛んに行われていますが、賛成するにしても反対するにしても、 あくまで定義式的な問題で「こっちを増やせば、こっちがこうなる」なんてわからないわけです。 因果的な識別関係で、政府支出がどのようなかたちで国民所得に影響を及ぼすか、というのを RCT 的な実験で介入法効果として識別することは、現状においてはまだできていません。これは宇宙物理学において、実験的な手法が取れないために観測データのみで最先端の研究をするのと似ています。その意味において、現在のマクロ経済学は、実証革命がいまだ及んでいないという難しい立場にあります。
――推論と聞くと第 3次人工知能ブーム以前のアルゴリズムである、探索木のようなものをイメージするのですが。
依田 慧眼ですね。たしかに具体的なアルゴリズムの種類区分でみると、ディープラーニングと因果推論はまったく別の起源を持ちます。ただし、ディープラーニング系の第 3 次人工知能ブームを、因果推論系の、いわば第 3.5 次人工知能ブームが継承しているのは間違いありません。デジタル化や IoT で、個々のデータがクラウドに集まってくるようになった 2000 年前後からの趨勢にあるという意味では、同じ潮流にあるものだと捉えられます。実際に、共通のデータを使うことも多いですから。
フィールド実験の段階的発展
――フィールド実験も段階的な発展を経てきたのでしょうか。
依田 フィールド実験にも 3 次の段階がありました。第 1 次は近代統計学の誕生当初です。 統計学にはフィッシャー、ネイマン、ピアソン*6という 3 人の有名な祖がいますが、そのうちのフィッシャーがランダム化を用いて因果性を識別できることを、最初に提唱しました。フィールド実験というのは、そのときからはじまっていることになります。第 2 次ブームは1960 年代で、アメリカとイギリスで多くの社会実験が行われました。ケネディ-ジョンソンの時代です。しかし、これはコストの問題から長続きしませんでした。 医療費を何パーセント程度、徴収すれば医療制度を最も効率的に運用できるかというような社会実験をしたのですが、なんせアナログの時代ですから、実験の運用コストがかさんでしまったのです。現在なら 1 億円でできた実験が当時は 10 億円、100 億円とかかったので長続きしませんでした。そして 1990 年代にまたフィールド実験が使われるようになりました。はじめに使われたのは開発経済学の分野で、発展途上国の貧困問題に対する実験です。その理由はやはり、コストが安くすんだからです。2000 年代に IT のビッグデータブームが訪れて、IoT を通じてデータを自動的に収集できるようになりました。データを低コストかつ高頻度に取得できるようになったというのが、重要なポイントです。
*6フィッシャー、ネイマン、ピアソン 20世紀において現在に通ずる統計学の基礎を確立した統計学者であるロナルド・フィッシャー(1890-1962)、イェジ・ネイマン(1894-1981)、カール・ピアソン(1857-1936)。
――先生が東日本大震災後の 2012 年に行われた電力量を抑制する実験は、データ取得という側面からも機が熟していたわけですね。
依田 2000 年代、特に 2010 年以降には、非常に実験しやすくなってきました。多くの人がインターネットに繋げるようになった 1995 年前後を Web 1.0 とすると、IoT やクラウド、また2008 年に Apple の iPhone 発売を嚆矢とするスマートフォンの普及を背景にスマートデバイスを通じて自動的にビッグデータが集まっているのが Web2.0の世界ですね。Web 2.0 の環境が第 3 次人工知能ブームを支え、この第 3 次フィールド実験も実施しやすい状況にあります。さきほどマクロ経済の話が出ましたが、人間の行動のデータが採れるからマクロ経済の世界でこれができるかというと「アベノミクスの3本の矢がどのぐらい効果があったのか」「日銀がゼロ金利を解除することで、どうなるか」ということを実験することはではできないので、やはり水掛け論にしかなりません。
――あくまで思考実験としてお伺いするのですが、同じ手法をマクロ経済の政策評価に使ったとすると、どうなるでしょう。
依田 たとえば金利の上昇がどういう影響を及ぼすかを調べたいのであれば、日本を 2 つに分けて、10 年ものの国債金利を上げる集団と、上げない集団とに分けて実験することが必要です。そしてミクロの積み上げとして仮説検証を行い、物価がどの程度上昇するか、また国債価格がどの程度下がるかなどを検証することになります。つまりマクロの問題を、我々が観察できるようなミクロの単位に落とし込んで、因果推論をすることは不可能ではありません。
――ただ、それをマクロ経済学と呼べるかというと……。
依田 マクロ経済学をミクロな現象に還元しただけであって、マクロな事象をマクロ経済学の独自の方法論で分析できたわけではありません。
――ミクロ経済学が生のデータを使い、科学的に因果関係を導くことができるようになると、マクロ経済学の虚構性が際立ってしまう。
依田 そうですね。一般的なレベルでは、因果推論的という意味においては、科学的に原因と結果の識別ができるけど、マクロは取り残されてしまって、マクロ独自の科学とはなにか、ということが問われてきています。最近でいうと、ネット番組などで成田悠輔さんが経済評論家とマクロ分野について論争する場面がよくみられますが、一般の視聴者からは経済学者の言うことと経済評論家の言うことの区別がつけづらくなっています。
――そもそも成田悠輔さんは、依田先生と同雑誌に論文が併載されるような、行動経済学がご専門ですよね。
依田 おっしゃるとおり、成田先生自身は、機械学習や因果推論における世界的な研究者ですし、最も優れた頭脳を持つ方ですが、マクロ経済に詳しいわけではありません。