情報の非対称性と終末論のなかで社会的ケアを模索する
第5回 “影の自分”との対話――データ・ダブルとしての私
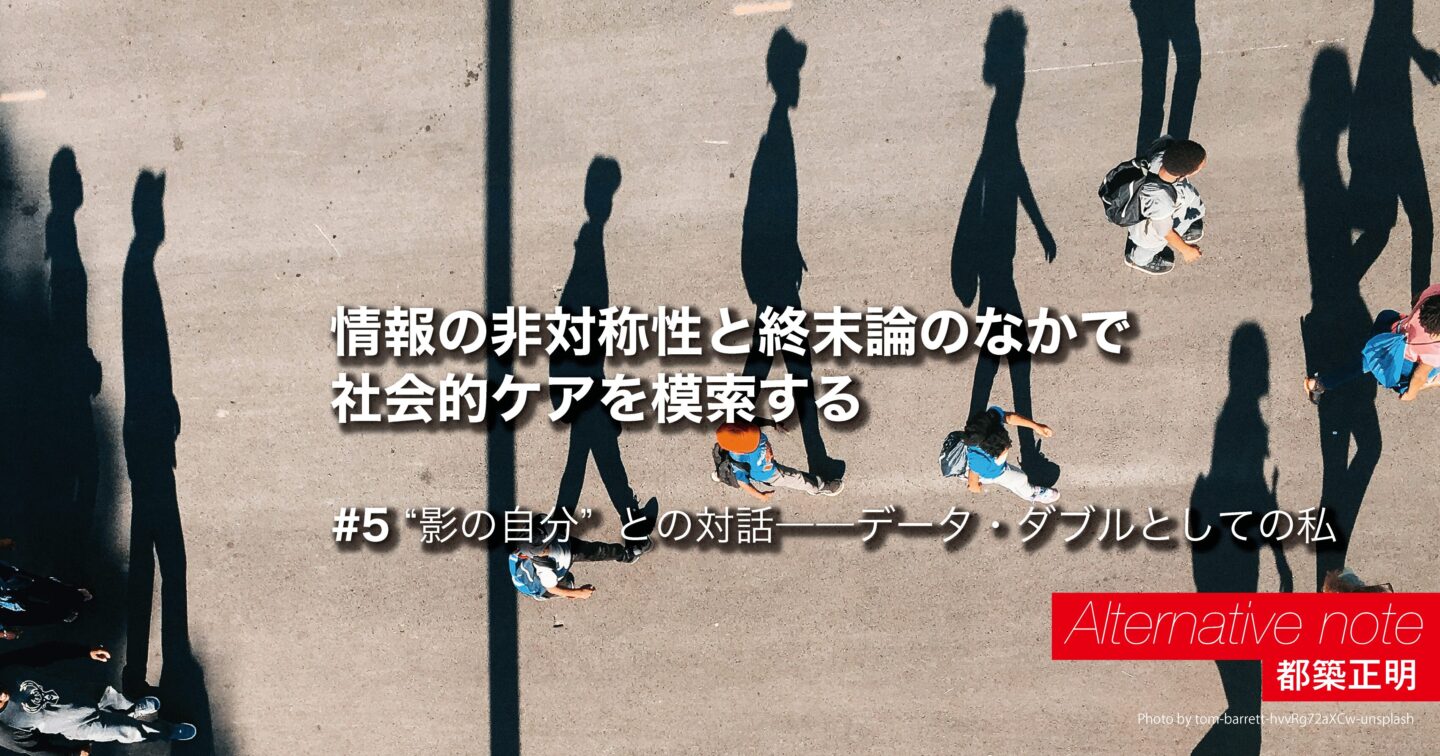
データ世界に生まれる“影の自分”への誤認とその拡散は、社会的ケアと政治の欠如が生む認識の真空に根ざしている。ナオミ・クラインは分断を超える鍵を、影を排除するのではなく理解する姿勢に見いだす。ボリス・グロイスが示すように、私たちは分断された複数の自己の声を聞きながらセルフケアを行うことで、社会的ケアの再構築を試みることができるのではないか。
目次
ふたりのナオミ
ナオミ・クラインは2023年刊行の著書『Doppelganger: A Trip into the Mirror World』(未邦訳/Farrar, Straus and Giroux)において、ネット空間において人々が陰謀論に惹きつけられる理由と、その誘引となる公共的ケアの欠如について論じている。
同書は、ナオミ・クライン自身がSNS上でナオミ・ウルフという人物と誤認され、執拗にバッシングされた経験を端緒としている。ナオミ・ウルフはベティ・フリーダンが『女らしさの神話』(荻野美穂訳/岩波文庫)で記したよう“女性らしさ”から解放された女性たちが、メディアや広告からの“美しさ”に苦しめられることを論じた『美の陰謀:女たちの見えない敵』(曽田和子訳/TBSブリタニカ)などの著書が世界的な反響を呼ぶなどして、1990年代の第3波フェミニズムの中心的人物とされた実在の人物である。ウルフはその後、コロナ対策はファシズムでありワクチンは大量死を目したものであるというような陰謀論へと傾倒していき、Twitter(現X)のアカウントが誤情報拡散で凍結される(のちに解除)ようにもなる。
クラインはこの体験をきっかけに、ネット空間という鏡像に映し出される“影の自分=ドッペルゲンガー”が意図せず独立して人々に認識されるだけでなく、当人の言動にまで侵食していく現象として考察していく。ソーシャルメディアにおいては、文脈を欠いた情報が大量に流出するなかで、発言や属性、アイデンティティが容易に取り違えられる。ウルフの場合は、コロナ禍以降のネット空間が公衆衛生の専門的世界と、不安・孤立・怒りを軸にした陰謀論の代替世界(Mirror World)との2つの分断した世界をつくり出し、ウルフは後者の世界でヒーロー視されることで、かつての左派フェミニストとしての信用が右派的ストーリーのなかに再利用されていった。この分断の原因となっているのは、「誤った信念」に還元せず、むしろ新自由主義的政策や社会的ケアの欠如が生み出した“認識の真空”に求める点にある。クラインは、影の自分を否定するのではなく、なぜそれが生まれるのかという条件を理解し、他者の不安に向き合うことこそが分断を超えるための第一歩であると説く。また同書では、フェイクの拡散は個人の愚かさではなく、社会的ケアの欠如や政治の不在、公共圏の弱体化により“認識の真空化”がもたらしたものであると分析されている。陰謀論は、孤独――貧困や社会政策の研究で知られる社会学者ピーター・タウンゼントのいう相対的剥奪感――のもとで、合理性ではなく帰属や物語性・感情的充足を求めるなかで“感情の政治(affective politics)”として機能するということだ。
複数の自己との対話とセルフケア
クラインは『Doppelganger: A Trip into the Mirror World』において“影の自分=ドッペルゲンガー”を排除すれば分断が深まるとして、ドッペルゲンガーが生まれた社会的条件を理解する姿勢を提示している。これはSNSが感情のUXを提供して怒りや恐怖といった負の情動をブーストする装置となりがちな現在、私たちがわきまえるべき倫理でもあろう。他者を嗤い“Wokeness”を冷笑するスタンスは、個人の自尊心を一時的に充足させるかもしれない。しかしその蠱惑に抗することでしか、正義や社会的ケアの再構築は不可能である。
正義については、本連載「出生と生産性をめぐるアポリア」においてジョン・ロールズやマイケル・サンデルの論を紹介してきた。またケアについては清水知子氏へのインタビューにおいて複数の角度からお話しいただいた。とても語り尽くせる内容ではないため、本稿ではアルバート・ハーシュマンが著書『離脱・発言・忠誠:企業・組織・国家における衰退への反応 』(矢野 修一訳/ミネルヴァ書房) において提示した「エグジット(Exit:離脱)」と「ヴォイス(Voice:声)」の概念を記すに留めたい。「エグジット」は、不満のある組織・関係から離脱するという選択だ。ハーシュマンは、市場メカニズムや競争が強い場では「エグジット」が起こりやすいとして、離脱が容易な組織ほど内部改善が進みづらいという側面を指摘している。附言すれば“No Voice, Free Exit”は、右派リバタリアニズムから派生した加速主義と新反動主義を提唱し、オルト・ライトに思想的根拠を与えたとされるニック・ランドが『暗黒の啓蒙書』(五井健太郎訳/講談社)において繰り返すスローガンである。「ヴォイス」は不満や要望を内部から表明し、改善を求める行動で、民主主義的参加の基礎であり、内部を変えようとするコミットメントを示す姿勢である。清水知子氏のインタビューでも言及される美術批評家ボリス・グロイスは、著書『ケアの哲学』(河村彩訳/人文書院)において、現代に生きる私たちが物理的身体だけではなく、データの集合として自己を形成する象徴的身体を所有していることを指摘する。そのうえでグロイスは、さまざまな専門知のなかから私たちが無知の主体として身体についての判断と選択を行うことで、フーコーのいう“生-政治”に抵抗するセルフケアの力を獲得する可能性を示す。多数の声を聞くこと――それは同時に、幾多のデータにより分断された自分自身の声を聞くことにほかならない。声については、稿を改めてまた考察したい。<了>




