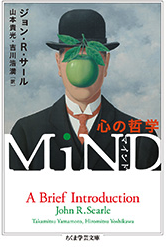信用をめぐるテクノロジー2:リンゴと暗号、認証と素数

前回は、テクノロジーはどのように信用を形にしてきたかを考えた。個人の信用についてふれてみたいと締めた。今回は、その続きを考えてみよう。個人の信用、個人を個人として証明するものについてだ。
目次
1 チューリングの悲劇とアップルのロゴマーク
2 チューリングテストと「中国語の部屋」
3 素数の美しさが暗号化のテクノロジーに寄与している
4 認証テクノロジーが拓く新たな経済システムの可能性
いきなり余談めくが、アップル社のあの有名なロゴマークのことはご存知だろう。あの齧られたリンゴの意味について、公式にはニュートンが万有引力を発見した故事にちなみ、齧った跡はデジタルな容量を示す単位(byte)と齧る(bite)をかけたものとされている。
30年以上前、大学受験に小論文が取り入れられた時期、京大入試の出題は齧られた林檎の写真について論じさせるものだった。もちろんアップル社など日本ではまだ知られていなかった当時、受験生の多くが歯茎の健康をケアする歯磨き粉をテーマにした(「リンゴをかじると血が出ませんか?」というCMが流行っていたのだ)。これでは点数は稼げないのはいうまでもない。模範解答はイヴが蛇に唆され齧る禁断の果実を述べたものだった。いま、同じ出題がされたらおそらくアップル社のロゴについての解答が大半を占めるだろう。
齧られたリンゴのマークでちょっと変わった解釈を聞いたことがある。それはコンピュータの父と呼ばれるアラン・チューリングの自殺にまつわるものだ。ナチスの暗号機エニグマを解読した、この天才は同性愛者だった。同性愛はその昔、イギリスでは犯罪だった。あることをきっかけに露見。やむことのない中傷にさらされ、チューリングは自殺する。その方法が青酸カリを塗ったリンゴを齧るというものだった。アップル社のマークのようなリンゴがチューリングの遺体のそばに発見されている。チューリングが生み出したコンピュータをアップル社が人々のものにしたのだ。
チューリングの悲劇はサイモン・シンの『暗号解読』上・下(新潮文庫)という名著で詳しく知ることができる。
機械(コンピュータ)がどれほど人間に近いかを判定する方法に「チューリングテスト」という考え方がある。アラン・チューリングが考えたのはいうまでもない。AIが進化した現在、よく耳にするようになったから知っている人も多いだろう。ごく簡単にいえば、人が隔たられた場所で機械と会話し相手が機械と気づかなければ、この機械はチューリングテストに合格、「人間的である」という考えだ。機械(コンピュータ)は人間になりすますことはできるのかと問われている。
チューリングテストに対し哲学者のジョン・サールが提案したのが「中国語の部屋」という思考実験だ。小さな穴が開いた部屋のなかに英語しか理解しないイギリス人を入れる。その部屋にはマニュアルが1冊だけある。マニュアルには小さな穴から入れられた紙に対する返答ルールがある。紙には部屋のなかの人には理解できない中国語が書かれている。人は紙に書かれた中国語への返答となる中国語をマニュアルから書き写す。部屋の外にいると、部屋のなかの人は中国語でのコミュニケーションが成立しているように見える。
つまりチューリングテストを受ける機械はたとえ人と対話しているようにみえたとしても、あるルールに従ってプログラム動かしているだけという可能性が消えず、サールが考えた部屋のなかのイギリス人と同じではないかというわけだ。
サールの思想については『MiND』(ちくま学芸文庫/ジョン・R. サール著、山本貴光訳、吉川浩満訳)を入門書としてお勧めしておく。
というわけで、機械が人間のように振る舞うことはかように困難な問題である。これは人間というもの実存への理解の難しさそのものと地続きであり、人が人であるという証明もまた非常に難しいものだ。個人を証明することも決して簡単なことではない。
個人の証明が簡単ではないと言ったが、ふだん私たちはそれをあらゆる場面で求められている。銀行や役所といった公的な機関だけでなく、スマホも動画配信もそれなしにはサービスを受けることができない。認証だ。
認証には大きく3つの種類がある。IDとパスワードを利用する「知識認証」、マイナンバーカードなどを使う「所有物認証」、そして指紋や虹彩といった身体の一部を判定する「生体認証」である。これらを見ると一目瞭然なのは、私たちがふだん触れている認証のほとんどがデジタル化されていることだ。認証はデジタルなテクノロジーによって行われている。
認証テクノロジーに欠かせないのが素数といったらどう思われるだろうか。
素数とは1とその数字以外では割り切れない数字だ。認証に欠かせないのがセキュリティであり、セキュリティに必須な暗号化のテクノロジーに素数が関係する。素数の性質が暗号を生成するのに役立つのだ。
さて、私のような文系には理解しがたいことだが、世の中には素数に魅せられた人が存在する。素数を美しいという。素数の美しさが暗号化のテクノロジーに寄与している。
脳神経医オリバー・サックスは『妻を帽子とまちがえた男』 (高見幸郎訳、金沢泰子訳/ハヤカワ・ノンフィクション文庫)で、自閉症の双子が行う素数での会話を紹介している。著者のサックスはその会話(暗号)を解読して、会話に参加してみせる。
認証テクノロジーのなかでも大きな注目を浴びるのが顔認証である。ここ十数年のAIの長足の進化がもたらした画像認識よって、続々と実用化が進んでいる。スマホも顔で解錠できるのはもはや当たり前だ。
生体認証のなかでも、カメラ付きデバイスであれば簡便に実装しうる顔認証は、特殊な機器を必要とする他の生体認証に先んじているといっていいだろう。特殊な機器が不要であれば、さまざまなコストを抑えられるのはいうまでもない。
顔認証は貧困層に対する少額融資などを行う金融サービスである「マイクロファイナンス」に対しても可能性をもつ。貧困層を対象にした低金利の無担保融資を行うグラミン銀行を創設したムハマド・ユヌスの『ソーシャル・ビジネス革命―世界の課題を解決する新たな経済システム』(岡田昌治監修、千葉敏生訳/早川書房)では、従来の金融機関では個人の信用を得られず高金利の資金に手を出し貧困から抜け出せなくなる人々の実情が述べられている。こうした貧困層の人たちは住所さえ明確でないために正規にお金を借りられないのだ。個人が個人であることを公的に証明する何ものも持たないがために口座をひらけない。
顔認証であれば個人を個人として記録し証明することは比較的安価で容易だ。すでに商用が進んでいるスコアリング・サービスと合わされば、個人の信用度を向上させることも難しくはない。信用スコアを電子マネーのように流通できれば、そのときには金融期間も通貨も不要になる可能性さえある。この個人への信用とは、かつての共同体にあった贈与と返礼の関係に近いものだ。個人の人間性が個人の信用を担保するからだ。
この関係がテクノロジーによって共同体という狭い社会だけではなく、世界中どこでも可能になる。
夢のような話かもしれない。しかし、理論と技術は揃っている。
顔認証が目指す方向にはこんな社会があると願っている。
現在の貨幣経済の進んだ先にはこんな信用経済があると信じている。