複雑な世界を複雑なまま生きる──PLURALITYとなめらかな社会
第2回 政治のアマチュアとプロに違いはあるか?
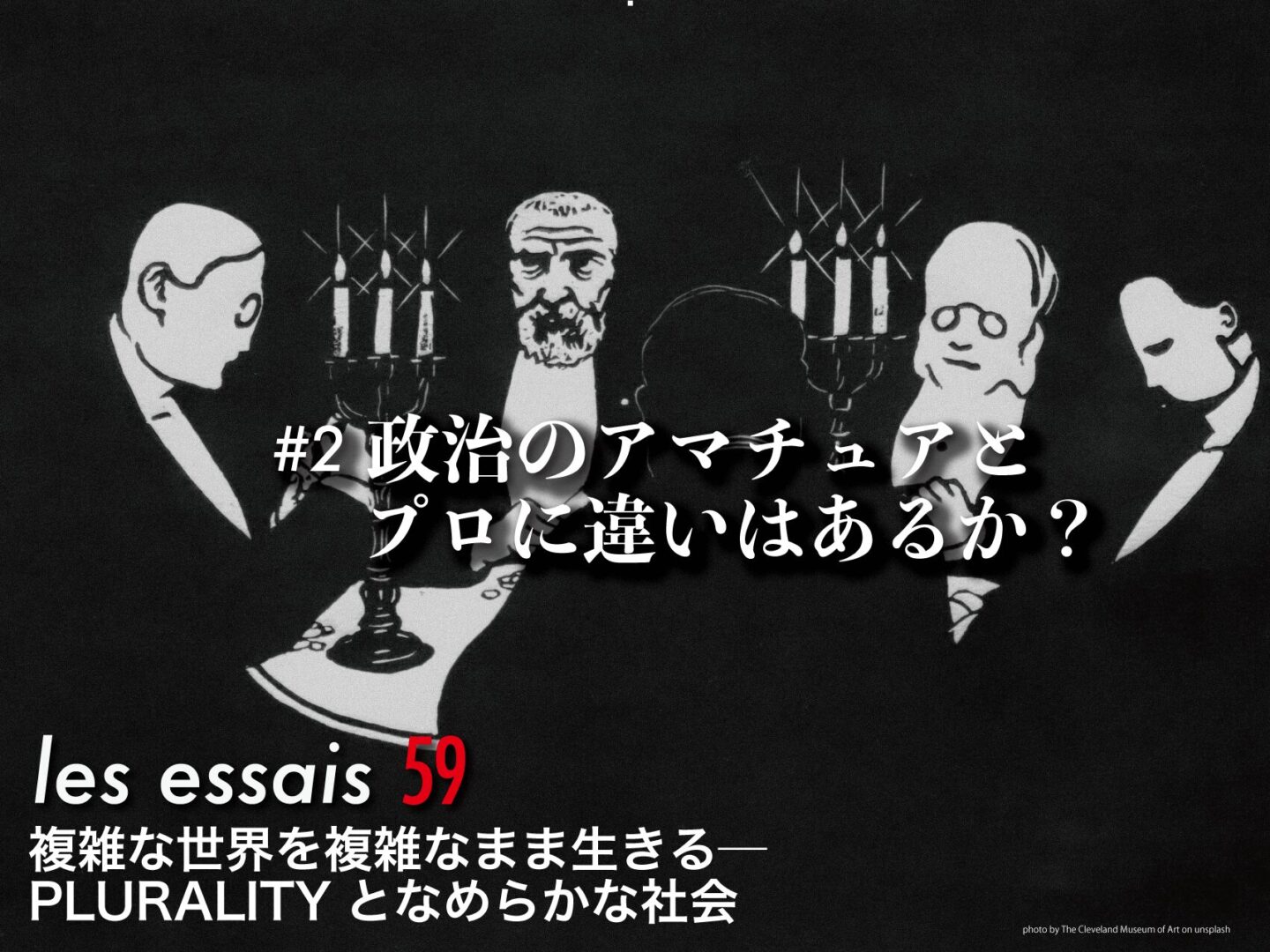
「政治は誰のものか?」という問いは、民主主義社会では当然のようでいて、実は深い疑念を孕んでいる。素人と専門家、民意と政治判断──『日の名残り』やケインズの批判を手がかりに、政治の担い手の正当性を考える。
目次
政治は誰のものか?
政治は誰のものだろう?
民主主義の社会でこんな疑問がわくのもおかしなものだが、玉川氏のコメントといい、わたしが話した若者といい、あるいはオルテガ、あるいは小阪修平の議論を考えると、素朴にそんな思いが頭を過ぎる。
わたしが思い出すことがもうひとつある。カズオ・イシグロの小説『日の名残り』(土屋政雄訳/ハヤカワ文庫)でのエピソードだ。主人である貴族ダーリントン卿の館に集う来客たちを前に、主人公の執事スティーブンスがスペンサーという貴族から、高度な外交問題に対する見解を矢継ぎ早に問われる場面だ。アメリカの債務問題、ヨーロッパの通貨に対するロシア・ボルシェビキの影響、北アフリカの情勢といった内容だ。
このエピソードはちょうど戦間期にあたり、国際情勢が不安定になり非常に複雑な状況を呈していた時代だ。
スペンサーの嫌味な問いかけにスティーブンスは「お役に立てそうにありません」と答える。それによって来客たちの笑いものにされるのだ。重要なのはこの翌日のことだ。
ダーリントン卿はスティーブンスに深く謝罪し、こう言い訳する。
「お前には、じつにひどいことをしてしまった。だがな、スティーブンス、ミスター・スペンサーも一生懸命だったのだ。彼はサー・レナードにあることを証明したかった。いまさらこんなことを言っても慰めになるかどうかわからんが、ある重要な論点の立証にお前はたいへん役に立ってくれた。サー・レナードはな、昔流儀のたわごとを並べていたのだ。国民の意思が最良の仲裁者だ、云々というな……。まったく信じられんことだ」
ジェームズ・アイヴォリーが監督しアンソニー・ホプキンスとエマ・トンプソンが共演した映画「日の名残り」の同エピソードが描かれ印象に残るシーンとなっている。
ここには端的に、政治は一般大衆には任せられないというインテリの蔑みに似た自信がある。しかし、こうした自信を見せたダーリントン卿は、第一次大戦後のドイツの再軍備に寛容であったどころか、ナチスの台頭にさえ理解を示し、館の給仕に雇ったユダヤ人娘を解雇までするのである。第二次世界大戦後、ダーリントン卿はこのことをもってイギリス国内から激しいバッシングを受ける。
先のエピソードが描かれるのは、スティーブンスが旅先で卿に対する憎悪めいた非難を耳にした後のことである。
さらに加えておけば、『日の名残り』の前半のクライマックスである、館で開催された外交問題を話し合う国際会議の最後の晩餐の席で、ダーリントン卿のこの姿勢は、──のちにスティーブンスの主人となる──アメリカ人政治家ルイースに「アマチュア(素人)」という言葉で攻撃される。むしろ、ダーリントン卿が非専門家の扱いされるのだ。卿のイギリス・ジェントルマンらしい意見が素人意見だと厳しく指弾される。
オルテガ・イ・ガセット (著)
佐々木 孝 (翻訳)
早川書房
ジェームズ・アイヴォリー (監督)
アンソニー・ホプキンス, エマ・トンプソン (出演),
COLUMBIA PICTURES
素人の意見に屈して悪手を選択
この会議では第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約に基づくドイツの賠償問題について議論を交わされた。1919年のヴェルサイユ条約では、第一次世界大戦で敗戦したドイツに巨額の賠償金の支払いを義務づけており、ドイツ経済への大打撃が懸念されるなか、賠償緩和についてもさまざまな代替案が話し合われた。
ルイースは「ヨーロッパがいま必要としているものは専門家なのです」と言う。ルイースは、ドイツの賠償緩和という実際のアメリカの外交的立場をかなり反映した意見を訴え、ヨーロッパ側の反論にあっていた。賠償問題の重要性は、ヨーロッパ諸国の国民感情に起因しているし、それは同時にアメリカへの債務返済という課題もあわせもっている。
こうなるとどちらが専門家でどちらが素人かわからなくなる。しかし、その証明は歴史が果たした。卿のアマチュアリズムに基づいた意見は現実の複雑さに対応できなかった。
有名な話だが、経済学者のケインズがパリ講和会議のイギリス代表団顧問として出席した経験をもとに、『平和の経済的帰結』(山形浩生訳/東洋経済新報社)でドイツ賠償金がいかに過酷で実行不可能か、またヨーロッパの経済と政治に深刻な悪影響を及ぼすかを厳しく批判したことも付記したい。ケインズは会議の只中に代表団顧問を辞任し帰国してしまう。
ドイツの戦後賠償の問題とその議論はのちの世界を決定する重要なものだった。そして、高度に専門的な内容であることも間違いない。
ヴェルサイユ条約では、戦勝国であるイギリス、フランスの政府は自国世論の“厳罰要求”に縛られるかたちで講和交渉を進め、賠償や領土割譲など対独強硬路線を選択した。これはある意味で素人の意見であり、それをケインズも厳しく批判し、イギリス代表団の財務顧問として参加していたパリ講和会議から立ち去ったのだ。エスタブリッシュメントであり、天才でもあったケインズにとっては、素人の意見にふりまわされて国際政治が決まることが許せなかったのかもしれない。
そして、このときのパリ講和会議の決定が正しいものであったか、いまやはっきりしており、ケインズの批判を受け容れない者はない。
ジョン・メイナード・ケインズ (著)
山形 浩生 (翻訳, 解説)
東洋経済新報社
関連記事
-
 REVIEW2025.12.12
REVIEW2025.12.12情報の非対称性と終末論のなかで社会的ケアを模索する
第5回 “影の自分”との対話――データ・ダブルとしての私2025.12.12テキスト 都築 正明 -
 REPORT2022.08.01
REPORT2022.08.01量子コンピューターを理解するための 量子力学入門
第3回 「1つの電子は同時に複数の場所に存在する」──2重スリット実験で示された量子力学の実在論2022.08.01テキスト 松下 安武 -
 FEATURE2024.09.19
FEATURE2024.09.19筑波大学名誉教授・精神科医 斎藤環氏に聞く
第4回 文脈把握と不確実性への対処を可能にするシステムとは2024.09.19聞き手 都築 正明








