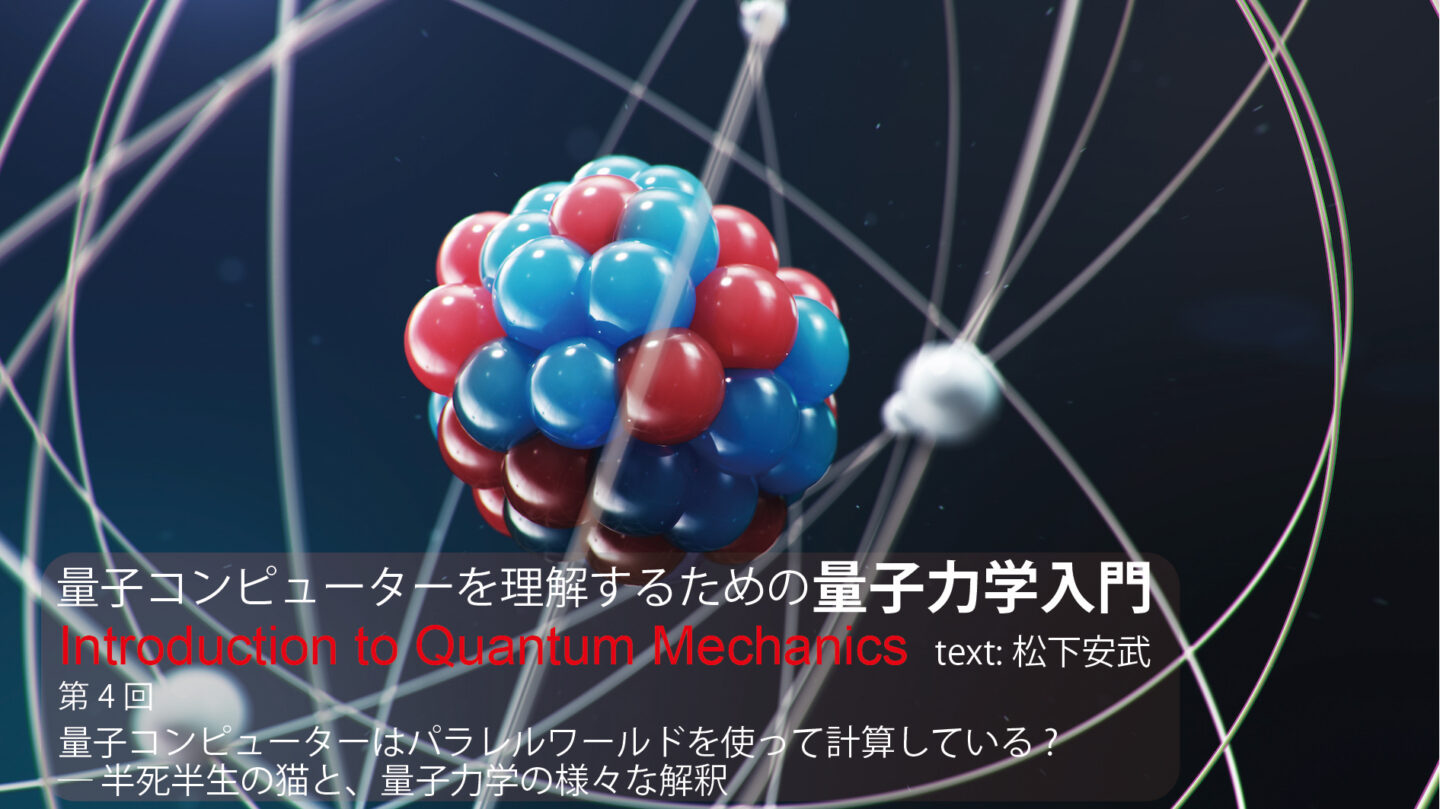AI研究開発は今世紀の核軍拡競争となるのか?

米中において繰り広げられつつあるAIの開発競争になんらかデジャブを感じるのは、かつての米ソの核開発競争を連想するためだろうか。もちろん状況をつぶさに見れば、当時と今を単純に比較できるものではない。だが、覇権を争う国家が世界を巻き込んで人類の命運を翻弄しかねないリスクを抱えていることは同じだ。
目次
1 AI兵器の登場をどう受けとるのか?
5月25日のことだ。いずれ耳にするであろうと思っていたニュースが、しかし思っていたより少し早く届いた。ロシアがAI搭載のロボット兵器の大量生産を開始したという。
AI搭載のロボット兵器「量産開始」…ロシア、兵器名は明かさず
このニュースには3つほど意味がありそうだ。ひとつはロシアが米中のAI開発競争に何らかのプレゼンスを発揮するためのプロパガンダとしての意味。次にウクライナをはじめとするNATO加盟国への軍事的な牽制。そして最後に考えておかなければならないのは、ロシアのみがAI兵器を大量生産しているわけではない可能性だ。AI兵器の開発は進みこそすれ、止まることはない。プーチン大統領が「AIを制する国家が世界を制する」と宣ったことは前にも触れたが、各国リーダーとも同じ認識だろう。
先端テクノロジーによる兵器の登場はほとんど人類の歴史と軌を一にしている。チャリオットも弩も火薬もその登場から、物を壊し、人を殺すための兵器であった。先端テクノロジーが戦争の勝敗を分けてきた。それを否定する者がいるとすれば、歴史を知らない者だけだろう。
ただAI兵器やAIに制御された自律兵器に対する見解はさまざまで、マスコミなどがこぞって煽るような危機感だけで事情を察するのは戒めたほうがいい。
世界の名だたる有識者、AIのみならず哲学や経営学の領域にまでわたってインタビューしたマーティン・フォードの『人工知能のアーキテクトたち ―AIを築き上げた人々が語るその真実』(松尾豊監修/水原文訳/オライリージャパン)からも、見解の相違が端的に見て取れる。
たとえばカリフォルニア大学バークレー校の世界的AI研究者であるスチュアート・ラッセルのように、AI兵器を「新たな軍拡競争の脅威」を高めると考える者もいれば、フェイスブック社の主任サイエンティストであるヤン・ルカンなどは軍隊がAIを活用することでより精密でピンポイントな攻撃が可能となり無闇な殺人が減って、軍隊は警察のような存在に変わると論じている。ホーキングやイーロン・マスクが懸念したような汎用型AIのリスクについては、総じて有識者たちの賛同を得られていないことも面白いが、中国が開発競争の一方の雄であること、特殊な政治体制が優位に働いている点などから警戒心を持つ者も少なくはないのが印象に残る。
もっとも、インタンビューに答える側の研究者に中国系が目立つことも付記しておくべきだろう。
2 全体主義下の科学者の倫理
テクノロジーと兵器をめぐる最も忌まわしい記憶は核兵器であることは同意してもらえるだろう。
1939年に核分裂が発見されたとき、それが兵器に転用できると考える科学者は決して多くはなかった。しかし莫大なエネルギーを生む連鎖反応が兵器になると考えられるまでにさほど時間はかかっていない。折しも時代は第二次世界大戦前の緊張状態にあった。あまり知られていないが、日本の理化学研究所や京都帝国大学でも同じ頃に研究が始まっている。
兵器になると考えられるようになったものの、実用化まで課題は山積だった。最初に兵器化を進めたのはナチスドイツである。不確定性原理を提唱したヴェルナー・ハイゼンベルクは核兵器の完成を未来に見ていた。当時、ナチス占領下のデンマークでニールス・ボーアに対し、原爆開発に相当な困難があると告げたことは有名だ。ただ、その際に開発のヒントとなる原子炉開発のアイデアメモを渡したとされている。ボーアは原子模型を確立し量子力学の発展に大きな寄与を果たした物理学者であり、後にアメリカに亡命している。
戦時中、敵国同士に分かれたこの二人がどんな思いを持っていたか。先端テクノロジーが国家間の争いに使われようとするとき、科学者たちの倫理観とはいかなるものであったか。そんな心情を推察した有名な戯曲に『コペンハーゲン』(マイケル・フレイン/小田島恒志訳/ハヤカワ演劇文庫)がある。日本でも宮沢りえが出演した舞台上演も行われている。
戯曲の中で二人が交わす会話は、暗喩に満ち世界の先行きを不安視しながらも、科学者としての倫理のあり方を追求する内容になっており、深い感銘を得ることができる。
3 ヒトモノカネを集中投下できる国が見せた破壊力
果たしてハイゼンベルグが第二次世界大戦中の原爆開発が無理だと本当に考えていたかは定かではない。史実に残るように原子炉の構造についてはアイデアあった。ただ、それを実現する費用も人材も材料も不足していた。そういえば戯曲『コペンハーゲン』のハイゼンベルグはデンマークから必要な資源を得ようとボーアに協力を申し込もうとしていたようにも映る。
原子力爆弾はこの後、わずか数年で開発が成功する。ハイゼンベルグが開発不能の理由にあげた原子炉を開発しうる才能がアメリカに渡っていたからだ。その名をエンリコ・フェルミという。妻がユダ人であったため、ムッソリーニのイタリアから亡命したのである。その昔、グーグル社が入社試験に使っているされたフェリミ推定の元になった研究者だ。
同様に、アメリカにはナチスドイツやその占領国から亡命してきたユダヤ人科学者が多くいた。家族がユダヤ人であった場合もフェリミと同じである。アルバート・アインシュタインも、先のボーアもアメリカに亡命していた。
ナチスが原爆開発を進めていることを知っていた亡命科学者たちは、ナチスがそれを手にする未来の地獄に恐れ慄いた。彼らはルーズベルト大統領に宛てた原子爆弾の開発を求める書簡に署名し「マンハッタン計画」を発動させた。
アメリカには人材も費用も場所もあった。ほどなくしてフェルミはシカゴ大学に原子炉を完成させる。核分裂の連鎖反応のコントロールに成功したのだ。人類が真に核を手に入れた瞬間と言ってもいい。ここから、マンハッタン計画は一気に進む。ロスアラモスの研究所に、国中の物理学者が集められ、ひとつの街を形成するほどであったという。のちにノーベル物理学賞を受賞したリチャード・ファインマンも、そのベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』上・下(大貫昌子訳/岩波現代文庫)にそこでの暮らしを生き生きと描いている。ファインマンはロスアラモスで最初の妻を失っている。
余談だが、戦後、アメリカの有名レコードレーベル、アトランティックレコードのエンジニアでありプロデューサーでもあったトム・ダウトも戦時中、一人の物理学徒としてマンハッタン計画に参加していたという。ことほど左様に大胆な人材登用ができたのも大国のなせるワザだろう。昨今の中国などのAI研究開発への桁違いのリソース投入もきっと同じだ。
原子力爆弾の開発を巡る展開は『原子爆弾 その理論と歴史』(山田克哉著/講談社ブルーバックス)のほか、さまざまに語られている。ことに当事者だった物理学者たちの伝記にはさまざまな思いが交差して面白い。
4 AI兵器の「相互確証破壊」
1945年8月6日に広島、9日には長崎に原爆が投下される。このうち長崎に投下された原爆「ファットマン」はプルトニウム型である。特殊な構造をもち威力も巨大なこの原子力爆弾の機構を考えたのは、ジョン・フォン・ノイマンである。彼もまたアシュケナジと言われるドイツ系ユダヤ人ではあったが亡命者ではない。
ノイマンといえば、今ではチューリングと並んでコンピュータの父と呼ばれる天才である。ノイマンはマッハタン計画にもすすんで参加しており、上記のように重要な役割を果たした。それだけでなく、同じく天才と称されマッハタン計画を主導したロバート・オッペンハイマーのように戦後、原爆開発を深く悔恨するようなことがなかった。この辺りはもう一方のチューリングが戦争や軍に翻弄されたことを思うと対照的である。
ノイマンは戦後も積極的に軍と関わりを持った。コンピュータの父とされるのは、電子計算機であるENIAC(エニアック)の開発に大きな影響を与えたからだが、ENIACはそもそもアメリカ陸軍が弾道計算を行うために始めたプロジェクトである。
このノイマンを主人公に、米ソ冷戦をめぐるチキンゲームを描いた名作ノンフィクションが『囚人のジレンマ―フォン・ノイマンとゲームの理論』(ウィリアム・パウンドストーン著/松浦俊輔訳/青土社)である。ノイマン自身が確立したゲーム理論のひとつ「囚人のジレンマ」における、2者の裏切りと協調の問題を冷戦期のアメリカとソヴィエトに擬えて語る。
このノンフィクションこそはAIなど先端テクノロジーの研究開発をめぐって繰り広げられつつある、現在の米中対立考察に示唆を与える読み物でもある。核開発テクノロジーの独占によって、アメリカ一国が世界を支配することを恐れた物理学者や哲学者がいたからだ。
この思惑のためにフォックス事件が起きる。ロスアラモス研究所にいたクラウス・フォックスという物理学者が起こしたスパイ事件である。彼はドイツ出身で共産主義者ではあったけれども、単に金やソ連共産党のために情報を盗んだのではない。ただ、この強大な兵器を二国以上が所有することでバランスをとりもどさねば、人類は破滅すると恐れたのだ。今でこそ「相互確証破壊」という核による先制攻撃を牽制する理論から、その考えにある程度の理解は示せるが、当時はマッカーシズムの時代である。フォックスは単なる裏切り者としてしか扱われなかった。
このフィクションが示唆するところ、つまりAI研究開発が米中、あるいはロシア、一国の独占的なテクノロジーとなることに世界の危機が予想されるなら、フォックスのような科学者が登場すると考えてもいいのではないか。
前回の記事のように、個人情報保護への規制が緩く、人口も多くデータ資源が豊富なだけでなく、独裁国家による手厚い保護によって中国だけが、AIの研究開発で圧倒的に先行した場合、「相互確証破壊」のバランスは崩れる。そう考える情報科学者がアメリカに研究データを提供することがあるのではないか。そういう歴史をまたしても歩もうとしているのではないか。そんな想像を刺激されるのである。
5 われわれは覇権がもたらす平和を享受できるか?
ソヴィエトが崩壊してしばらくして、アメリカの政治学者フランシス・フクヤマは『歴史の終わり』上・下(フランシス・フクヤマ/渡部昇一訳)/三笠書房)で、ヘーゲルの歴史観およびアレクサンドル・コジェーヴの講義を元にして、ソ連崩壊によりイデオロギー対立が喪失して歴史が終焉したと論じた。当時から批判の多かった論だが、なんと言ってもアメリカ一国による覇権が歴史の終わりを意味するとは、皮肉にしてもひどすぎる。パクスアメリカーナが歴史の終着点というのは独善でしかない。とはいえ、冷戦の終了がそれほどまでにインパクトを持って迎えられたことだけは事実だ。
そして現在、歴史は少しも終わっておらず新たなイデオロギー対立の時代に向かおうとしているようだ。フクヤマと同時代の政治学者サミュエル・ハンティントンの『文明の衝突』(鈴木主税訳/集英社)めいた対立も浮かんで見えるが、もはや紙幅がない。また、いずれ。