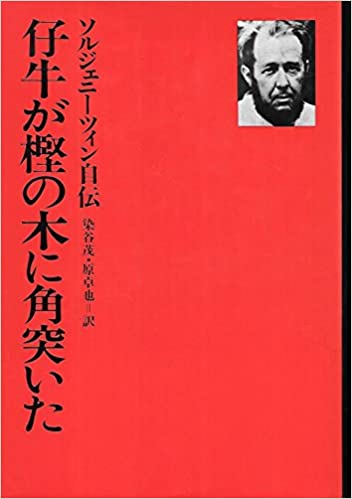私たちが目の当たりにする悲惨は真実の影なのか?

前回の記事から1カ月が経った。書いたのはロシアがウクライナに侵攻した日(2022年2月24日)であった。ウクライナ寄り、あるいはNATO寄りのメディアを一概に信じることはできないが、戦域は拡大しつつもロシアは戦略的には失敗を重ねており国内での厭戦気分も高じているように見られる。
目次
戦争がもたらすロマン、大きな物語
命と尊厳は天秤にかけられるのか?
ソルジェニーツィンとウクライナ
頭の中で書かれた小説
表出を避ける反権力のメッセージ
世界は洞窟の影
戦争がもたらすロマン、大きな物語
この戦争についてさまざまな意見が交わされている。何があっても戦争はすべきでなく、祖国を捨てても逃げるべきとの意見も見られるが、多くはゼレンスキー大統領を支持するもので、大国ロシアに対し一歩たりとも譲歩せず戦い抜くこと、国を守ることへの応援が占めている。原義どおりにロマンある立場と言えるだろう。こうした議論を見るにつけ、私が思い出していたのは、思春期に戦争を体験し、悲惨な有様を「火垂るの墓」(『アメリカひじき・火垂るの墓』新潮文庫)などの諸作品に著した野坂昭如が生前、言っていたことだ。それのなかにこそ、本当の戦争の悲惨を強く感じたからだ。
野坂は大意、次のように語った。
たとえ祖国が失われ陵辱されたとしても戦争だけはしてはいけない。
ここまで強度あるメッセージには、どんな主張も浅薄に思えてしまう。それは私だけだろうか。誤解のないように述べるとすれば、私自身は亡国も陵辱も受け入れ難いし、それを受け入れるぐらいなら死を選ぶほうの人間だと思っている。
だから、野坂のメッセージをかつて学生団体SEALDs(シールズ)のメンバーが言い放った「もし中国や韓国が攻めてくるなら、僕が九州の玄関口で、とことん話して、酒を飲んで、遊んで、食い止めます。それが本当の抑止力でしょう?」のそれと同じく青臭いものだと片付けることも頭と口先ではできるだろう。しかし、野坂のメッセージの強度に圧倒され、私は言葉を失った。それほど戦争とは悲惨なものなのか、と。
すべての戦死は犬死である。そんなふうに思わずにはいられなかった。
犬死にもロマンがある。だからこそ私たちは戦争を止められないのかもしれないが。
そして私自身もそのロマンにもシンパシーを感じてしまうのだ。言うも虚しい。
命と尊厳は天秤にかけられるのか?
ウクライナの徹底的な抗戦について、旧ソヴィエト時代のホロドモールに遡って言及する場面がメディアで見られた。ホロドモールとは当時、ロシアの領域であったウクライナで起きた大飢饉を指す。最高指導者だったヨシフ・スターリンが農業集団化(コルホーズ)を強引に進めるために起こした人為的な飢饉と言われる。ウクライナでは実に全人口の20%にあたる1000万人余りが飢餓で亡くなったとされている。真偽を確かめてはいないのだが、ネット上には死んだ我が子の肉を食用として売る夫婦を写した、目を覆いたくなるようなホロドモール時の写真がある。ナチスがユダヤ人に行ったホロコーストの犠牲者数が600万人と言われていることを考えれば、犠牲者数は桁違いである。
この悲惨と屈辱の記憶が、現在のウクライナをしてロシアには屈してならない、ホロドモールを繰り返してはならないという戦意に繋がっているのではないかとメディアのコメンテーターは語った。人間は命と尊厳を天秤にかけなくてはならないのだろうか。野坂の言うように天秤に命と尊厳をかけるべきではないとも思う。
ただし、戦争を体験した野坂のメッセージのように、ホロドモールの体験者に民族を守るために戦うべきだと言われれば、その強度の前には私はこれまた言葉を失うだろう。
私が戦争について知っていることはあまりに少ない。無知だけが眼前にある。
ソルジェニーツィンとウクライナ
私がホロドモールについて知ったのは、鮎川信夫と吉本隆明の対談を収めた『対談 文学の戦後』(講談社文芸文庫)からである。1970年代に行われた対談だけれども、なかにソヴィエトのいかがわしさ、暗さについての言及があり、ウクライナの暴動と数百万人規模の犠牲者が出たことが書かれている。
『対談 文学の戦後』で、鮎川信夫と吉本隆明はたとえば江藤淳が繰り広げた議論への違和感を述べる。秀才型のインテリが陥る正義、本稿に従ってあえて言えばロマンティシズムへの違和感だ。それはある種の悲壮であり、故に犠牲的である。個が犠牲にならなければならないという、それはファシズムの時代の日本であれ旧ソヴィエトであれ、全体を調律し組織を強化するうえに課されてしまう思想を批判している。
この対談集でたびたび取り上げられる名前に、江藤淳の他に、ソヴィエト出身のノーベル賞作家であるアレクサンドル・ソルジェニーツィンがある。先のホロドモールについても、二人がそれを知ったのはソルジェニーツィンの『収容所群島』(木村浩訳/新潮社、絶版)であると述べている。スターリン批判を経て新左翼が生まれ、そしてそれさえ学生運動の敗北によって衰退し始めた時代に行われた対談だが、やはりまだソヴィエトの実態について誤認がありマルクス主義をいかに実現すべきなのかを問うている。この議論のために、強制収容所を暴くことでソヴィエトの実態を知らせたものとして『収容所群島』が材料にされるのだ。
頭の中で書かれた小説
ソルジェニーツィンはスターリン批判によって強制収容所に送られた。数年にわたり強制労働を行った。その日常を描いたのが、のちにソルジェニーツィンの作品として最初に発表されることになる『イワン・デニーソヴィチの一日』(木村浩訳/新潮文庫)である。この極限のなかに何処かペーソスを感じる独特の傑作はいかに綴られたか。紙もペンにも不自由する強制収容所で、いや紙とペンが十分にあってさえ書くことが許されなかったであろう強制収容所に収監された政治犯の一日の記録は、ソルジェニーツィンの頭の中で綴られ記憶された。頭の中のノートに一文字ずつ記憶として刻むことによって執筆されたのだ。
フルシチョフのスターリン批判演説を経て解放されたソルジェニーツィンは地方の中学校教師をしながら、頭の中の文字を紙に書き写した。その原稿を秘密裏に雑誌に送り、出版の可能性を探った。最終的にはフルシチョフのお墨付きさえ得てソヴィエトで刊行され、ソルジェニーツィンのデビュー作となった。
脳内での執筆から刊行までの経緯については『仔牛が樫の木に角突いた ソルジェニーツイン自伝』 (染谷茂、原卓也訳/新潮社、絶版)で生々しくスリリングに読める。スパイ小説さながらに描写される原稿の受け渡し、刊行が決まり高い評価を得たときの高揚感はエンターテイメント性を感じるほどだ。しかし、この本は非常に大部であるだけでなく、『収容所群島』と同じく絶版である。ちなみに、私は『収容所群島』全6巻を25年前に京王線国領駅の前のブックオフで、1冊100円で手に入れた。当時、すでにソヴィエトはなくソルジェニーツィンは過去の人だったかといえばそうでもなくNHKのドキュメンタリーにも出演することがあった。だから単にブックオフが本の価値を見誤っただけなのだろう。
表出を避ける反権力のメッセージ
頭の中に書かれた作品は検閲を逃れることができる。当然だ。表出されないものを審査することは、神なる存在でもなければできない。
表出されない意思を武器として戦うというSFがベストセラーになっている。『三体』シリーズだ。私はまだ通読できていないしネタバレになるので感想は控えるがモチーフになっているのは、古典物理学から量子力学、情報科学、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーと現在における自然科学のエッセンスばかりであり、知的な喜びも大きく得られるとだけ述べておきたい。
さて、1作目にあたる『三体』(劉慈欣著/立原透耶監修/大森望、光吉さくら、ワン・チャイ訳/早川書房)は中国の文化大革命時代の紅衛兵によるインテリ狩りのシーンで始まる。ここにも社会主義国家の言論や思想への統制が描写されるわけである。そして、この経験こそ、あるいは歴史こそがこの作品の表出されない意思が武器となるというアイデアの源泉ではないかと考えている。それはソルジェニーツィンが強制収容所で頭の中のノートに小説を書き綴ったことと通底する。どんな権力であろうと、私たちの頭の中を支配することはできないという反権力のメッセージだ。権力は見えるもの聞こえるものしか支配できないという批判ともとれる。
世界は洞窟の影
さんざん、頭の中だの脳内だのと述べておいていまさらなのだが、私はそう書きながら私たちの意思は本当に頭の中や脳内だけの現象なのだろうかと疑っている。いや、それは現象ではないかもしれない。意思や心をどのように語ることができるのか。
脳がただの物質であるならば、その最小単位は素粒子である。素粒子であるならば、古典力学は別として量子力学であれば物理学として解明できるはずだ。そう論じたのは以前の記事で『皇帝の新しい心』という著作を取り上げた物理学者のロジャー・ペンローズである。ペンローズは『心は量子で語れるか 21世紀物理学の進むべき道をさぐる』(中村和幸訳/講談社ブルーバックス)で、量子力学がさらに進化発展することで人間の意思や心もいずれは物理学によって数学的に論じうると述べる。意思や心が数学のように法則や定理に従うものと判明した場合、もはやソルジェニーツィンの業は不可能になるかもしれない。なんとなれば、彼の秘められているはずの思想が物理的に表出させうるからだ。
『心は量子で語れるか』は興味深いことに、こうしたペンローズの議論に対し三人の論者が反論し誌上で議論が交わされる。なかでも、かつてはペンローズの盟友であり世界的な発見を共に成し遂げたスティーヴン・ホーキングの反論だ。哲学的も示唆に富んでいる。
引用しておこう。
基本的にペンローズはプラトン主義者で、唯一の物理的実在を記述する、唯一の観念の世界が実在すると信じている。一方、私は実証主義者で、物理理論は私たちが構築する数学モデルにすぎないと思っているし、また物理理論が実在に対応しているかどうかを尋ねるのは無意味で、それらは単に観測結果を予言するかどうかだと考えている。
プラトンのイデア論は、この世の実在はすべて観念であり、私たちが触れる世界とは洞窟の壁に映った影のようなものとする。量子物理学がイデアとして確立すれば、私たちの世界のすべてはそのイデアに統一されるだろう。イデアの世界こそ、完全な真実の世界なのだ。そういう世界が物理学によって実現するのだろうか。それとも、絶対的な世界はなく果てしない相対が続く、影のような世界があるのだろうか。
私たちが目の当たりにする悲惨は真実の影なのだろうか?