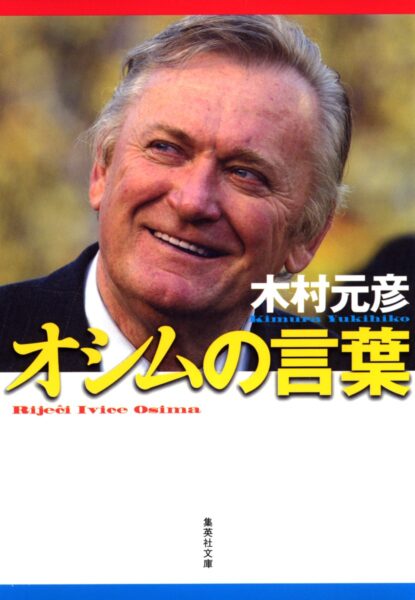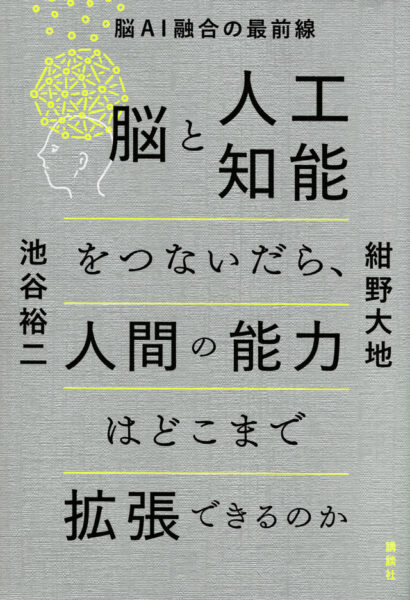ワールドカップが求めた数学的な正しさと、ポストヒューマニズムの行方

これを書いている2022年11月24日は、FIFAワールドカップカタール2022において日本代表が戦前の予想を覆し強豪ドイツ代表を逆転で破った翌日のことである。Jリーグ以降30年、進化を続けてきたサッカー日本代表の最大の成果となる勝利であった。
目次
イビチャ・オシムの論理と哲学
ワールドカップに持ち込まれた数学的正しさ
ポストヒューマニズムをいかに論じるのか
テクノロジーはいかにして“神”になるのか
イビチャ・オシムの論理と哲学
一夜明けて、メディアは喧しい。テレビでもWEBでもサッカーに関心のある、ありとあらゆる人たちが感動を語り、喜びを爆発させ、戦術を評価している。外信で諸外国では、このアップセット、ジャイアントキリングをいかに報じているかを伝え、それぞれの代表ファンの受け止めを切り取る。
ちょうど20年前、日韓大会において日本代表をベスト16に導いたフランス人、フィリップ・トルシエ元監督もワールドカップの全試合を中継する動画配信サービスABEMAの番組に出演、「感動で言葉にならない」としながらも、森保一監督の手腕を褒め称えた。“赤鬼”と呼ばれ激昂すると怒鳴り散らしながら選手を突き飛ばしていたようなトルシエがメガネ姿で嬉しそうにしているのは、関係者でもないのに面映いような気にさせられた。
他にも、西野朗や岡田武史らの代表監督経験者のコメントが続々と寄せられている。おそらく今後、ジーコやザッケローニいった代表監督経験者たちのコメントも聞くことができるだろう。
しかし、私自身が代表監督経験者たちのなかでもっともそのコメントを聞きたかった人物は今年の春、物故した。イビチャ・オシムだ。オシムにこのドイツ戦の勝利をどうしても見せたかった。そして、口を開けば名言というオシムの試合評を聞いてみたかった。そう思っているのは私だけではないだろう。
思えば、今はなきユーゴスラビア代表をオシムが監督として率いた1990年のイタリア大会。そのグループリーグ初戦の相手は奇しくも西ドイツであった。当時も圧倒的強者であった西ドイツ相手に、オシムの奇策も実らずユーゴスラビアは1-4で負けている。次戦以降は立て直し、ストイコビッチの活躍もあって決勝トーナメントに進出、スペインを破るなど準々決勝まで進んでいる。ベスト4をかけたアルゼンチン戦もPK戦までもつれる熱戦であったことはサッカーファンの記憶に残っているだろう。
オシムの魅力は奥行きのある言葉に彩られたその哲学にあった。豊かな比喩で選手のミッションを論じ、研ぎ澄まされた論理で戦術を語った。オシムは、名門サラエヴォ大学の理数学部数学科で数学の学士を得ているだけでなく、哲学をも学んでいる。夫人と出会ったのも数学の家庭教師をしていたからだ。キャリアの選択で「数学かサッカーか」で悩んだという。
サッカーと数学の共通点を見つけるには、そうとうに高度な数学を理解したうえでサッカーをプレーしたことがなければ無理な話ではあるだろうが、オシムの戦術の裏には数学的な確率論や変数の処理があるように見えたのは気のせいだろうか。
オシムの話をすると止まらなくなる。多くの語録が残されているので、読まれたことがない人にはぜひ手に取ってほしい。その言葉はサッカーのためだけでなく、人生のためになるものだからだ。
オシムの人生は戦乱のバルカン半島の歴史に翻弄された。東欧問題に詳しい木村元彦の『オシムの言葉 フィールドの向こうに人生が見える』(集英社文庫)は、オシムの言葉が人生の苦難がもたらされたものだと教えてくれる。オシム自身の手になる『日本人よ!』(長束恭行訳/新潮社)では、そのロジカルな語り口を十分に味合うことができる。
ワールドカップに持ち込まれた数学的正しさ
日本がドイツを破った以上に世界を驚かせた試合があった。FIFAランキング3位、36戦無敗を誇ったアルゼンチンを同51位のサウジアラビアが逆転で破ったのだ。
この勝敗に少なからず影響を与えたと言われるのが、本大会から導入されたAIによる「半自動オフサイド判定」というテクノロジーだ。前大会の2018年ロシアで導入されたVAR(ビデオアシスタントレフリー)に続くもので、それらはセットで活用される。
アルゼンチンとサウジアラビアの試合でも前半25分、アルゼンチンのゴールがVARによって取り消され、モニタの画面にはオフサイドラインを超えたアルゼンチン選手のデジタル画像が映し出された。
半自動オフサイド技術はスタジアムの天井に設置された多数のトラッキングカメラによってボールと選手の位置を正確に測定する。公式試合球にもセンサーが内蔵され、1秒間で50回以上の追跡を可能にしている。
VAR導入の際にも「機械にたよるのか」「サッカーの醍醐味が失われる」という批判が一部にはあったが、当初よりジャッジの公平性を支持するほうが大勢だった。ファンからは微妙なジャッジに対してはすぐにVARを求める声があがるようになった。半自動オフサイド技術も同様であろう。審判へのアピールプレーや審判をうまく欺くプレーであるマリーシアが不可能になり、それを得意とする南米チームが不利になると言われはじめている。そのことを世界中のファンが歓迎している。
ここで思うのだ。私たちはサッカーにおいてさえ、人間よりもAIを信じるようになっている、と。AIの正しさとはつまり自然科学の正しさであり、自然科学の正しさとは数学的な正しさのことにほかならない。デカルトとガリレオが真実の追求のための数学を取り入れて以来、この世界の正しさの最大の根拠は数学である。
サッカーと数学。オシムのそれとは違う意味だが、サッカーの試合を正しいものにするAIは、しかしサッカーを美しいものとして留めてくれるかはまた別の議論が必要だろう。
とはいえ、数学がいかにして人間が「正しい」と認識する基盤を整えてきたのかは非常に興味深いものだ。
数学の進化とは, 正しさの直観能力の進化である. それは人間の悟性が, より抽象的な世界の中に新たな正しさを見出すことである. 『物語 数学の歴史 正しさへの挑戦』
そう論じられるのは数学者の加藤文元の『物語 数学の歴史 正しさへの挑戦』(中公文庫)である。
数学は正しいのみならず、美しいと形容されることが多い。天才数学者たちの証明は「美しい」と感嘆されるものだ。この数学の美しさが、サッカーの美しさに寄与するものであれば、私たちはどんなにか幸福だろう。
ポストヒューマニズムをいかに論じるのか
私はかつてこのレビュー記事の21回目で「神と悪魔と、人間と。量子の世界は知的枠組みの何を変えうるのか?」と題し、科学が神の座を奪ったことから、フリードリヒ・ニーチェが近代の始まりに「神の死」を宣言したこと、そしてそれに続く20世紀、ミシェル・フーコーが「人間の死」を告げたことを書いた。その際、「『人間の死』とは、誤解を恐れず端的にいえば人間原理主義(ヒューマニズム)の死を意味する。」と述べたが、私たちは現在、確実に人間という存在──あるいはすべての実在──の再定義を迫られている。
人間という存在の再定義とは、この原稿の流れでいえばサッカーにおける審判の役割を見直すことに通じている。すべてをデジタルデータとAIがジャッジするのであれば、審判の役割とはなんであろうか? 人間である必要があるのだろか?
ましてや先に見たように、審判よりもAIのジャッジのほうに信をおくのであれば、審判に必要なのは「正しさ」なのだろうか。
ヒューマニズムの次に議論されねばならないのは「ポスト・ヒューマニズム」である。フーコーが述べたのが、生物としてではなく主義としての人間の終焉であったのは間違いないが、2022年の現在、私たちにつきつけられているのは、生物としての人間の終焉すら感じさせる状況だ。端的にはAIの知的能力が一部ではすでに人間のそれを凌駕しており、レイ・カーツワイルがポストヒューマンとして論ずるように、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、ロボット工学といった分野の加速的な進化によって、人間は生物として変化を遂げはじめ、その消滅さえ予測されうる未来が視野に入ってきたのだ。
ポストヒューマンに至る思想的な転回と、いま現在、世界中の哲学者や思想家が向き合っているテクノロジーや資本主義の問題についての思想地図となるのが、哲学者・倫理学者の岡本裕一郎の『ポスト・ヒューマニズム テクノロジー時代の哲学入門』(NHK出版新書)である。ヒューマニズムを超えていくものとしての加速主義、思弁的実在論と、ヒューマニズムを更新しようとする新実在論が対比によって代表的論者の立場を明らかにしながら述べられる。私がこのレビューで数年にわたって論じてきた内容と通底する部分が多くあり、思索の次のヒントを得た。
私は以前、カーツワイルのポストヒューマンとは、かつて神から奪われた進化という超越的な能力をプロテスタント的な反発から人間に取り戻そうという思想ではないかと読み解いたが、岡本は同書のなかで次のように述べる。
カーツワイルがニーチェの思想についてどれほど真剣に考えていたのかは、明らかではない。だが、「人間を超える」という点で、カーツワイルとニーチェがつながっていたことは間違いないだろう。 『ポスト・ヒューマニズム テクノロジー時代の哲学入門』
ニーチェの「超人」とカーツワイルの「トランスヒューマン」はほぼ同じ思想だといえる。この両者は私たちが知っている人間とは別の人間の定義であることは言うまでもない。
テクノロジーはいかにして“神”になるのか
AIと人間の脳をつなぐことで、脳の機能を高めたり、障害を取り除いたりできるのではないかという研究が進んでいる。先日、Twitter社を買収したイーロン・マスクが設立したニューラリンク社はBMI(Brain-computer Interface:ブレインマシン・インターフェイス)を開発している。
ニューラリンク社のBMIは非常に微細なセンサーを脳のなかに埋め込み、脳波を読みとりある種のデバイスを操作できるようにする。これによって、脳内で念じただけでパソコンを操作したり、インターネットから直接的にデータを取り込めたり、視力や聴力に障害のある人に外部デバイスからの視野や音声を届けたりが可能になる。すでに、動物実験ではこうしたことが可能となっている。
もはやSF映画の世界である。当然、これらの開発については猛烈な批判もある。脳神経学者を中心に、人体に与える影響についてだけでなく、動物実験にも動物虐待だと猛烈に批判が起き、計画されていたサルをつかった動物実験は中止されている。
BMIには大別して2つの方法がある。脳を切開して内部にセンサーなどを入れる外科手術を要する「侵襲性」のもの、ヘッドギアなどのツールで脳の外部から脳波を読み取る「非侵襲性」のものである。当然、大きな批判にさらされるのは侵襲性のBMIである。
脳を開いてAIを埋め込むことで、超人が生まれることを想像するのは難しいことではない。おそらくは知的能力の向上のみならず、身体機能の向上も可能であろう。それは私が子供の頃に見た改造人間の姿そのものである。
BMIが非人間的──これ自体、ヒューマニズムの影響下にある基準だ──なものだと非難するのは簡単だし、同意を得るのも難しくはない。しかし、BMIへの期待は医療の側からみれば、単に非難するだけでは終われなくなる。
前述したように、視力や聴力を機械的に回復することができれば、障害者にとって福音でしかない。私自身も数年前に脳梗塞で昏倒し後遺症を患う身だけに、BMIによってかつての体がもどってくるなら、喜んでそんな外科手術でも受けるだろう。
現在の研究では、精神疾患でさえBMIによる治療が期待されているのだ。アメリカのカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームで実際に研究が進んでいる。
患者の気分が鬱状態になったときに脳に電気刺激を与え、鬱気分の改善を図ることに成功しているのだ。研究は進み、脳のどの部分を刺激することで気分がどのように変化するかを調べているという。
現代病として広がる鬱病は、症状を示すバイタルサインが明確になく医者の経験によって診断されている。AIはすでにディープラーニング以前のルールベースの時代からエクスパートシステムとして医療分野で活用が進んでいた。これは、前提となるバイタルサインが明確に表れることでAIの診断を容易にしているからだ。しかし、鬱病をはじめとする精神疾患の多くは、エクスパートシステムのAIでは前提がないために診断が難しかった。これがディープラーニングによって、豊富な診断データをつかってAIが学習を積めば、熟練の医者のように精神疾患を診断することも可能であり、診断にもとづく指示があれば、脳に電気刺激を与えることで症状を緩和させられる。これだけとってもAIの進化とBMIの進化がもたらすものは非常に大きい。
医療と情報科学によって人間という存在ははっきりと姿を変えつつある。そのことを非常に前向きにまとめた書籍が、東京大学で研究を続ける池谷裕二と紺野大地の『脳AI融合の最前線 脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか』(講談社)である。
紺野は同書のなかで、人間の苦のなかでもっとも辛いのは認知症と考え、AIと脳との融合にその治療の可能性を探っているという。
人間が終焉するということは、それは人間が人間の苦しみから脱することでもある。
カーツワイルは老いや死からテクノロジーによって逃れようとしている。私はそれがあたかも自らが神になる行為あるいはテクノロジーが神になることに思えるのだ。
この記事はワールドカップから始まった。ワールドカップに神が降臨したのは、1986年のメキシコ大会、アルゼンチン対イングランドの試合においてである。ふわりとあがったボールはヘディングしようとしたディエゴ・マラドーナの手に当たってゴールに吸い込まれた。マラドーナは「ただ神の手が触れた」と言った。マラドーナはこのゴールの後に“人間業”とは思えない5人抜きゴールを決め、まさにサッカー界の神たる存在になったのである。
そう、VARも半自動オフサイド判定もない時代。スポーツにはまだ神が存在した時代の話である。
もはやスポーツにも神は現れることはなくなるだろう。それがロマンを失うことと同意義だとは私は思わない。なぜなら、そこに数学的な美しさが加えられるかもしれないからだ。