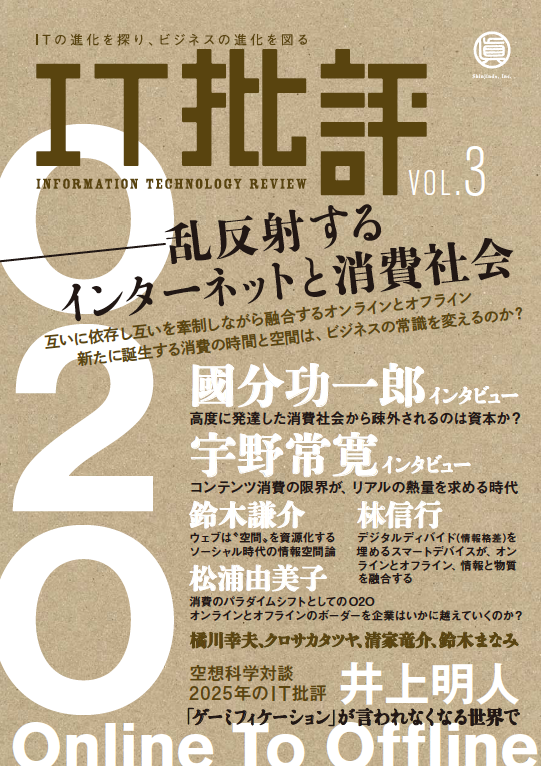パサージュからネットへ〜資本主義の構造転換と消費社会の変容 第2回

清家竜介
あたかも第2次世界大戦前夜を想起されるかのような、時代のうねりが見え隠れする2014年――。
果たして、高度に発達した資本主義社会が世界を歪ませているのか?
そして、この情報通信技術の発達は、古い社会を排除しようとしているのだろうか?
それともまったく新しい社会を準備している途上なのだろうか?
その途上ゆえに、さまざま軋みが世界各地の生じているのか?
ヴァルター・ベンヤミンのメディア論から、消費社会の変容を論じる。
第1回はこちら。
知覚の学としてのメディア論と複製技術
ベンヤミンは、パリの亡命生活の中で、未完の著書『パサージュ論』を準備する傍に「複製技術時代の芸術作品」という重要なメディア論の古典を執筆している。ベンヤミンは、その中で以下のように述べている。
「人間の集団の存在様式が総体的に変化するにつれて、人間の知覚の在り方も変わる。人間の知覚が組織されている在り方│知覚を生じさせるメディア│は、自然の条件に制約されているのではなく、歴史の諸条件にも制約されている」
この論述を先の資本主義の構造転換の問題と結びつけて考えることができるだろう。つまり商品を媒介する貨幣というメディアは、資本主義の構造転換をもたらし、人々の知覚を変容せしめ、理性を腐らせてしまうわけだ。
ベンヤミンは、このような資本主義的生産様式と、所有関係を変更することなく戦争という蕩尽(価値実現と消費)によって資本主義の危機を乗り越えようとするファシズムの猛威に抗するべく、複製技術による集団の知覚の変容の問題を探求していく。
ベンヤミンは、複製技術を、資本主義を推し進める強力な武器であると同時に、資本主義を解体するポテンシャルを持つ両義的なものとして捉えている。
先に述べたように、美的衣装をまとった芸術作品は、神々や貴族階級に仕えるものであった。その時代の芸術作品は、複製されたものでなく、オリジナルであった。巨大なカテドラルとそれを飾るダヴィンチの壁画やミケランジェロの彫刻、レンブラントやベラスケスなどの偉大な芸術家によって王侯貴族の居城や大ブルジョワの大邸宅に架けられた肖像画を思い浮かべればよいだろう。
それらの芸術作品は、まさにオリジナルであり、それを観賞するためには、オリジナルの作品のもとに直接訪れて、礼拝しなければならない。「オリジナルが、今ここに在る」という事実から、芸術作品の真正性の概念が生じ、そこに「アウラ(オーラ)」が現れる。オリジナルとは、伝承や歴史に位置づけられた強力なアウラに包まれていることを特徴とする。
神々に仕える僧侶や王侯貴族は、伝統的なコンテクストによって位置づけられた芸術作品のアウラによって、自らの権威を高めていたのである。
しかしながら、複製技術は、そのようなアウラをまとった芸術作品の権威を揺るがしていく。例えば、グーテンベルクの発明した活版印刷術で印刷された活字の書物であるルターによるドイツ語訳の聖書は、それまでの高価な羊皮紙の上に聖なるラテン語でかかれた写筆の聖書と異なる、大量に複製された安価な商品であった。羊一頭から四枚しか取れない高価な羊皮紙に技巧を凝らして装飾され一字一字ごと写筆された聖書は、まさに最高級の芸術作品であった。紙と活字という新たなメディアは、それまでの書物を覆っていたアウラを奪ってしまった。活版印刷術は、出版資本主義を成立させると同時に、それまでの特権的なアウラに包まれていた聖なる写筆文化を解体していったのである。
革命的メディアとしての写真と映画
ベンヤミンは、様々な複製技術の中でも、写真こそが「真に革命的な複製手段」であると述べている。オリジナルの唯一性と異なり、複製は、二次性と反復性をもっぱらとするが、その中でも写真は、決定的に人々の知覚を変容させるからだ。
写真は、それまでの宗教画や肖像画のように高価ではない。それは、活字の書物と同じように、大衆の手に届くものであり、実際に大衆を求め、大衆のものとなった。
活字が知的世界のアウラを取り去り、それまでの知的な特権階級を解体し平準化していったように、写真は、絵画や彫刻のオリジナルによって占有されていた美的領域を複写して、誰もが近寄れ、持ち運ぶことができるものに転じてしまう。
さらにオリジナルと異なった複製である写真は、対象のクローズアップや動物の素早い動きなどを瞬時にフィルムに定着させ、人間の目に映らなかった無意識的な領域をも可知的なものにする操作性において優れている。
この写真というメディアによって生み出された芸術作品は、それまでの絵画とは異なった集団的知覚の組織化を行う。美的領域を大衆化させ、さらに無意識の領域を集団的知覚へと組み入れてしまうのだ。
ベンヤミンは、このような写真というメディアによって媒介された知覚の在り方に「平等な社会主義への変化」を読み取る。芸術作品を覆っていたアウラを払拭し、美的領域を大衆化させる写真というメディアが「世界における平等性への感覚」を強化すると考えたのである。すなわち写真というメディアによって、芸術作品が、特権者の権威を維持する儀礼から、社会主義的な政治を推し進めるための機能を持つようになったのである。
さらにベンヤミンは、映画に着目する。映画は、静止した写真のフィルムを連続的に連結させたものである。ただし映画は、様々なシーンを捉えたフィルムをモンタージュして編集することで作り出される。シーンを捉える撮影方法もクローズアップやスローモーションなどを駆使する。それは写真と同様、それまで人々の意識に上ることのなかった視覚的無意識の領域を映し出すことができる。
ベンヤミンは、アウラを葬ったフィルムによって構成される映画が、当然、視覚的な無意識の領域を映し出すとともに、それまで人々を支配しているものに対する洞察を深めると、考えた。映画は、旧来のアウラを召喚してきた魔術的テクノロジーに慣らされた牢獄のような日常世界を、高速度撮影というダイナマイトで爆破する。カメラの前には、視覚的な無意識に浸透された別の空間が広がっているのだ。
映画や写真という複製技術は、大衆の自己認識という正当な階級的関心を強化し、彼らの自己認識を深めるポテンシャルを持つとベンヤミンは考えた。それらのニューメディアは、階級構造を明確化することで、大衆(労働者たち)の階級意識を明晰化するものであると考えたのである。もちろんベンヤミンは、大衆達の自己認識という正当な階級的関心が、資本主義によって腐敗した方向へとそらされるという懸念も表明している。新たなメディアを、労働者階級が奪取するのか、ファシストが奪取するのかそれが重要な政治問題であることをベンヤミンは強調していた。
結局、ベンヤミンが危惧していたように、写真や映画の力は、ベンヤミン達ではなく、ファシストや国家主義者達の手に落ちることで大衆の自己認識を曇らせる。そしてベンヤミンは亡命の旅の途中、スペインで囚われの身となり服毒し自らの命を断った。
アメリカに亡命したホルクハイマーとアドルノは、アメリカの文化産業もまた、美的なものを文化商品へと変えることで、労働者の自己認識を誤らせることを認識した。例えばハリウッドなどの映画産業は、スター崇拝などの気晴らしを提供することで、労働者の不満をも商品生産の回路の中に繰り込んでいた。彼らは、ベンヤミンが期待をかけた映画や写真などの複製技術が、大衆の認識を高めるのではなく、資本主義経済の回路を強化している現実に直面したのである。
フォーディズムからポスト・フォーディズムのテクノロジーへ
ベンヤミンの「複製技術時代の芸術作品」の中で、比較的注目されていない「第一の技術」と「第二の技術」という概念がある。この二つの概念は、現代において極めてアクチュアルなものになっている。
ベンヤミンの「第一の技術」とは、人間による自然の制御をもっぱらとする技術である。それは人間社会の必要性から生じる。ベンヤミンは、その特徴として、「やたらと人間を投入するもの」であることを指摘している。例えば、ピラミッドや万里の長城の建築などを想起すればよいだろう。また太古の宗教における神々への生け贄や太平洋戦争における零戦の特攻などは、生命を投入する自己犠牲的行為の極として考えられる。それらは、実のところ礼拝的価値によって権威づけられ、魔術的なアウラに取り巻かれた権力と結びついたものである。
もう一つの「第二の技術」は、人間による自然の制御ではなく、人々を労働の苦役から解放し、人間と自然との遊戯へと向かうものである。「第二の技術」は、自然と人間との遊戯が、たゆまず多様化していくものであるとベンヤミンは言う。それは労働者を解放し、遊戯へと向かう。例えば、対象の遠隔操作やロボット技術などが典型といえよう。
実のところ、ポスト・フォーディズムと呼ばれる資本主義の蓄積体制は、この第二の技術のポテンシャルを高めている。
1970年代初頭まで支配的であったフォーディズムという資本蓄積体制は、「大量生産─大量消費」を特徴とする。フォーディズムは、生産過程を細部まで分解し、ベルトコンベア式の単純な流れ作業へと組み立て直した生産ラインを構築することで商品を大量生産した。
しかしながら、生産過程に組み込まれた労働者達は、熟練工のような創意工夫を発揮する機会を奪われる。それとともに、機械的な単純作業の与えるストレスに耐えることが困難となり、沢山の離職者が生じる。フォーディズムでは、労働者を引き留めるために、高賃金を与えることでこの問題を切り抜けようとした。
こうしたフォーディズムのテクノロジーは、高賃金を労働者に支払うといえども単純な苦役を強いるという意味で、ベンヤミンのいうところの「第一の技術」の系譜に属すると言える。
労働者は、高賃金を得ることによって、フォーディズムのテクノロジーが大量生産した商品を大量消費することができた。第二次大戦後の先進諸国における福祉政策にも支えられ、商品を作れば作るほど売れる「規模の経済」が成立し、未曾有の好景気をもたらした。
だが1970年前後にフォーディズムのテクノロジーによって先進諸国の経済は成熟飽和となり、世界経済の景気は後退局面に入る。成熟飽和経済とは、フォーディズムのテクノロジーによって大量生産された自動車、テレビ、冷蔵庫などの耐久消費財が各家庭に行き渡ってしまい、その販路を失ってしまうほど経済が成熟した状態を指す。
このフォーディズムがもたらした資本主義の危機からポスト・フォーディズムという資本蓄積体制の模索が生じてくる。
ポスト・フォーディズムは、「多品種少量生産」を特徴とする。多品種少量生産は、フォーディズムによって成熟飽和した経済において、商品の微細な差異を競うことで、商品を売り続けようとする戦略に基づいている。車や家電などを流行遅れの洋服のように古びたものに見せるため、マーケティングや広告に費用をかけて演出することが必要となったのだ。マーケティングや広告業の隆盛は、生産と消費の次元を、たんに安くて良い物を作ることではなく、消費者との一種のコミュニケーションの次元へと押し上げていく。それは経済と美的なものの交わる領域を拡大させるものであった。
反生産的となったフォーディズムの乗り越えを目指して、ポスト・フォーディズムのテクノロジーは、資本主義経済における生産と消費の在り方を、言語コミュニケーションへと接近させ、記号的消費を特徴とする消費社会を現出せしめたのである。この消費社会を生み出したポスト・フォーディズムのテクノロジーは、ベンヤミンの言う「第二の技術」の在り方に接近している。というのも生産と消費が、生産者と消費者の「遊戯」の領域に近づいているのだ。日本では80年代からバブル崩壊にかけて、記号消費が花盛りであった。