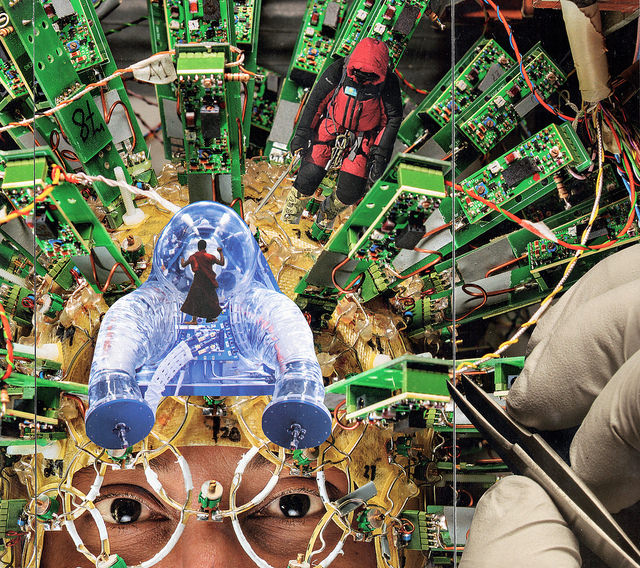ITproのための「ももクロ論」補論⑤

桐原永叔
4回にわたって、ITサービスとの関連のなかから、ももいろクローバーZの人気の秘密について、読み解いてきた。見えてきたのは、消費行動を可視化、理論化を押し進めるITサービスの潮流とは、まったく異質なものが大きな人気を得ようとしている現状である。最終回は、ももいろクローバーZの活動と、その人気が示したものに、どんな可能性があるのかを探っていく。
ここまでの話→① ② ③ ④
第5話 理論化できないももいろクローバーZ。クラスターを破壊するラディカルなイノベーション
最後に音楽産業に起きたイノベーションの話をしたいと思う。レコード会社は長らくコンテンツビジネスの雄であったが、今世紀の入り、軒並み苦境に立たされていることは周知のとおりだ。IT技術の発達とインターネットの普及によって、音楽コンテンツはダウンロードされ、コピーされるよういになり、レコード・レーベルは急激な衰退を余儀なくされたのである。
音楽コンテンツのネット配信というイノベーションがもたらしたものは、それまでの音楽産業に起きた数度の変化とはまったく違ったものだった。72回転のSPから33回転のLP、録音技術のデジタル化、レコードからCDといったこれまでの変化は、既存の企業にとって決して不利に働くことがなかった。
顧客を創造しえなくなった既存の音楽産業
しかし、CDからネット配信への変化は、まったく連続性なく破壊的に、ラディカルなイノベーションとして訪れ、既存のレコード・レーベルはもはや、ドラッガーの言葉を借りれば、顧客を創造しえなくなったのである。
新たな顧客を創造し始めたのは、IT企業とイベント興行企業である。1曲ごとにネットからダウンロードされることによる「シングルへの回帰」と、音楽がイベントとして消費される「フェスの隆盛」である。
そしてもうひとつ、音楽産業に訪れたラディカルなイノベーションによってマネタイズの仕組みが解体されたことも見落とせない。今日まで、商品として流通させられるのは、楽譜などの印刷物、レコード、CDなどの記録媒体のようにテキスト化できるもののみであり、著作権は音楽出版社や管理事業者が、記録媒体に収められた演奏やパフォーマンスなどに対する権利(著作隣接権)は、レコード・レーベルがマネタイズしてきた。パフォーマーの権利は著作隣接権として保護されているが、とはいってもテキストにも情報にもできない“音”、たとえば、バンドのグルーヴや即興的なパフォーマンスにおける再現不能な“絶妙さ”といったものは未だに保護されず、したがってマネタイズもなされていない。
しかし、フェスが隆盛する時代において、複製不能なリアルの体験こそがフェスを訪れる観客のニーズの大きな部分を占めているとすれば、音楽業界はグルーヴのようなものをいかにマネタイズしていくか、この課題にこそ取り組まなければならないだろう。
そしてマネタイズを考えれば、その価格をいかに決めるかも避けては通れない課題だ。梅棹忠夫は、早くから、情報(値段のつきにくいもの)の価格設定は、お布施つまり寄付的行為というカタチでしか実現しないといった。寄付的行為化するとは、コミュニティなどの集団内における関係が、価格の基準になるということだともいえる。SNSによって、個の生産性を維持しながら連帯する消費者たちにはもはや、企業がおこなってきたセグメンテーションによるアプローチは功を奏さないようにも思える。
既存の性別や年齢、社会的地位や購入履歴によるセグメントがまったく不能になるとは思わないが、たとえばフィスクの行った消費者の生産活動の3分類(「記号論的生産性」、「言明的生産性」、「テキスト的生産性」)に従ったセグメントいったものを考案する必要はあるではないか。実際、インターネットのユーザーには、ただ批評を書く(「言明的生産性」の)ためだけに、商品やサービスを購入する者さえいるのだから。こうした消費者を、その購入履歴のデータからプロファイリングするだけで分析できるのだろうか? 「隠れた」「影の」経済活動は資本や企業の論理から、ほとんど無意識的に逃れる性質のものではないのか?
技術と神秘
結論に向かううえで断っておきたいのは、わたしは決してITの進化に対して懐疑的であったり、ノスタルジーを主張したりするつもりはないことだ。むしろ現在のITビジネスが把握しきれないもの、見落としてきたと思える問題でさえ、さらなる技術の進歩によって解決を模索する以外のやり方は、危険でしかないと思っている。
たとえば、吉本隆明はリベラル派の論客でありながら(という言い方自体に語弊があるかもしれないが)、80年代に湧いた反原発の動きに対して、原発の問題を解決するには技術の進化しかその方法はないと主張した。「子どもたちに原発のない未来を」といった情緒に傾きがちな訴えには、情緒的な反論しか存在せず、根本的な解決など見えようはずもない。
であるならば、技術の進化こそ原発の問題を解決する糸口になり得るのであり、より安全な原発稼働の技術こそを考えるべきではないかと主張したのである。情緒的な議論でリアルな現状を見失いかけていたなかで、技術の進歩こそ目の前の難題を人間が努力で解決しうる唯一最大の方法と思考したことに共感を覚えている(誤解のないようにいっておくが、現在ある「豊かな国づくりのためには原発が必要」といった議論も情緒的すぎて、わたしには受け入れがたいものだ)。
同時に、技術進化などの理論化に対抗してでてくる神秘性や宗教性といったものが危険なものであることもよく承知している。これらは、企業論理など比にならないほどに、人々を惑わせるものであるからだ。消費活動から疎外されるだけならいいが、生活や人生といったものからさえ疎外させうるパワーをもっているものだ。
何がいいたいのかといえば、もっとも危ないのが、技術を神話で補おうとすること、神秘を理論で無視するということではないか。そして、それによって個々の考えを疎外してしまうことではないか。昨今の「現代のベートーベン」「割烹着のリケジョ」といった、特定の個性に付与された神話が、どれほどまでに合理的な理解を遠ざけるものであるかを思い出しておきたい。
再定義の時代
ITサービスと技術の進歩についても同じ論理が当てはまると思う。可視化、システム化を推し進めてきたことによって生じた綻びがあるとすれば、それは技術の進歩を否定して神秘的なものに依存するのではなく、全く新しい観点を取り入れたアプローチによってイノベーションを模索することこそ近道なのであり、そのためにリセットボタンを押してしばし思考を巡らせることも有用だろう。
わたしは『IT批評』を創刊したとき、インターネットに代表される情報技術は、あらゆるものに再定義を迫ると考えた。電子書籍は書籍というのもの定義を、電子マネーは貨幣の定義を、ネット選挙は政治の定義を変えうるという意味だ。IT化は、決してリアルの代替物ではないからだ。ただの代替物として、既存の商品やサービスをエンパワーメントするものとして、IT化を捉ええていれば、新しい観点をもつことは難しい。
だからこそ、可視化、システム化とは縁遠い活動形態をとってきたことで模倣のできない独自性を発揮し、ファンを動員してきたももクロを、大衆文化の定義を改めて考え直す契機と感じてしまったのだ。これが『ももクロ論』を書く大きな動機となった。
ここまであまりふれられなかったが、ももクロもその活動においてインターネットの恩恵を多分に享受している。AKB同様に、インターネット上にはコミュニティが存在するし、YouTubeには著作権など無関係にファンが編集(生産)した動画が溢れている。Ustreamでも早くから自分たちの姿を配信してきた。ツイッターでも運営側からの情報が配信されている。
しかし、その手法はリアルの代替物とは呼びがたいものだ。たとえばUstreamの動画配信などは、まったく別のアイドルの意味づけを創出しているようにみえる。テレビ放送的なコードに準じながら、Ustreamであるがゆえにどんどん(グダグダというべきか)逸脱しいくためだ。テレビ番組を模していながら、かえってそのために、テレビ番組を不法に占拠したかのような、ももクロのUstream番組が意味するものは、一般の人が配信する番組以上に、テレビ放送が解体される姿を見せつけられようであった。
それこそ、アイドルを再定義してしまうラディカルな存在に見えるために、いい歳をした大人をふくめて、クラスターを破壊してファンを広げているのではないか。それに比べると、AKBは芸能界におけるアイドルという意味で、持続的イノベーションの域にあるようにも思える。
ももクロの魅力の正体こそが、ITサービスの進歩の方向性のヒントとなり得るのではないかという考えはしばらく変わりそうにない。神秘性を帯びながら技術によってみずから神秘性を破壊し、技術的な進歩をえながらも、すぐに理論化できない領域に踏み出してしまう存在(コンテンツ)の今日的な象徴として。ラディカルなイノベーションの基点となるトリックスターとして。
価格を決定させ、消費者にゆだねる
再び、AKBとももクロの対比を参考にするなら、ITシステムの持つエッセンスを最大限利用し、アイドルという商品の人気を徹底的に理論化し、テンプレート化して大量再生産を可能して今世紀的ビジネス手法で成功したAKBに対し、理論づけや予測、視覚化することともっとも縁遠い活動形態をとっているももクロの人気は、まだ勢いを失っていない。
ももクロの魅力は可視化、システム化どころかテキスト化さえ拒む。いわば、マネタイズしにくいものの本流である。しかし、そのこと自体がももクロの強い魅力となり、ファンを動かし、人々を動員するパワーの源であるとしたら、その魅力を解明し、そこから見えてくるものがあるのではないだろうか。
ももクロの動員力の正体は何か。それはライブおける彼女たちの即興を引き出そうとする演出とともに存在するライブの一回性の魅力を抜きには語れないだろう。マネージャーである川上アキラ氏はももクロに歌唱力がないことを理解したうえで、「技術がないからこそ、プロレスの前座のように感情を見せるしかない」と語り、意図的、戦略的な活動より、むしろ感情、情熱が先行させ、進めてきたように見える。それは、プリミティブなものづくりの情熱とも似ている。
再現でも模倣でもない、一回限りの即興性によってステージに生きているのがももクロだとすれば、それこそが、再現可能性、複製可能性をコンテンツの主たる内容としているAKBとの最大の違いだろう。わたしを含め、それまでアイドルなどというものがみずからの生活、趣味のスペースに入る余地などないと思っていた大人たちが、ももクロに惹かれていったのは、偶発性の高いリスクを孕んだパフォーマンスによって現れる緊張と高揚、それが生み出すライブの一回限りの瞬間に事故のように衝突してしまったためだ。
ももクロの「システム化」されない活動、このライブの一回性の魅力こそセグメント、クラスターを破壊するパワーであり、そのことによって多岐にわたる趣味嗜好からのファンを獲得し、彼らをももクロに共鳴させている。
ITサービスがユーザーにシステム化されていないコンテキスト(それはユーザーが自由に選択し得るコンテキストといってもいい)を解放し、運営を委ねることができたなら、セグメント、クラスターを横断するボーダーレスなユーザーを獲得し得るのではないだろうか。そしてそこでは「隠れた経済活動」と「影の文化経済」が駆動することが期待できるだろう。その成否は、マネタイズの過程での価格設定でさえユーザーに委ねるという立場の逆転が起こるかもしれないのだが。